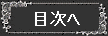シャワーもメイクも完璧にすませた、午前9時。
お腹がすいたね! ってコトになった私たちは、近所
のファミレスでモーニングセットを食べている。
スクランブルエッグとハッシュドポテト。ソーセージ
とサラダに、焼き立てのパンが2つ。
気取ることなくペロッと平らげて店内を見渡すと、う
まっている10席のうち8席がカップルなことに気づい
た。
あの子も、あの人も……。私みたいに幸せな朝を迎え
たのかなぁ。
妙な仲間意識を覚えて、自分勝手に赤面する。
「身体……キツクないか?」
向かい合わせの席で蒼くんは、いつにもまして優しか
った。
本日3度目の類似質問。
テーブル越しに左手を伸ばし、壊れものを扱うように
私の頬を撫でる。
「悪い、本当。俺、さっきは寝ぼけてて……」
朝一で私の躰に深く触れたことを、蒼くんは可愛いく
らいに反省していた。
別にイイのに。
2回目しても……私はぜんぜん、良かったのに。
彼がこんなにも自己嫌悪におちいってるのは、シーツ
に残った鮮血を目にしちゃったからかもしれない。
初めての証。
それを見つけて気恥ずかしさでいっぱいになった私を、
無言で、でも嬉しそうなカオで抱き寄せたんだ。
「まだ、その……痛むか?」
「ふふっ。もう大丈夫だってば。朝はね、少し痛かった
んだけど。今は違和感があるってくらいなの」
「違和感?」
「……ううん。何でもない! それより、コレありがと
う。毎日ずーっと付けるからね」
落ちつきなく足をバタバタさせて、私は胸もとの蝶を
シャラッと揺らした。
あれから改めてつけてもらったネックレスは、今一番
の宝物。
ちょうちょが5匹動くたびに表情を変えて、すっごく
キレイなの。
「ほら、見て〜。こーするとね、チャームが横にゆらゆ
らするんだよ〜。でね、キラキラなの〜」
ペンダントを掲げて光に透かしてみせると、蒼くんは
「プッ」と吹きだすように笑い、愛しむような目で私を
見つめた。
「良かった、気に入って。のこと考えて選んだら、
自然と蝶しか目に入らなかった」
「うん。すごく好きだよ〜」
「女の子って感じだな。お前は可愛いものが似合うから」
「……え……(きゃぁぁぁぁ〜!!)」
昨日までとは絶対的に違う、心の距離。
見えない糸でギュッと結びつけられた気がして、もう
恐いものなんて何もなかった。
良かった。蒼くんと一つになれて。
今日という日に。
お見合いの前に……。
幸せな時間を壊したくなくて、まだこの話題にはふれ
てなかったのだけど。
そろそろ現実と向き合わなきゃダメかもしれない。
そして蒼くんも同じことを考えてたみたいだった。
「あとどのくらい……何時まで、一緒にいられる?」
食後のコーヒーを喉に流しこみ、彼は静かに口をひら
いた。
「うん、あとちょっとかな。10時までには帰ってきな
さいって、お母さんに言われてて……」
「え?」
私の言葉が意外だったらしく、蒼くんは目を丸くする。
「……お前のおばさんって、俺とのこと知ってるのか?」
「あ、うん。お母さんには話したの。蒼くんと付き合っ
てることも、イブのことも。無断外泊はさすがに心配す
るかなぁって」
「そうか……」
あ……何か聞きたそう。でもそれをグッと押し殺して
る。
2人の間に今日初めての沈黙が流れる。
蒼くんの頭に広がってる疑問は、何となく想像できた。
『お見合いの件、お母さんはどう考えてるのか』
常にストレートを投げつける彼が躊躇っているのは、
今まで会話に登場させるのを避けていた私の――家の
事情を察してだ。
「……あのね。うちのお母さんもね……。天力者だ子孫
だ〜のしがらみの中でお嫁にきた人で……。二十歳の時
にお父さんとお見合い結婚してるの」
ちょうど今の私と同じ感じでね……なんて、ちょっと
緊張気味に話すと、蒼くんは「うん」と落ちついた相槌
をうって姿勢をさりげなく正した。
「でもお母さんのトコは天力者とか、代々伝わってきた
とかそういう家柄でもなくて。ただのお嬢さま育ち、と
いうか。うちの一族では発言力のない、よそ者扱い……
というか……」
おっとりしたお母さんがあの厳格なお父さんのもとで、
ガチガチの宗家の中で。ずっと疎外感をもちながら生活
してきたことを私も八純もよく知っている。
小っちゃい頃、2人でよく語ったんだ。
『お母さんを早く自由にさせてあげたいね』って。
それなのに私もまた自由を求めるから、しわ寄せはぜ
んぶお母さんのところにいっちゃう。
「……だからね、お母さんに助けてとは言えないの」
サラッと口にして笑ってみせると、蒼くんは「うん」
ともう一度大きく頷いた。
そしてテーブルの上で無意味にストローの紙を折る私
の手をギュッと握り、癒すように微笑んでくれる。
「初めからそのつもりだろ? むしろあのウチん中に、
の理解者がいるって分かって安心した」
「蒼くん……」
どうしてそんな風に、いつも前向きに考えてくれるん
だろう。
メンドウくさくないの? けっこうオオゴトだよ?
この血筋が足かせで、まともに恋愛なんてできなかっ
たのに。
(初カレが……蒼くんでホント良かった……)
彼は『天力者の姫』じゃない私を大切にしてくれる、
唯一の人なの。
「好き――」
真っ直ぐな瞳に導かれるように、思わずマジ告白して
しまった。
驚いた蒼くんは一瞬フイッと視線をそらし、耳を赤く
しながらこめかみを引っ掻く。
「家で……食えば良かったな。朝飯」
「え?」
「何か今、お前にすごくキスしたい」
「……!」
ドキドキが止まらなかった。
口角を上げてはにかむ、少し幼い表情の蒼くんが愛し
くて。胸がきゅんって鳴って。
ここがファミレスだなんてこと、ぜんぜん気にならな
くなっちゃうの。
「イイよ……して」
シャワーもメイクも完璧にすませた、午前9時。
お腹がすいたね! ってコトになった私たちは、近所
のファミレスでモーニングセットを食べている。
スクランブルエッグとハッシュドポテト。ソーセージ
とサラダに、焼き立てのパンが2つ。
気取ることなくペロッと平らげて店内を見渡すと、う
まっている10席のうち8席がカップルなことに気づい
た。
あの子も、あの人も……。私みたいに幸せな朝を迎え
たのかなぁ。
妙な仲間意識を覚えて、自分勝手に赤面する。
「身体……キツクないか?」
向かい合わせの席で蒼くんは、いつにもまして優しか
った。
本日3度目の類似質問。
テーブル越しに左手を伸ばし、壊れものを扱うように
私の頬を撫でる。
「悪い、本当。俺、さっきは寝ぼけてて……」
朝一で私の躰に深く触れたことを、蒼くんは可愛いく
らいに反省していた。
別にイイのに。
2回目しても……私はぜんぜん、良かったのに。
彼がこんなにも自己嫌悪におちいってるのは、シーツ
に残った鮮血を目にしちゃったからかもしれない。
初めての証。
それを見つけて気恥ずかしさでいっぱいになった私を、
無言で、でも嬉しそうなカオで抱き寄せたんだ。
「まだ、その……痛むか?」
「ふふっ。もう大丈夫だってば。朝はね、少し痛かった
んだけど。今は違和感があるってくらいなの」
「違和感?」
「……ううん。何でもない! それより、コレありがと
う。毎日ずーっと付けるからね」
落ちつきなく足をバタバタさせて、私は胸もとの蝶を
シャラッと揺らした。
あれから改めてつけてもらったネックレスは、今一番
の宝物。
ちょうちょが5匹動くたびに表情を変えて、すっごく
キレイなの。
「ほら、見て〜。こーするとね、チャームが横にゆらゆ
らするんだよ〜。でね、キラキラなの〜」
ペンダントを掲げて光に透かしてみせると、蒼くんは
「プッ」と吹きだすように笑い、愛しむような目で私を
見つめた。
「良かった、気に入って。のこと考えて選んだら、
自然と蝶しか目に入らなかった」
「うん。すごく好きだよ〜」
「女の子って感じだな。お前は可愛いものが似合うから」
「……え……(きゃぁぁぁぁ〜!!)」
昨日までとは絶対的に違う、心の距離。
見えない糸でギュッと結びつけられた気がして、もう
恐いものなんて何もなかった。
良かった。蒼くんと一つになれて。
今日という日に。
お見合いの前に……。
幸せな時間を壊したくなくて、まだこの話題にはふれ
てなかったのだけど。
そろそろ現実と向き合わなきゃダメかもしれない。
そして蒼くんも同じことを考えてたみたいだった。
「あとどのくらい……何時まで、一緒にいられる?」
食後のコーヒーを喉に流しこみ、彼は静かに口をひら
いた。
「うん、あとちょっとかな。10時までには帰ってきな
さいって、お母さんに言われてて……」
「え?」
私の言葉が意外だったらしく、蒼くんは目を丸くする。
「……お前のおばさんって、俺とのこと知ってるのか?」
「あ、うん。お母さんには話したの。蒼くんと付き合っ
てることも、イブのことも。無断外泊はさすがに心配す
るかなぁって」
「そうか……」
あ……何か聞きたそう。でもそれをグッと押し殺して
る。
2人の間に今日初めての沈黙が流れる。
蒼くんの頭に広がってる疑問は、何となく想像できた。
『お見合いの件、お母さんはどう考えてるのか』
常にストレートを投げつける彼が躊躇っているのは、
今まで会話に登場させるのを避けていた私の――家の
事情を察してだ。
「……あのね。うちのお母さんもね……。天力者だ子孫
だ〜のしがらみの中でお嫁にきた人で……。二十歳の時
にお父さんとお見合い結婚してるの」
ちょうど今の私と同じ感じでね……なんて、ちょっと
緊張気味に話すと、蒼くんは「うん」と落ちついた相槌
をうって姿勢をさりげなく正した。
「でもお母さんのトコは天力者とか、代々伝わってきた
とかそういう家柄でもなくて。ただのお嬢さま育ち、と
いうか。うちの一族では発言力のない、よそ者扱い……
というか……」
おっとりしたお母さんがあの厳格なお父さんのもとで、
ガチガチの宗家の中で。ずっと疎外感をもちながら生活
してきたことを私も八純もよく知っている。
小っちゃい頃、2人でよく語ったんだ。
『お母さんを早く自由にさせてあげたいね』って。
それなのに私もまた自由を求めるから、しわ寄せはぜ
んぶお母さんのところにいっちゃう。
「……だからね、お母さんに助けてとは言えないの」
サラッと口にして笑ってみせると、蒼くんは「うん」
ともう一度大きく頷いた。
そしてテーブルの上で無意味にストローの紙を折る私
の手をギュッと握り、癒すように微笑んでくれる。
「初めからそのつもりだろ? むしろあのウチん中に、
の理解者がいるって分かって安心した」
「蒼くん……」
どうしてそんな風に、いつも前向きに考えてくれるん
だろう。
メンドウくさくないの? けっこうオオゴトだよ?
この血筋が足かせで、まともに恋愛なんてできなかっ
たのに。
(初カレが……蒼くんでホント良かった……)
彼は『天力者の姫』じゃない私を大切にしてくれる、
唯一の人なの。
「好き――」
真っ直ぐな瞳に導かれるように、思わずマジ告白して
しまった。
驚いた蒼くんは一瞬フイッと視線をそらし、耳を赤く
しながらこめかみを引っ掻く。
「家で……食えば良かったな。朝飯」
「え?」
「何か今、お前にすごくキスしたい」
「……!」
ドキドキが止まらなかった。
口角を上げてはにかむ、少し幼い表情の蒼くんが愛し
くて。胸がきゅんって鳴って。
ここがファミレスだなんてこと、ぜんぜん気にならな
くなっちゃうの。
「イイよ……して」
 ちょっと前までは公共の場で堂々とイチャつくカップ
ルのこと、冷ややかな目で見てたのに。
恥ずかしい人たち! って、蔑んでたのに。
もお、本当にゴメンナサイ。
恋人同士はいつだって別の空間で息をしちゃうんだね。
立てかけてあったメニュー表で目隠しをして、私たち
は柔らかく口づけた。
触れ合っているだけで無敵。
どんよりした曇り空が、そこだけ陽だまりに変わるの。
ちょっと前までは公共の場で堂々とイチャつくカップ
ルのこと、冷ややかな目で見てたのに。
恥ずかしい人たち! って、蔑んでたのに。
もお、本当にゴメンナサイ。
恋人同士はいつだって別の空間で息をしちゃうんだね。
立てかけてあったメニュー表で目隠しをして、私たち
は柔らかく口づけた。
触れ合っているだけで無敵。
どんよりした曇り空が、そこだけ陽だまりに変わるの。
<<前へ 次へ>>
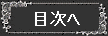
 シャワーもメイクも完璧にすませた、午前9時。
お腹がすいたね! ってコトになった私たちは、近所
のファミレスでモーニングセットを食べている。
スクランブルエッグとハッシュドポテト。ソーセージ
とサラダに、焼き立てのパンが2つ。
気取ることなくペロッと平らげて店内を見渡すと、う
まっている10席のうち8席がカップルなことに気づい
た。
あの子も、あの人も……。私みたいに幸せな朝を迎え
たのかなぁ。
妙な仲間意識を覚えて、自分勝手に赤面する。
「身体……キツクないか?」
向かい合わせの席で蒼くんは、いつにもまして優しか
った。
本日3度目の類似質問。
テーブル越しに左手を伸ばし、壊れものを扱うように
私の頬を撫でる。
「悪い、本当。俺、さっきは寝ぼけてて……」
朝一で私の躰に深く触れたことを、蒼くんは可愛いく
らいに反省していた。
別にイイのに。
2回目しても……私はぜんぜん、良かったのに。
彼がこんなにも自己嫌悪におちいってるのは、シーツ
に残った鮮血を目にしちゃったからかもしれない。
初めての証。
それを見つけて気恥ずかしさでいっぱいになった私を、
無言で、でも嬉しそうなカオで抱き寄せたんだ。
「まだ、その……痛むか?」
「ふふっ。もう大丈夫だってば。朝はね、少し痛かった
んだけど。今は違和感があるってくらいなの」
「違和感?」
「……ううん。何でもない! それより、コレありがと
う。毎日ずーっと付けるからね」
落ちつきなく足をバタバタさせて、私は胸もとの蝶を
シャラッと揺らした。
あれから改めてつけてもらったネックレスは、今一番
の宝物。
ちょうちょが5匹動くたびに表情を変えて、すっごく
キレイなの。
「ほら、見て〜。こーするとね、チャームが横にゆらゆ
らするんだよ〜。でね、キラキラなの〜」
ペンダントを掲げて光に透かしてみせると、蒼くんは
「プッ」と吹きだすように笑い、愛しむような目で私を
見つめた。
「良かった、気に入って。のこと考えて選んだら、
自然と蝶しか目に入らなかった」
「うん。すごく好きだよ〜」
「女の子って感じだな。お前は可愛いものが似合うから」
「……え……(きゃぁぁぁぁ〜!!)」
昨日までとは絶対的に違う、心の距離。
見えない糸でギュッと結びつけられた気がして、もう
恐いものなんて何もなかった。
良かった。蒼くんと一つになれて。
今日という日に。
お見合いの前に……。
幸せな時間を壊したくなくて、まだこの話題にはふれ
てなかったのだけど。
そろそろ現実と向き合わなきゃダメかもしれない。
そして蒼くんも同じことを考えてたみたいだった。
「あとどのくらい……何時まで、一緒にいられる?」
食後のコーヒーを喉に流しこみ、彼は静かに口をひら
いた。
「うん、あとちょっとかな。10時までには帰ってきな
さいって、お母さんに言われてて……」
「え?」
私の言葉が意外だったらしく、蒼くんは目を丸くする。
「……お前のおばさんって、俺とのこと知ってるのか?」
「あ、うん。お母さんには話したの。蒼くんと付き合っ
てることも、イブのことも。無断外泊はさすがに心配す
るかなぁって」
「そうか……」
あ……何か聞きたそう。でもそれをグッと押し殺して
る。
2人の間に今日初めての沈黙が流れる。
蒼くんの頭に広がってる疑問は、何となく想像できた。
『お見合いの件、お母さんはどう考えてるのか』
常にストレートを投げつける彼が躊躇っているのは、
今まで会話に登場させるのを避けていた私の――家の
事情を察してだ。
「……あのね。うちのお母さんもね……。天力者だ子孫
だ〜のしがらみの中でお嫁にきた人で……。二十歳の時
にお父さんとお見合い結婚してるの」
ちょうど今の私と同じ感じでね……なんて、ちょっと
緊張気味に話すと、蒼くんは「うん」と落ちついた相槌
をうって姿勢をさりげなく正した。
「でもお母さんのトコは天力者とか、代々伝わってきた
とかそういう家柄でもなくて。ただのお嬢さま育ち、と
いうか。うちの一族では発言力のない、よそ者扱い……
というか……」
おっとりしたお母さんがあの厳格なお父さんのもとで、
ガチガチの宗家の中で。ずっと疎外感をもちながら生活
してきたことを私も八純もよく知っている。
小っちゃい頃、2人でよく語ったんだ。
『お母さんを早く自由にさせてあげたいね』って。
それなのに私もまた自由を求めるから、しわ寄せはぜ
んぶお母さんのところにいっちゃう。
「……だからね、お母さんに助けてとは言えないの」
サラッと口にして笑ってみせると、蒼くんは「うん」
ともう一度大きく頷いた。
そしてテーブルの上で無意味にストローの紙を折る私
の手をギュッと握り、癒すように微笑んでくれる。
「初めからそのつもりだろ? むしろあのウチん中に、
の理解者がいるって分かって安心した」
「蒼くん……」
どうしてそんな風に、いつも前向きに考えてくれるん
だろう。
メンドウくさくないの? けっこうオオゴトだよ?
この血筋が足かせで、まともに恋愛なんてできなかっ
たのに。
(初カレが……蒼くんでホント良かった……)
彼は『天力者の姫』じゃない私を大切にしてくれる、
唯一の人なの。
「好き――」
真っ直ぐな瞳に導かれるように、思わずマジ告白して
しまった。
驚いた蒼くんは一瞬フイッと視線をそらし、耳を赤く
しながらこめかみを引っ掻く。
「家で……食えば良かったな。朝飯」
「え?」
「何か今、お前にすごくキスしたい」
「……!」
ドキドキが止まらなかった。
口角を上げてはにかむ、少し幼い表情の蒼くんが愛し
くて。胸がきゅんって鳴って。
ここがファミレスだなんてこと、ぜんぜん気にならな
くなっちゃうの。
「イイよ……して」
シャワーもメイクも完璧にすませた、午前9時。
お腹がすいたね! ってコトになった私たちは、近所
のファミレスでモーニングセットを食べている。
スクランブルエッグとハッシュドポテト。ソーセージ
とサラダに、焼き立てのパンが2つ。
気取ることなくペロッと平らげて店内を見渡すと、う
まっている10席のうち8席がカップルなことに気づい
た。
あの子も、あの人も……。私みたいに幸せな朝を迎え
たのかなぁ。
妙な仲間意識を覚えて、自分勝手に赤面する。
「身体……キツクないか?」
向かい合わせの席で蒼くんは、いつにもまして優しか
った。
本日3度目の類似質問。
テーブル越しに左手を伸ばし、壊れものを扱うように
私の頬を撫でる。
「悪い、本当。俺、さっきは寝ぼけてて……」
朝一で私の躰に深く触れたことを、蒼くんは可愛いく
らいに反省していた。
別にイイのに。
2回目しても……私はぜんぜん、良かったのに。
彼がこんなにも自己嫌悪におちいってるのは、シーツ
に残った鮮血を目にしちゃったからかもしれない。
初めての証。
それを見つけて気恥ずかしさでいっぱいになった私を、
無言で、でも嬉しそうなカオで抱き寄せたんだ。
「まだ、その……痛むか?」
「ふふっ。もう大丈夫だってば。朝はね、少し痛かった
んだけど。今は違和感があるってくらいなの」
「違和感?」
「……ううん。何でもない! それより、コレありがと
う。毎日ずーっと付けるからね」
落ちつきなく足をバタバタさせて、私は胸もとの蝶を
シャラッと揺らした。
あれから改めてつけてもらったネックレスは、今一番
の宝物。
ちょうちょが5匹動くたびに表情を変えて、すっごく
キレイなの。
「ほら、見て〜。こーするとね、チャームが横にゆらゆ
らするんだよ〜。でね、キラキラなの〜」
ペンダントを掲げて光に透かしてみせると、蒼くんは
「プッ」と吹きだすように笑い、愛しむような目で私を
見つめた。
「良かった、気に入って。のこと考えて選んだら、
自然と蝶しか目に入らなかった」
「うん。すごく好きだよ〜」
「女の子って感じだな。お前は可愛いものが似合うから」
「……え……(きゃぁぁぁぁ〜!!)」
昨日までとは絶対的に違う、心の距離。
見えない糸でギュッと結びつけられた気がして、もう
恐いものなんて何もなかった。
良かった。蒼くんと一つになれて。
今日という日に。
お見合いの前に……。
幸せな時間を壊したくなくて、まだこの話題にはふれ
てなかったのだけど。
そろそろ現実と向き合わなきゃダメかもしれない。
そして蒼くんも同じことを考えてたみたいだった。
「あとどのくらい……何時まで、一緒にいられる?」
食後のコーヒーを喉に流しこみ、彼は静かに口をひら
いた。
「うん、あとちょっとかな。10時までには帰ってきな
さいって、お母さんに言われてて……」
「え?」
私の言葉が意外だったらしく、蒼くんは目を丸くする。
「……お前のおばさんって、俺とのこと知ってるのか?」
「あ、うん。お母さんには話したの。蒼くんと付き合っ
てることも、イブのことも。無断外泊はさすがに心配す
るかなぁって」
「そうか……」
あ……何か聞きたそう。でもそれをグッと押し殺して
る。
2人の間に今日初めての沈黙が流れる。
蒼くんの頭に広がってる疑問は、何となく想像できた。
『お見合いの件、お母さんはどう考えてるのか』
常にストレートを投げつける彼が躊躇っているのは、
今まで会話に登場させるのを避けていた私の――家の
事情を察してだ。
「……あのね。うちのお母さんもね……。天力者だ子孫
だ〜のしがらみの中でお嫁にきた人で……。二十歳の時
にお父さんとお見合い結婚してるの」
ちょうど今の私と同じ感じでね……なんて、ちょっと
緊張気味に話すと、蒼くんは「うん」と落ちついた相槌
をうって姿勢をさりげなく正した。
「でもお母さんのトコは天力者とか、代々伝わってきた
とかそういう家柄でもなくて。ただのお嬢さま育ち、と
いうか。うちの一族では発言力のない、よそ者扱い……
というか……」
おっとりしたお母さんがあの厳格なお父さんのもとで、
ガチガチの宗家の中で。ずっと疎外感をもちながら生活
してきたことを私も八純もよく知っている。
小っちゃい頃、2人でよく語ったんだ。
『お母さんを早く自由にさせてあげたいね』って。
それなのに私もまた自由を求めるから、しわ寄せはぜ
んぶお母さんのところにいっちゃう。
「……だからね、お母さんに助けてとは言えないの」
サラッと口にして笑ってみせると、蒼くんは「うん」
ともう一度大きく頷いた。
そしてテーブルの上で無意味にストローの紙を折る私
の手をギュッと握り、癒すように微笑んでくれる。
「初めからそのつもりだろ? むしろあのウチん中に、
の理解者がいるって分かって安心した」
「蒼くん……」
どうしてそんな風に、いつも前向きに考えてくれるん
だろう。
メンドウくさくないの? けっこうオオゴトだよ?
この血筋が足かせで、まともに恋愛なんてできなかっ
たのに。
(初カレが……蒼くんでホント良かった……)
彼は『天力者の姫』じゃない私を大切にしてくれる、
唯一の人なの。
「好き――」
真っ直ぐな瞳に導かれるように、思わずマジ告白して
しまった。
驚いた蒼くんは一瞬フイッと視線をそらし、耳を赤く
しながらこめかみを引っ掻く。
「家で……食えば良かったな。朝飯」
「え?」
「何か今、お前にすごくキスしたい」
「……!」
ドキドキが止まらなかった。
口角を上げてはにかむ、少し幼い表情の蒼くんが愛し
くて。胸がきゅんって鳴って。
ここがファミレスだなんてこと、ぜんぜん気にならな
くなっちゃうの。
「イイよ……して」
 ちょっと前までは公共の場で堂々とイチャつくカップ
ルのこと、冷ややかな目で見てたのに。
恥ずかしい人たち! って、蔑んでたのに。
もお、本当にゴメンナサイ。
恋人同士はいつだって別の空間で息をしちゃうんだね。
立てかけてあったメニュー表で目隠しをして、私たち
は柔らかく口づけた。
触れ合っているだけで無敵。
どんよりした曇り空が、そこだけ陽だまりに変わるの。
ちょっと前までは公共の場で堂々とイチャつくカップ
ルのこと、冷ややかな目で見てたのに。
恥ずかしい人たち! って、蔑んでたのに。
もお、本当にゴメンナサイ。
恋人同士はいつだって別の空間で息をしちゃうんだね。
立てかけてあったメニュー表で目隠しをして、私たち
は柔らかく口づけた。
触れ合っているだけで無敵。
どんよりした曇り空が、そこだけ陽だまりに変わるの。