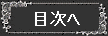◇ 3.俺のもの 〜 蒼 〜
金曜の夜、宮が送ってきた月の画像から始まったラインのトーク。
どこに遊びに行きたいかって尋ねた俺の送信が、既読になったままぷつりと途切れた時点で悪い予感はした。
4限終了後の大学のカフェテリア。
総務課に提出するプリントを仕上げている俺の向かいの席で、宮はどこか心ここにあらずだ。
新作メニューの『伊予柑のホワイトチョコケーキ』とか何とかいうのが出たら真っ先に食べたい! って先週まで張り切ってたくせに。
目の前の皿にはほとんど興味を示さず、浮かない顔でセットの紅茶にチビチビと口をつける。
「何かあったか?」
返しの予測できる捻りのない問いかけを、 我慢できずに投げかける。
「え? 別に何もないよっ」
宮はそう言って笑うけど、何もないわけがない。
さっきから目線が合うたびにわずかに伏せてそらすのは、俺に後ろめたい事があるからだろう。
あいつと……何かあったか?
そう頭の端にチラリと過った不安を、涼しい顔で抑え込めないほどに心が波立っていた。
けど、ストレートにぶつける勇気はない。
俺は柱にかかる時計に目をやりながら、反応を探るようにその名を呟く。
「天海のやつ遅いな」
宮はビクッと肩を跳ねさせ、明らかな動揺を見せた。
「え……しーちゃん来るの?」
「ああ、悪い。言ってなかったっけか? 貸してた去年度のレポートを、ここで受け取ることになってる」
「へぇ……そうなんだね。うんっ……」
声を上ずらせながら、宮はわざと気にしてない素振りを見せる。
嘘のつけないヤツ。そういうとこに惹かれてるのに、こんな時は少しばかり厄介だ。
「それより、それ食わねーのか?」
靄のかかる感情をいったん振り切り、俺は皿の上のケーキを指さした。
「もちろん食べるよ!」
指摘されると宮は少し慌てた様子でカチャンとフォークを鳴らし、見るからに大きすぎる一口を頬張る。
「わぁ、おいしいっ。クリームがわりと濃厚!」
「そりゃ良かった」
今日一番の笑顔が見られた事に、俺は心から安堵した。宮が笑ってくれるなら何個でも食わせてやりたい。
宮が最後の一切れを食べ終わる頃、カフェテリアの出入口が急に騒がしくなって、天海が来たんだとすぐ分かった。
男女を問わない視線が渦を巻いて、相変わらずあいつの周囲は花が咲いたようだと思う。
芸能活動の場を広げてからの天海はますますその存在感を強め、天力者とは別の光のオーラをまとっていた。
あいつは室内を見渡して、まず宮の後ろ姿を見つける。そしてそれから俺まで視線を伸ばし片手を上げると、颯爽とこちらに近づいてきた。
「ありがとね、これ。蒼の文体はどれも噛み砕いた言葉が使われていて、スルッと頭に入ってきたよ」
感嘆の言葉をそえて資料の入ったクリアファイルを差し出した天海は、その後、当然のように宮の隣に座った。
退けられた鞄を多少不服そうに受け取りながら、じと目で幼なじみを見上げる宮。それを気にも留めず、ひょうひょうと会話を続ける天海。
特だん珍しくもない光景に俺はホッと胸を撫で下ろす。
何かあった気まずさで2人がお互いを避け合ってでもしたらどうしようか……なんて、勘ぐりすぎだったかもしれない。
今日の授業の難しさを嘆き、日中のこの蒸し暑さをなじり。俺達3人は何てことない話題を、『ながら喋り』して時間を共有した。
ふとして天海が、目の前にあるしわしわになった銀紙を乗せただけの皿に視線を落とした。
「ねーそのセリが食べたのってさ、新作の伊予柑のケーキ?」
「うん、そうだよ。甘酸っぱくておいしかった〜」
ケーキに話題が移ったあたりで、俺は自分の作業に集中し黙々とペンを走らせていた。
宮の嬉しそうな声が頭上に響いて、下を向いたまま自然と口元が緩む。
「ホワイトチョコが絶妙で、スポンジがふわふわでね。1個ペロリと食べちゃった」
「ふ〜ん、前評判通りの味だったってわけね。だからもう買えなかったんだ」
「え? しーちゃん食べたかったの?」
「いや、そうじゃないけど。それって限定10個でしょ? 昼に売り切れ看板出てたの見かけたからさ。今、セリが食べてるのが不思議で」
「蒼くんがね、キープしておいてくれたの。顔見知りの厨房の人に頼んでくれたんだって」
「ふ〜ん……」
ん?
弾むように交わされていた二人の会話。天海の声の温度が急に下がった気がして、気になって顔を上げる。
あいつはテーブルに頬杖をついて少し斜めに構えながら、俺と目が合うと小さく笑った。
「蒼ってば甘やかしすぎじゃない? そういう小間使いみたいなことしてると、セリってばすぐ調子にのるよ」
「小間使いって……古すぎんだろ。アホ。さんざん手をかけてきたお前が何言って――」
「うん、だからね。そういうの僕だけでイイからさ」
必要以上に口角を上げて微笑む天海だけど、言葉のニュアンスが妙に引っかかる。
ジョーク? 気のせい? いつもと違うノリに一抹の不安を覚え、僅かに鼓動が速まっていく。
俺は戸惑って、次の言葉を飲みこんだ。
そんな俺に天海は一瞬挑発的ともいえる目を向けると、まるで見せつけるかの様にゆっくりと宮の右手をとった。
「クリームついてるよ」
「え? どこ?」
「ほら、この指のとこ」
そう言うとそのまま自分の口元に引き寄せ、ペロッと躊躇いなく舌で舐めとる。
「っ!?」
人目もはばからず大胆なことをやってのける天海に、俺は声にならない叫びをあげた。
思わずガタンッと大きく椅子を鳴らして立ち上がる。と同時に、どこからか女達の悲鳴のような声も上がる。
 「ん〜甘っ」
天海はちょっと顔をしかめ、「これは男子向けじゃなないね」なんて、悪びれなく振る舞った。
いや、そうじゃねーだろ。常識的に考えて、それは行き過ぎじゃねーのか?
誰が見ても熱っぽい男女のやりとり。幼なじみの領域を完全に超えてると思うのは、きっと俺だけじゃないはずだ。
カフェテリアは学部という隔たりを排した交流の場として、大勢の学生が行き来している。そんな場所で周囲を証人にして、こいつは俺に一体何を見せたいんだろう。
でもその行為以上に、視界に入った宮のカオが俺の心を更に混沌とさせた。
紅潮した頬も潤んだ瞳も、らしくない。
天海に対してこんな『女』の反応を見せるなんて、俺の前では一度だってなかったのに――。
「ねえ、蒼。久しぶりに軽くいかない? 付き合ってよ」
「ん〜甘っ」
天海はちょっと顔をしかめ、「これは男子向けじゃなないね」なんて、悪びれなく振る舞った。
いや、そうじゃねーだろ。常識的に考えて、それは行き過ぎじゃねーのか?
誰が見ても熱っぽい男女のやりとり。幼なじみの領域を完全に超えてると思うのは、きっと俺だけじゃないはずだ。
カフェテリアは学部という隔たりを排した交流の場として、大勢の学生が行き来している。そんな場所で周囲を証人にして、こいつは俺に一体何を見せたいんだろう。
でもその行為以上に、視界に入った宮のカオが俺の心を更に混沌とさせた。
紅潮した頬も潤んだ瞳も、らしくない。
天海に対してこんな『女』の反応を見せるなんて、俺の前では一度だってなかったのに――。
「ねえ、蒼。久しぶりに軽くいかない? 付き合ってよ」
 目の奥にさっきまでとは違う穏やかな色を浮かべて、天海はジョッキを構える身振りをした。
「あ、セリは先に帰っててね。男飲みだからさ」
「えっ、何で? イヤよ! 私は蒼くんと一緒に……」
動揺を隠してすがるようにこちらに手を伸ばす宮。俺はそれを「ごめん」と柔らかく押し戻し、できる限りで笑う。
「行ってきてもいいか? 夜いつもの時間に電話するから」
宮は別れ間際まで、表情に困惑と不満の色を浮かべていた。
当然だ。日々の時間に追われて彼氏らしいこともできないでいるくせに、天海の誘いはあっさりと受けたりして。
でも今は何を削ってでも天海と向き合うことを優先したかった。
宮に関して常に曖昧な立ち位置をキープしてきたコイツが、俺のとこまで降りてきた気がする。
その機会をみすみす逃せないと思ったんだ。
青波大の裏にある古びた居酒屋に入り、俺達は生ビールだけを注文した。
レトロな古材のテーブルは所々ささくれ立ち、背もたれのない赤い丸イスは体重をかけると左右にガタついている。
2階に雀荘をもつこの店はむしろそっちの出入りがメインなようで、酒を飲む場としてはあまりにも閑散としていた。
『乾杯』と目で合図するに留めて、運ばれてきたジョッキを半分くらい空ける。天海と2人で酒を飲むなんてどれぐらいぶりだろう。
楽しい話じゃないと分かっているのに、懐かしいこの感じが心地よかった。
でもそれはやっぱり、ここまでの話。
店主らしきおばあさんが客に呼ばれて階段を上がると、1階は貸切状態になる。
そこを見計らって、天海は崩していた体を正し真っ直ぐに俺を見据えた。
「この前、セリに正式にプロポーズしたよ。そんでもって強引に押さえつけてキスした」
「なっ……!!」
予想の少しだけ上をいった告白。
無理やりというニュアンスにカッときて咄嗟に胸ぐらをつかんだ。
プロポーズよりも、こいつが直接宮に触れたことが許せない。どんな場所で、どんな風に? その時宮はどんなカオをしたんだろう。
想像するだけで巡る感情が沸点を超えてしまいそうになる。
もう近づくな! と叫べれば、どんなに楽だろう。でも俺は知ってるから、こいつらを繋ぐ鎖はそんな簡単に切れねーって分かってるから。
いったん深呼吸で冷却して、掴み上げたシャツの襟を解放する。
「この前まで卒業するまでは傍観するとか、俺らの事は応援するだとか何とか言ってなかったっけか?」
睨みつけることで精いっぱい感情を抑えた。
わざと意地の悪い聞き方をして反撃を待ってみるが、天海の変わらない表情に痺れをきらし我慢できずに追撃する。
「宮は俺のものだ」
その一言に、天海はぴくりと眉を動かした。
そしてフッと薄く笑み、抑揚のない声でぽつりと呟く。
「うん……。完全にスイッチ入った」
挑発的とは違う強い意志を孕む眼差し。しまった、ヤバイとこをこじ開けたんだって、本能で悟る。
「僕はずっとさ、セリの自由を守ってあげたくてそばにいたんだよね。『天力者の姫』っていう立場からただ逃げたって仕方ないじゃん?
ぶつかり続けるのも疲れるし、ならその箱庭を少しでも広げてあげようって」
どこか遠い目をして時おり口元を綻ばせ、天海は宮への素直な想いを語り始めた。
天力継承者を生み育てることを義務づけられた宮の人生。ならその時が来るまでとことん甘やかして、色んな経験をさせてあげようと子供ながらに覚悟を決めたと言う。
「だからね、初めての恋愛なら応援してあげたいって思ったのはホント。蒼がイイヤツなのは知ってるし、宮家の事情込みで愛し合えるならこういうのもアリじゃんって思ってた」
でも今……と一端区切りをおいて、残ったビールを流し込む。
「改めて気づいちゃったよ。たとえ蒼でも、セリを『俺のもの』って豪語されるのは面白くない。もう1ミリもあの躰に触れて欲しくないってね」
整った顔で毅然と言い放つ天海を、俺はわずかな恐怖心をもって眺めた。
現に付き合ってる男に向かって、よくもそんな強気な発言ができるもんだと呆れて鼻で笑ってみせる。
遅すぎんだよ、どアホ! 同じ視点から宮を見ていた俺には、お前の気持ちは出逢った頃からだだ漏れだった。
なのに煮え切らない態度が腹立たしくて、同時に脅威で。そういうの全部飲みこみながら2人の間に割って入るのに、俺がどんだけ勇気がいったか分かるか?
やっと手にいれたんた。好きだって言われて、躰も繋がって。あいつの世界に寄り添っていきたいと本気で思ってる。
はいそーですかって、簡単に手離してたまるか!
でも――。
その一方で近頃ひどく感じる心のズレ。想い合う心が行き違い、優先すべきをどこか外している気がする。
宮は俺に甘えない。ワガママを言わない。無理も要求しない。
ちゃんと頼れよ! 天海には素で求めるくせに! って、事あるごとにもどかしく感じるのに、俺に受け止めるだけの器がないのも事実だから苦しい。
そもそも付き合ってから1度だって、あいつの中に天海の影が見えない日なんてなかった。
触れ合うのが自然で寄り添うのが当然で、慕う気持ちは友達とか恋人のそれを当に超えていて――。本人が否定してもむしろ日々濃くなっている事に、俺は嫌でも気付かされる。
きっと今も昔も無意識に、宮の中に天海と別々の道を歩くなんていう選択肢はないんだよ。
だから俺達は行きつく先を想像できずに、あれから一歩も進めないでいるんだ。
「……お前の気持ちは分かった。でも、決めるのは宮だ」
あらゆる感情を押し殺して、ついて出たのはそんな綺麗事。
「うん」
天海は小さく頷いて切なげに笑う。
「ごめん、蒼。セリを本気で奪いにいくね」
…………。
ああ。ついに言いやがった。
コイツに形振り構わず行かれたら、きっと俺なんか一溜りもない。
もうどう転んでも今まで通りじゃ済まされない所まで来たんだって、明確に悟った。
たまらなくなった俺は自分の前髪をグシャリと握り、逃げ場を探すように机に視線を落とす。
並んだ2つのビールジョッキがこれからの俺達と対比して、とても空しいものに映った。
目の奥にさっきまでとは違う穏やかな色を浮かべて、天海はジョッキを構える身振りをした。
「あ、セリは先に帰っててね。男飲みだからさ」
「えっ、何で? イヤよ! 私は蒼くんと一緒に……」
動揺を隠してすがるようにこちらに手を伸ばす宮。俺はそれを「ごめん」と柔らかく押し戻し、できる限りで笑う。
「行ってきてもいいか? 夜いつもの時間に電話するから」
宮は別れ間際まで、表情に困惑と不満の色を浮かべていた。
当然だ。日々の時間に追われて彼氏らしいこともできないでいるくせに、天海の誘いはあっさりと受けたりして。
でも今は何を削ってでも天海と向き合うことを優先したかった。
宮に関して常に曖昧な立ち位置をキープしてきたコイツが、俺のとこまで降りてきた気がする。
その機会をみすみす逃せないと思ったんだ。
青波大の裏にある古びた居酒屋に入り、俺達は生ビールだけを注文した。
レトロな古材のテーブルは所々ささくれ立ち、背もたれのない赤い丸イスは体重をかけると左右にガタついている。
2階に雀荘をもつこの店はむしろそっちの出入りがメインなようで、酒を飲む場としてはあまりにも閑散としていた。
『乾杯』と目で合図するに留めて、運ばれてきたジョッキを半分くらい空ける。天海と2人で酒を飲むなんてどれぐらいぶりだろう。
楽しい話じゃないと分かっているのに、懐かしいこの感じが心地よかった。
でもそれはやっぱり、ここまでの話。
店主らしきおばあさんが客に呼ばれて階段を上がると、1階は貸切状態になる。
そこを見計らって、天海は崩していた体を正し真っ直ぐに俺を見据えた。
「この前、セリに正式にプロポーズしたよ。そんでもって強引に押さえつけてキスした」
「なっ……!!」
予想の少しだけ上をいった告白。
無理やりというニュアンスにカッときて咄嗟に胸ぐらをつかんだ。
プロポーズよりも、こいつが直接宮に触れたことが許せない。どんな場所で、どんな風に? その時宮はどんなカオをしたんだろう。
想像するだけで巡る感情が沸点を超えてしまいそうになる。
もう近づくな! と叫べれば、どんなに楽だろう。でも俺は知ってるから、こいつらを繋ぐ鎖はそんな簡単に切れねーって分かってるから。
いったん深呼吸で冷却して、掴み上げたシャツの襟を解放する。
「この前まで卒業するまでは傍観するとか、俺らの事は応援するだとか何とか言ってなかったっけか?」
睨みつけることで精いっぱい感情を抑えた。
わざと意地の悪い聞き方をして反撃を待ってみるが、天海の変わらない表情に痺れをきらし我慢できずに追撃する。
「宮は俺のものだ」
その一言に、天海はぴくりと眉を動かした。
そしてフッと薄く笑み、抑揚のない声でぽつりと呟く。
「うん……。完全にスイッチ入った」
挑発的とは違う強い意志を孕む眼差し。しまった、ヤバイとこをこじ開けたんだって、本能で悟る。
「僕はずっとさ、セリの自由を守ってあげたくてそばにいたんだよね。『天力者の姫』っていう立場からただ逃げたって仕方ないじゃん?
ぶつかり続けるのも疲れるし、ならその箱庭を少しでも広げてあげようって」
どこか遠い目をして時おり口元を綻ばせ、天海は宮への素直な想いを語り始めた。
天力継承者を生み育てることを義務づけられた宮の人生。ならその時が来るまでとことん甘やかして、色んな経験をさせてあげようと子供ながらに覚悟を決めたと言う。
「だからね、初めての恋愛なら応援してあげたいって思ったのはホント。蒼がイイヤツなのは知ってるし、宮家の事情込みで愛し合えるならこういうのもアリじゃんって思ってた」
でも今……と一端区切りをおいて、残ったビールを流し込む。
「改めて気づいちゃったよ。たとえ蒼でも、セリを『俺のもの』って豪語されるのは面白くない。もう1ミリもあの躰に触れて欲しくないってね」
整った顔で毅然と言い放つ天海を、俺はわずかな恐怖心をもって眺めた。
現に付き合ってる男に向かって、よくもそんな強気な発言ができるもんだと呆れて鼻で笑ってみせる。
遅すぎんだよ、どアホ! 同じ視点から宮を見ていた俺には、お前の気持ちは出逢った頃からだだ漏れだった。
なのに煮え切らない態度が腹立たしくて、同時に脅威で。そういうの全部飲みこみながら2人の間に割って入るのに、俺がどんだけ勇気がいったか分かるか?
やっと手にいれたんた。好きだって言われて、躰も繋がって。あいつの世界に寄り添っていきたいと本気で思ってる。
はいそーですかって、簡単に手離してたまるか!
でも――。
その一方で近頃ひどく感じる心のズレ。想い合う心が行き違い、優先すべきをどこか外している気がする。
宮は俺に甘えない。ワガママを言わない。無理も要求しない。
ちゃんと頼れよ! 天海には素で求めるくせに! って、事あるごとにもどかしく感じるのに、俺に受け止めるだけの器がないのも事実だから苦しい。
そもそも付き合ってから1度だって、あいつの中に天海の影が見えない日なんてなかった。
触れ合うのが自然で寄り添うのが当然で、慕う気持ちは友達とか恋人のそれを当に超えていて――。本人が否定してもむしろ日々濃くなっている事に、俺は嫌でも気付かされる。
きっと今も昔も無意識に、宮の中に天海と別々の道を歩くなんていう選択肢はないんだよ。
だから俺達は行きつく先を想像できずに、あれから一歩も進めないでいるんだ。
「……お前の気持ちは分かった。でも、決めるのは宮だ」
あらゆる感情を押し殺して、ついて出たのはそんな綺麗事。
「うん」
天海は小さく頷いて切なげに笑う。
「ごめん、蒼。セリを本気で奪いにいくね」
…………。
ああ。ついに言いやがった。
コイツに形振り構わず行かれたら、きっと俺なんか一溜りもない。
もうどう転んでも今まで通りじゃ済まされない所まで来たんだって、明確に悟った。
たまらなくなった俺は自分の前髪をグシャリと握り、逃げ場を探すように机に視線を落とす。
並んだ2つのビールジョッキがこれからの俺達と対比して、とても空しいものに映った。
<<前へ 4話へ>>
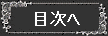
 「ん〜甘っ」
天海はちょっと顔をしかめ、「これは男子向けじゃなないね」なんて、悪びれなく振る舞った。
いや、そうじゃねーだろ。常識的に考えて、それは行き過ぎじゃねーのか?
誰が見ても熱っぽい男女のやりとり。幼なじみの領域を完全に超えてると思うのは、きっと俺だけじゃないはずだ。
カフェテリアは学部という隔たりを排した交流の場として、大勢の学生が行き来している。そんな場所で周囲を証人にして、こいつは俺に一体何を見せたいんだろう。
でもその行為以上に、視界に入った宮のカオが俺の心を更に混沌とさせた。
紅潮した頬も潤んだ瞳も、らしくない。
天海に対してこんな『女』の反応を見せるなんて、俺の前では一度だってなかったのに――。
「ねえ、蒼。久しぶりに軽くいかない? 付き合ってよ」
「ん〜甘っ」
天海はちょっと顔をしかめ、「これは男子向けじゃなないね」なんて、悪びれなく振る舞った。
いや、そうじゃねーだろ。常識的に考えて、それは行き過ぎじゃねーのか?
誰が見ても熱っぽい男女のやりとり。幼なじみの領域を完全に超えてると思うのは、きっと俺だけじゃないはずだ。
カフェテリアは学部という隔たりを排した交流の場として、大勢の学生が行き来している。そんな場所で周囲を証人にして、こいつは俺に一体何を見せたいんだろう。
でもその行為以上に、視界に入った宮のカオが俺の心を更に混沌とさせた。
紅潮した頬も潤んだ瞳も、らしくない。
天海に対してこんな『女』の反応を見せるなんて、俺の前では一度だってなかったのに――。
「ねえ、蒼。久しぶりに軽くいかない? 付き合ってよ」
 目の奥にさっきまでとは違う穏やかな色を浮かべて、天海はジョッキを構える身振りをした。
「あ、セリは先に帰っててね。男飲みだからさ」
「えっ、何で? イヤよ! 私は蒼くんと一緒に……」
動揺を隠してすがるようにこちらに手を伸ばす宮。俺はそれを「ごめん」と柔らかく押し戻し、できる限りで笑う。
「行ってきてもいいか? 夜いつもの時間に電話するから」
宮は別れ間際まで、表情に困惑と不満の色を浮かべていた。
当然だ。日々の時間に追われて彼氏らしいこともできないでいるくせに、天海の誘いはあっさりと受けたりして。
でも今は何を削ってでも天海と向き合うことを優先したかった。
宮に関して常に曖昧な立ち位置をキープしてきたコイツが、俺のとこまで降りてきた気がする。
その機会をみすみす逃せないと思ったんだ。
青波大の裏にある古びた居酒屋に入り、俺達は生ビールだけを注文した。
レトロな古材のテーブルは所々ささくれ立ち、背もたれのない赤い丸イスは体重をかけると左右にガタついている。
2階に雀荘をもつこの店はむしろそっちの出入りがメインなようで、酒を飲む場としてはあまりにも閑散としていた。
『乾杯』と目で合図するに留めて、運ばれてきたジョッキを半分くらい空ける。天海と2人で酒を飲むなんてどれぐらいぶりだろう。
楽しい話じゃないと分かっているのに、懐かしいこの感じが心地よかった。
でもそれはやっぱり、ここまでの話。
店主らしきおばあさんが客に呼ばれて階段を上がると、1階は貸切状態になる。
そこを見計らって、天海は崩していた体を正し真っ直ぐに俺を見据えた。
「この前、セリに正式にプロポーズしたよ。そんでもって強引に押さえつけてキスした」
「なっ……!!」
予想の少しだけ上をいった告白。
無理やりというニュアンスにカッときて咄嗟に胸ぐらをつかんだ。
プロポーズよりも、こいつが直接宮に触れたことが許せない。どんな場所で、どんな風に? その時宮はどんなカオをしたんだろう。
想像するだけで巡る感情が沸点を超えてしまいそうになる。
もう近づくな! と叫べれば、どんなに楽だろう。でも俺は知ってるから、こいつらを繋ぐ鎖はそんな簡単に切れねーって分かってるから。
いったん深呼吸で冷却して、掴み上げたシャツの襟を解放する。
「この前まで卒業するまでは傍観するとか、俺らの事は応援するだとか何とか言ってなかったっけか?」
睨みつけることで精いっぱい感情を抑えた。
わざと意地の悪い聞き方をして反撃を待ってみるが、天海の変わらない表情に痺れをきらし我慢できずに追撃する。
「宮は俺のものだ」
その一言に、天海はぴくりと眉を動かした。
そしてフッと薄く笑み、抑揚のない声でぽつりと呟く。
「うん……。完全にスイッチ入った」
挑発的とは違う強い意志を孕む眼差し。しまった、ヤバイとこをこじ開けたんだって、本能で悟る。
「僕はずっとさ、セリの自由を守ってあげたくてそばにいたんだよね。『天力者の姫』っていう立場からただ逃げたって仕方ないじゃん?
ぶつかり続けるのも疲れるし、ならその箱庭を少しでも広げてあげようって」
どこか遠い目をして時おり口元を綻ばせ、天海は宮への素直な想いを語り始めた。
天力継承者を生み育てることを義務づけられた宮の人生。ならその時が来るまでとことん甘やかして、色んな経験をさせてあげようと子供ながらに覚悟を決めたと言う。
「だからね、初めての恋愛なら応援してあげたいって思ったのはホント。蒼がイイヤツなのは知ってるし、宮家の事情込みで愛し合えるならこういうのもアリじゃんって思ってた」
でも今……と一端区切りをおいて、残ったビールを流し込む。
「改めて気づいちゃったよ。たとえ蒼でも、セリを『俺のもの』って豪語されるのは面白くない。もう1ミリもあの躰に触れて欲しくないってね」
整った顔で毅然と言い放つ天海を、俺はわずかな恐怖心をもって眺めた。
現に付き合ってる男に向かって、よくもそんな強気な発言ができるもんだと呆れて鼻で笑ってみせる。
遅すぎんだよ、どアホ! 同じ視点から宮を見ていた俺には、お前の気持ちは出逢った頃からだだ漏れだった。
なのに煮え切らない態度が腹立たしくて、同時に脅威で。そういうの全部飲みこみながら2人の間に割って入るのに、俺がどんだけ勇気がいったか分かるか?
やっと手にいれたんた。好きだって言われて、躰も繋がって。あいつの世界に寄り添っていきたいと本気で思ってる。
はいそーですかって、簡単に手離してたまるか!
でも――。
その一方で近頃ひどく感じる心のズレ。想い合う心が行き違い、優先すべきをどこか外している気がする。
宮は俺に甘えない。ワガママを言わない。無理も要求しない。
ちゃんと頼れよ! 天海には素で求めるくせに! って、事あるごとにもどかしく感じるのに、俺に受け止めるだけの器がないのも事実だから苦しい。
そもそも付き合ってから1度だって、あいつの中に天海の影が見えない日なんてなかった。
触れ合うのが自然で寄り添うのが当然で、慕う気持ちは友達とか恋人のそれを当に超えていて――。本人が否定してもむしろ日々濃くなっている事に、俺は嫌でも気付かされる。
きっと今も昔も無意識に、宮の中に天海と別々の道を歩くなんていう選択肢はないんだよ。
だから俺達は行きつく先を想像できずに、あれから一歩も進めないでいるんだ。
「……お前の気持ちは分かった。でも、決めるのは宮だ」
あらゆる感情を押し殺して、ついて出たのはそんな綺麗事。
「うん」
天海は小さく頷いて切なげに笑う。
「ごめん、蒼。セリを本気で奪いにいくね」
…………。
ああ。ついに言いやがった。
コイツに形振り構わず行かれたら、きっと俺なんか一溜りもない。
もうどう転んでも今まで通りじゃ済まされない所まで来たんだって、明確に悟った。
たまらなくなった俺は自分の前髪をグシャリと握り、逃げ場を探すように机に視線を落とす。
並んだ2つのビールジョッキがこれからの俺達と対比して、とても空しいものに映った。
目の奥にさっきまでとは違う穏やかな色を浮かべて、天海はジョッキを構える身振りをした。
「あ、セリは先に帰っててね。男飲みだからさ」
「えっ、何で? イヤよ! 私は蒼くんと一緒に……」
動揺を隠してすがるようにこちらに手を伸ばす宮。俺はそれを「ごめん」と柔らかく押し戻し、できる限りで笑う。
「行ってきてもいいか? 夜いつもの時間に電話するから」
宮は別れ間際まで、表情に困惑と不満の色を浮かべていた。
当然だ。日々の時間に追われて彼氏らしいこともできないでいるくせに、天海の誘いはあっさりと受けたりして。
でも今は何を削ってでも天海と向き合うことを優先したかった。
宮に関して常に曖昧な立ち位置をキープしてきたコイツが、俺のとこまで降りてきた気がする。
その機会をみすみす逃せないと思ったんだ。
青波大の裏にある古びた居酒屋に入り、俺達は生ビールだけを注文した。
レトロな古材のテーブルは所々ささくれ立ち、背もたれのない赤い丸イスは体重をかけると左右にガタついている。
2階に雀荘をもつこの店はむしろそっちの出入りがメインなようで、酒を飲む場としてはあまりにも閑散としていた。
『乾杯』と目で合図するに留めて、運ばれてきたジョッキを半分くらい空ける。天海と2人で酒を飲むなんてどれぐらいぶりだろう。
楽しい話じゃないと分かっているのに、懐かしいこの感じが心地よかった。
でもそれはやっぱり、ここまでの話。
店主らしきおばあさんが客に呼ばれて階段を上がると、1階は貸切状態になる。
そこを見計らって、天海は崩していた体を正し真っ直ぐに俺を見据えた。
「この前、セリに正式にプロポーズしたよ。そんでもって強引に押さえつけてキスした」
「なっ……!!」
予想の少しだけ上をいった告白。
無理やりというニュアンスにカッときて咄嗟に胸ぐらをつかんだ。
プロポーズよりも、こいつが直接宮に触れたことが許せない。どんな場所で、どんな風に? その時宮はどんなカオをしたんだろう。
想像するだけで巡る感情が沸点を超えてしまいそうになる。
もう近づくな! と叫べれば、どんなに楽だろう。でも俺は知ってるから、こいつらを繋ぐ鎖はそんな簡単に切れねーって分かってるから。
いったん深呼吸で冷却して、掴み上げたシャツの襟を解放する。
「この前まで卒業するまでは傍観するとか、俺らの事は応援するだとか何とか言ってなかったっけか?」
睨みつけることで精いっぱい感情を抑えた。
わざと意地の悪い聞き方をして反撃を待ってみるが、天海の変わらない表情に痺れをきらし我慢できずに追撃する。
「宮は俺のものだ」
その一言に、天海はぴくりと眉を動かした。
そしてフッと薄く笑み、抑揚のない声でぽつりと呟く。
「うん……。完全にスイッチ入った」
挑発的とは違う強い意志を孕む眼差し。しまった、ヤバイとこをこじ開けたんだって、本能で悟る。
「僕はずっとさ、セリの自由を守ってあげたくてそばにいたんだよね。『天力者の姫』っていう立場からただ逃げたって仕方ないじゃん?
ぶつかり続けるのも疲れるし、ならその箱庭を少しでも広げてあげようって」
どこか遠い目をして時おり口元を綻ばせ、天海は宮への素直な想いを語り始めた。
天力継承者を生み育てることを義務づけられた宮の人生。ならその時が来るまでとことん甘やかして、色んな経験をさせてあげようと子供ながらに覚悟を決めたと言う。
「だからね、初めての恋愛なら応援してあげたいって思ったのはホント。蒼がイイヤツなのは知ってるし、宮家の事情込みで愛し合えるならこういうのもアリじゃんって思ってた」
でも今……と一端区切りをおいて、残ったビールを流し込む。
「改めて気づいちゃったよ。たとえ蒼でも、セリを『俺のもの』って豪語されるのは面白くない。もう1ミリもあの躰に触れて欲しくないってね」
整った顔で毅然と言い放つ天海を、俺はわずかな恐怖心をもって眺めた。
現に付き合ってる男に向かって、よくもそんな強気な発言ができるもんだと呆れて鼻で笑ってみせる。
遅すぎんだよ、どアホ! 同じ視点から宮を見ていた俺には、お前の気持ちは出逢った頃からだだ漏れだった。
なのに煮え切らない態度が腹立たしくて、同時に脅威で。そういうの全部飲みこみながら2人の間に割って入るのに、俺がどんだけ勇気がいったか分かるか?
やっと手にいれたんた。好きだって言われて、躰も繋がって。あいつの世界に寄り添っていきたいと本気で思ってる。
はいそーですかって、簡単に手離してたまるか!
でも――。
その一方で近頃ひどく感じる心のズレ。想い合う心が行き違い、優先すべきをどこか外している気がする。
宮は俺に甘えない。ワガママを言わない。無理も要求しない。
ちゃんと頼れよ! 天海には素で求めるくせに! って、事あるごとにもどかしく感じるのに、俺に受け止めるだけの器がないのも事実だから苦しい。
そもそも付き合ってから1度だって、あいつの中に天海の影が見えない日なんてなかった。
触れ合うのが自然で寄り添うのが当然で、慕う気持ちは友達とか恋人のそれを当に超えていて――。本人が否定してもむしろ日々濃くなっている事に、俺は嫌でも気付かされる。
きっと今も昔も無意識に、宮の中に天海と別々の道を歩くなんていう選択肢はないんだよ。
だから俺達は行きつく先を想像できずに、あれから一歩も進めないでいるんだ。
「……お前の気持ちは分かった。でも、決めるのは宮だ」
あらゆる感情を押し殺して、ついて出たのはそんな綺麗事。
「うん」
天海は小さく頷いて切なげに笑う。
「ごめん、蒼。セリを本気で奪いにいくね」
…………。
ああ。ついに言いやがった。
コイツに形振り構わず行かれたら、きっと俺なんか一溜りもない。
もうどう転んでも今まで通りじゃ済まされない所まで来たんだって、明確に悟った。
たまらなくなった俺は自分の前髪をグシャリと握り、逃げ場を探すように机に視線を落とす。
並んだ2つのビールジョッキがこれからの俺達と対比して、とても空しいものに映った。