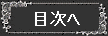◆ 4.くすぐったい束縛
「おはよう。ほら、起きて」
ぬるま湯に足を浸しているような心地良さの中。誰かに髪を撫でられた気がして、一瞬だけまぶたが開いた。
朝なの? やだ……今すごくイイ夢を見てたのに。
少しでも長くこのまどろみに浸かっていたい。
瞼に当たる強い光が恨めしくて寝返りをうつと、今度は頬に羽で撫でられるような感触があった。
優しくてくすぐったい。
夢うつつで口元を緩めると、次にその柔らかさが耳たぶを覆って、私の身体をキュンッと収縮させた。
「んっ……」
「ったく。そんな色っぽい声出されたら、他のコトもしたくなるんだけど」
乱暴な声が耳奥に刺さって、私は一気に現実に吸引される。
突如開けた視界の一番手前に、呆れたようなしーちゃんの顔。
私が目覚めたことに気づくと軽く笑みをのせて、おでこに啄むようなキスをした。
「おはよう、セリ」
「うん……おは……よ……」
 形の良い唇。さっきから頬に触れていた柔らかい羽根の正体はコレだったのかって思う。
眠気眼をこすってぼんやりと天井を眺めると、ベッドの縁に腰かけていたしーちゃんがそのまま腕を伸ばして頭上のカーテンを開けた。
「もう10時まわってるよ。休講? サボり? とりあえずフリーって思っていいわけ?」
高いところから差し込む日差しが、完全に私を覚醒させる。
枕元を手探ってスマホをつかむと、空しくも2時間前にアラームを消した痕跡があった。
「うそぉ〜〜〜〜」
情けなく叫んで、上半身を勢いよく跳ね上げる。
2限の英文の先生は気まぐれに出席をとる事で有名なんだ。今日がその日だとヤマをはっていたのに、そんな朝に限って寝坊しちゃうなんてついてない。
「もうちょっと早く起こして欲しかったよ〜」
呆れ顔の幼なじみにそう身勝手に泣きついて、腰から下を布団にくるまったままどうにか座る。
毛先の引っかかった長い髪を無意識に指でといていると、それを手伝うようにしーちゃんも指を絡めて一房すくった。
「なに? 昨日、夜遊びでもしてたわけ?」
「違うよ、そんなことしてないもん。たまたま見つけたユーチューブの動画にはまっちゃって……」
そこまで普通に会話して、ふと重大な違和感に気づく。
「ちょっとしーちゃんってば、いつの間に私の部屋に来たの??」
倒れたマニキュアの瓶と食べかけのチョコが混在する机。
2人がけのソファーには脱いだカーディガンが裏返っておいてあるし、フローリングには読みかけのファッション誌がそのままになっている。
キレイにしてるとは言い難い自室を予告なく暴かれたのが恥ずかしくて、私は半ば本気で両の拳を振り上げた。
「来る時はラインとか入れてよ〜。せめてノックするとか」
「何で? 今更じゃない。セリだって僕の部屋にアポなしで乱入してくるくせに」
「いいじゃない、しーちゃんは。生活感のないモデルルームみたいなお部屋で、見られて困るものとかも置かない主義なんだから」
「はぁ。そこね」
不満を訴えた私をしーちゃんはどこか白っとした目で見る。
「ったく、危なっかしいなあ」
「何?」
「もっと警戒心もちなよ。寝ている隙に勝手に肌に触れられて、嫌悪感も示さずスルーなんてさ。普通の男だったら調子にのるよ?」
「なっ……!?」
無遠慮に入ってきて寝込みを襲ったくせに、何て勝手な言い草だろうと思う。
私は唇を尖らせてプイッとわざとらしくそっぽを向いた。
「だってしーちゃんじゃない。どこ触られたって、別にどーも思わないもん」
「ふ〜ん。じゃあもっとちゃんと意識してもらわなきゃね」
抑揚のない声でそう言うと、しーちゃんは私の腰に巻きついていた肌掛け布団の端をペロンと捲る。
そして片手で私の体を跨いですり寄り、吐息がかかる距離まで顔を近づけてきたの。
「ほら、目をつむって」
伏し目がちな色っぽい眼差しとチロリと垣間見える赤い舌先が、あの夜の絡みつくようなキスを思い出させる。
「あ……ヤッ……」
また無理やりされるかもしれない。
そう考えたら急に鼓動がうるさくなって、体温が上昇していくのを止められなかった。
「ふふ。顔赤いよ」
しーちゃんは満足げに囁くと私の前髪を人差し指で左右にかきわけて…………そこに容赦なくデコピンしたんだ!?
「いたっ!」
「あはは。何かイチイチ反応が新鮮。ねーそろそろ起きたら? 頬にくっきり枕ジワついててヤバいよ」
「!!??※※?!」
からかわれた!? う……百戦錬磨めぇ〜!
やり場のない怒りと恥ずかしさ、拍子抜けしたやら悔しいやらで。私は指摘を受けたほっぺを手の甲でゴシゴシ擦りながら、上目づかいで睨みつける。
「しーちゃんのそういうとこ、どーかと思う。女の子みんながみんな、しーちゃんのS系のノリを受け入れると思わないでよね」
厭味を込めて吐き捨ててみたのに、しーちゃんは私から奪った枕を胸に抱きながらしれっとした顔を返すの。
「ん、別に。セリにしかしないし」
ちょっとぉ! 私、Mとかじゃないからね!?
思わず叫びかけたんだけどまた絶対からかわれるのが分かって、グッと口を一文字に結んだ。
その様子がよっぽど間抜けだったのか、しーちゃんは珍しく声を出して笑う。
「飽きないわけだよね。20年一緒にいても、まだまだ見た事ないカオがあるんだからさ」
屈託ない笑顔に、私の胸はドキンと跳ねた。
こっちこそ! だよ。もう何なの?
優しかったり意地悪だったり。甘く迫ってくると思ったら、また子供扱いして……。
しーちゃんの想いを知ってしまってから、悔しいことに私は振り回されっぱなしだ。
声とか、表情とか、仕種とか。しーちゃんから奏でられるもの全部に敏感になって、否応なしに心が乱されてしまう。
意識したら何だか少し気恥ずかしくなって、私はラベンダー色のパジャマの襟を軽く整えた。
そしてベッドから脚を下し、今からどうしようかなとぼんやり思う。
すでに2限目も中途半端だし、午後の授業はもともと休講。お天気が良さそうだからどこかに遊びに行きたいけど、誘える相手も思い浮かばない。
手持無沙汰にフローリングに置いてあった雑誌をラックに戻したりしていると、ベッドに浅く座ったままのしーちゃんと目が合った。
「あ、そう言えば何か用事だったんじゃ……」
「ねえ、午後暇になったんでしょ? だったら撮影付き合ってくれない?」
「えぇ? 何のために?」
「う〜ん。理由が必要なら『荷物持ち』ってことで」
「えぇぇ!?」
普段スマホとお財布しか持ち歩かないくせに! って反論すると、「僕の仕事への協力は惜しまない的なこと言ってなかったっけ?」なんてイジワル顔で返される。
「ほら、20分で準備してよ。ついでにセリのお腹も満たしてあげるからさ」
青山のスタジオかと思った撮影現場は、郊外のお洒落なカフェだった。
私もよく読んでる女性ファッション誌とのコラボ企画らしく、人気モデルの女の子としーちゃんがデートしてるとこばかりをカメラが追いかけている。
休日を楽しむ初々しい社会人カップルの設定?
モノレール下で待ち合わせて、レンガ道を手を繋いで歩いて。2人は雑貨屋さんをひと回りした後、黄色い三角屋根のオープンカフェで足を止めるの。
抹茶のフローズンドリンクを嬉しそうにオーダーする彼女。
その同じストローに口をつけてデレるカレシ=しーちゃんの姿を、私は集まったギャラリーに混じって遠巻きに眺めていた。
かれこれ2時間もこんなシーンばかりを見せつけられると、さすがの私にも複雑な感情が生まれる。
何でしーちゃんはわざわざこんな撮影に呼んだのかなぁ。
『モデルのシキ』はしーちゃんのもう1つの生活の場で、天力者とか守り役とかから離れられる唯一の世界。だからずっと私の侵略を拒んでたように思うの。
こんなふうに仕事をしてるとこを見せてくれたことなんてなかったし、こっそり覗きに行って毒づかれた事もあった。
なのに何で今日? 美人さんを見習って女子力をもっと磨けってこと?
モデルの女の子達は雑誌で見るよりずっと細くて、肌なんて真っ白で。女の私でも見惚れちゃうくらいキレイ。
その隣に引け目なく並べるしーちゃんが、今更ながらに眩しい存在に思える。
「ねー、あのYURIちゃんと撮ってる男の子だれ?」
「あれだよ、あれ! カルペスのCMの!」
ランチ帰りに通りがかったぽいOLさん達が、しーちゃんを見つけて興奮気味にギャラリーの輪に加わってきた。
「も〜ヤバイ! 何であんなにカッコいいの〜!? シキさんが神すぎてツラいんですけどっっ!」
前方にいる女子高生グループは熱狂的なファンみたい。
この時間に制服のままそんなに目立っちゃって大丈夫なの? とこちらが心配になっちゃうくらい、黄色い声をあげてはしゃいでいる。
しーちゃんはすごくカッコいいんだ、たぶん。
でもずっとそばにいた私はすっかり遠視気味。遠くのものがよく見えて、すぐ近くは手探らないと分からないの。
貸切のオープンカフェの最前列で、撮影中のしーちゃんはシャッター音が途切れるとファンに向かって軽く会釈した。
でも特別に私に視線を向けることはしない。
当然かもしれないけどそれがやけに悔しくて、自分でも理解できないくらいイライラする。
あ、もしかして、自分の存在を誇示するために私を仕事場に連れてきたんじゃないの?
こんなにモテモテの僕がプロポーズしてあげてるんだから、さっさとOKしろよ〜的な?
しーちゃんがそんなタイプじゃないことくらい百も承知なのに、胸から棘が生え出すようにどこか攻撃的な気持ちになった。
やだ。何よこれ……。
着ていたワンピースの胸元を鷲づかみ、たまらなくなって踵を返す。
手を伸ばしても届かない距離から、しーちゃんを見るのは何かイヤだ。
だから見物人たちを壁にして待っていようと思ったのに、数歩離れただけのところで突然見知らぬ人に通せんぼされた。
「あのっ、アナスイワンピのお嬢さん! 読者モデルやってみませんか?」
黒いパンツスーツに赤いフレーム眼鏡がインパクト大の30代半ばの女性。
業界人? キャッチ? 華やかさもケバさも感じられないけど……。
「いえ、けっこうです」
不審に思ってあからさまに目を背けると、その人は慌てて両手で名刺を差し出す。
「急に声をかけて、びっくりさせてしまいスミマセン! 私、宝船社で『REAL』というファッション誌を担当してます及川と申しますが――」
「え? リアル?」
聞き慣れた単語と、名刺に印刷された見慣れたロゴとを照らし合わせて、驚いて顔を上げた。
「REALのエディターさん……なんですか?」
私の反応を脈ありととったのか、彼女は子供みたいにパーッと表情を明るめると、早口でどんな事をするのか説明してくれる。
「今回は男性ファッション誌の夏祭り企画なんです。浴衣姿を数カット撮らせてもらえると嬉しいんですけどー」
この人はもちろん、私としーちゃんが繋がってることを知らない。
真剣に誘ってくれてるのが申し訳なくて、「ちょっと待って下さい」といったん制する。
「あのREALは、私ちょっと……」
「あぁすいません。今回の依頼はREALじゃないんですよ。大学生向けの兄弟誌で、急きょ女の子をお願いされてまして」
「そう……なんですか?」
少し考えて、それならと思う。
人前に出て目立つようなことは苦手だけど、ちょっと華やかな世界に出ることで自信に繋がるなら嬉しい。
しーちゃんも切っ掛けは読モだった。
あんな風にキラキラ輝けたら『天力者の姫』なんていう肩書がなくても、存在価値を確かめることができるのかなぁ。
「じゃあ私、やってみまグフぅっ……」
悩んだ末の前向きな返事は、突然伸びてきた大きな手に羽交い絞めにされ、口を塞がれる形で言葉尻を潰されてしまった。
形の良い唇。さっきから頬に触れていた柔らかい羽根の正体はコレだったのかって思う。
眠気眼をこすってぼんやりと天井を眺めると、ベッドの縁に腰かけていたしーちゃんがそのまま腕を伸ばして頭上のカーテンを開けた。
「もう10時まわってるよ。休講? サボり? とりあえずフリーって思っていいわけ?」
高いところから差し込む日差しが、完全に私を覚醒させる。
枕元を手探ってスマホをつかむと、空しくも2時間前にアラームを消した痕跡があった。
「うそぉ〜〜〜〜」
情けなく叫んで、上半身を勢いよく跳ね上げる。
2限の英文の先生は気まぐれに出席をとる事で有名なんだ。今日がその日だとヤマをはっていたのに、そんな朝に限って寝坊しちゃうなんてついてない。
「もうちょっと早く起こして欲しかったよ〜」
呆れ顔の幼なじみにそう身勝手に泣きついて、腰から下を布団にくるまったままどうにか座る。
毛先の引っかかった長い髪を無意識に指でといていると、それを手伝うようにしーちゃんも指を絡めて一房すくった。
「なに? 昨日、夜遊びでもしてたわけ?」
「違うよ、そんなことしてないもん。たまたま見つけたユーチューブの動画にはまっちゃって……」
そこまで普通に会話して、ふと重大な違和感に気づく。
「ちょっとしーちゃんってば、いつの間に私の部屋に来たの??」
倒れたマニキュアの瓶と食べかけのチョコが混在する机。
2人がけのソファーには脱いだカーディガンが裏返っておいてあるし、フローリングには読みかけのファッション誌がそのままになっている。
キレイにしてるとは言い難い自室を予告なく暴かれたのが恥ずかしくて、私は半ば本気で両の拳を振り上げた。
「来る時はラインとか入れてよ〜。せめてノックするとか」
「何で? 今更じゃない。セリだって僕の部屋にアポなしで乱入してくるくせに」
「いいじゃない、しーちゃんは。生活感のないモデルルームみたいなお部屋で、見られて困るものとかも置かない主義なんだから」
「はぁ。そこね」
不満を訴えた私をしーちゃんはどこか白っとした目で見る。
「ったく、危なっかしいなあ」
「何?」
「もっと警戒心もちなよ。寝ている隙に勝手に肌に触れられて、嫌悪感も示さずスルーなんてさ。普通の男だったら調子にのるよ?」
「なっ……!?」
無遠慮に入ってきて寝込みを襲ったくせに、何て勝手な言い草だろうと思う。
私は唇を尖らせてプイッとわざとらしくそっぽを向いた。
「だってしーちゃんじゃない。どこ触られたって、別にどーも思わないもん」
「ふ〜ん。じゃあもっとちゃんと意識してもらわなきゃね」
抑揚のない声でそう言うと、しーちゃんは私の腰に巻きついていた肌掛け布団の端をペロンと捲る。
そして片手で私の体を跨いですり寄り、吐息がかかる距離まで顔を近づけてきたの。
「ほら、目をつむって」
伏し目がちな色っぽい眼差しとチロリと垣間見える赤い舌先が、あの夜の絡みつくようなキスを思い出させる。
「あ……ヤッ……」
また無理やりされるかもしれない。
そう考えたら急に鼓動がうるさくなって、体温が上昇していくのを止められなかった。
「ふふ。顔赤いよ」
しーちゃんは満足げに囁くと私の前髪を人差し指で左右にかきわけて…………そこに容赦なくデコピンしたんだ!?
「いたっ!」
「あはは。何かイチイチ反応が新鮮。ねーそろそろ起きたら? 頬にくっきり枕ジワついててヤバいよ」
「!!??※※?!」
からかわれた!? う……百戦錬磨めぇ〜!
やり場のない怒りと恥ずかしさ、拍子抜けしたやら悔しいやらで。私は指摘を受けたほっぺを手の甲でゴシゴシ擦りながら、上目づかいで睨みつける。
「しーちゃんのそういうとこ、どーかと思う。女の子みんながみんな、しーちゃんのS系のノリを受け入れると思わないでよね」
厭味を込めて吐き捨ててみたのに、しーちゃんは私から奪った枕を胸に抱きながらしれっとした顔を返すの。
「ん、別に。セリにしかしないし」
ちょっとぉ! 私、Mとかじゃないからね!?
思わず叫びかけたんだけどまた絶対からかわれるのが分かって、グッと口を一文字に結んだ。
その様子がよっぽど間抜けだったのか、しーちゃんは珍しく声を出して笑う。
「飽きないわけだよね。20年一緒にいても、まだまだ見た事ないカオがあるんだからさ」
屈託ない笑顔に、私の胸はドキンと跳ねた。
こっちこそ! だよ。もう何なの?
優しかったり意地悪だったり。甘く迫ってくると思ったら、また子供扱いして……。
しーちゃんの想いを知ってしまってから、悔しいことに私は振り回されっぱなしだ。
声とか、表情とか、仕種とか。しーちゃんから奏でられるもの全部に敏感になって、否応なしに心が乱されてしまう。
意識したら何だか少し気恥ずかしくなって、私はラベンダー色のパジャマの襟を軽く整えた。
そしてベッドから脚を下し、今からどうしようかなとぼんやり思う。
すでに2限目も中途半端だし、午後の授業はもともと休講。お天気が良さそうだからどこかに遊びに行きたいけど、誘える相手も思い浮かばない。
手持無沙汰にフローリングに置いてあった雑誌をラックに戻したりしていると、ベッドに浅く座ったままのしーちゃんと目が合った。
「あ、そう言えば何か用事だったんじゃ……」
「ねえ、午後暇になったんでしょ? だったら撮影付き合ってくれない?」
「えぇ? 何のために?」
「う〜ん。理由が必要なら『荷物持ち』ってことで」
「えぇぇ!?」
普段スマホとお財布しか持ち歩かないくせに! って反論すると、「僕の仕事への協力は惜しまない的なこと言ってなかったっけ?」なんてイジワル顔で返される。
「ほら、20分で準備してよ。ついでにセリのお腹も満たしてあげるからさ」
青山のスタジオかと思った撮影現場は、郊外のお洒落なカフェだった。
私もよく読んでる女性ファッション誌とのコラボ企画らしく、人気モデルの女の子としーちゃんがデートしてるとこばかりをカメラが追いかけている。
休日を楽しむ初々しい社会人カップルの設定?
モノレール下で待ち合わせて、レンガ道を手を繋いで歩いて。2人は雑貨屋さんをひと回りした後、黄色い三角屋根のオープンカフェで足を止めるの。
抹茶のフローズンドリンクを嬉しそうにオーダーする彼女。
その同じストローに口をつけてデレるカレシ=しーちゃんの姿を、私は集まったギャラリーに混じって遠巻きに眺めていた。
かれこれ2時間もこんなシーンばかりを見せつけられると、さすがの私にも複雑な感情が生まれる。
何でしーちゃんはわざわざこんな撮影に呼んだのかなぁ。
『モデルのシキ』はしーちゃんのもう1つの生活の場で、天力者とか守り役とかから離れられる唯一の世界。だからずっと私の侵略を拒んでたように思うの。
こんなふうに仕事をしてるとこを見せてくれたことなんてなかったし、こっそり覗きに行って毒づかれた事もあった。
なのに何で今日? 美人さんを見習って女子力をもっと磨けってこと?
モデルの女の子達は雑誌で見るよりずっと細くて、肌なんて真っ白で。女の私でも見惚れちゃうくらいキレイ。
その隣に引け目なく並べるしーちゃんが、今更ながらに眩しい存在に思える。
「ねー、あのYURIちゃんと撮ってる男の子だれ?」
「あれだよ、あれ! カルペスのCMの!」
ランチ帰りに通りがかったぽいOLさん達が、しーちゃんを見つけて興奮気味にギャラリーの輪に加わってきた。
「も〜ヤバイ! 何であんなにカッコいいの〜!? シキさんが神すぎてツラいんですけどっっ!」
前方にいる女子高生グループは熱狂的なファンみたい。
この時間に制服のままそんなに目立っちゃって大丈夫なの? とこちらが心配になっちゃうくらい、黄色い声をあげてはしゃいでいる。
しーちゃんはすごくカッコいいんだ、たぶん。
でもずっとそばにいた私はすっかり遠視気味。遠くのものがよく見えて、すぐ近くは手探らないと分からないの。
貸切のオープンカフェの最前列で、撮影中のしーちゃんはシャッター音が途切れるとファンに向かって軽く会釈した。
でも特別に私に視線を向けることはしない。
当然かもしれないけどそれがやけに悔しくて、自分でも理解できないくらいイライラする。
あ、もしかして、自分の存在を誇示するために私を仕事場に連れてきたんじゃないの?
こんなにモテモテの僕がプロポーズしてあげてるんだから、さっさとOKしろよ〜的な?
しーちゃんがそんなタイプじゃないことくらい百も承知なのに、胸から棘が生え出すようにどこか攻撃的な気持ちになった。
やだ。何よこれ……。
着ていたワンピースの胸元を鷲づかみ、たまらなくなって踵を返す。
手を伸ばしても届かない距離から、しーちゃんを見るのは何かイヤだ。
だから見物人たちを壁にして待っていようと思ったのに、数歩離れただけのところで突然見知らぬ人に通せんぼされた。
「あのっ、アナスイワンピのお嬢さん! 読者モデルやってみませんか?」
黒いパンツスーツに赤いフレーム眼鏡がインパクト大の30代半ばの女性。
業界人? キャッチ? 華やかさもケバさも感じられないけど……。
「いえ、けっこうです」
不審に思ってあからさまに目を背けると、その人は慌てて両手で名刺を差し出す。
「急に声をかけて、びっくりさせてしまいスミマセン! 私、宝船社で『REAL』というファッション誌を担当してます及川と申しますが――」
「え? リアル?」
聞き慣れた単語と、名刺に印刷された見慣れたロゴとを照らし合わせて、驚いて顔を上げた。
「REALのエディターさん……なんですか?」
私の反応を脈ありととったのか、彼女は子供みたいにパーッと表情を明るめると、早口でどんな事をするのか説明してくれる。
「今回は男性ファッション誌の夏祭り企画なんです。浴衣姿を数カット撮らせてもらえると嬉しいんですけどー」
この人はもちろん、私としーちゃんが繋がってることを知らない。
真剣に誘ってくれてるのが申し訳なくて、「ちょっと待って下さい」といったん制する。
「あのREALは、私ちょっと……」
「あぁすいません。今回の依頼はREALじゃないんですよ。大学生向けの兄弟誌で、急きょ女の子をお願いされてまして」
「そう……なんですか?」
少し考えて、それならと思う。
人前に出て目立つようなことは苦手だけど、ちょっと華やかな世界に出ることで自信に繋がるなら嬉しい。
しーちゃんも切っ掛けは読モだった。
あんな風にキラキラ輝けたら『天力者の姫』なんていう肩書がなくても、存在価値を確かめることができるのかなぁ。
「じゃあ私、やってみまグフぅっ……」
悩んだ末の前向きな返事は、突然伸びてきた大きな手に羽交い絞めにされ、口を塞がれる形で言葉尻を潰されてしまった。
 「いや、ゴメンネ。それ却下で」
しーちゃんが私の自由を奪ったまま、代わりに彼女に頭を下げる。
どこから現れたの? 撮影は終わったの? こんなとこに出てきちゃって大丈夫なの!?
思いがけない人気モデルの登場。動揺したのは私だけじゃなかったらしく、エディターさんもぽかんと口を開いて表情に困惑の色を見せる。
「はわわゎゎ……シキ君? 何でですか?」
「だってそれ今朝言ってたやつでしょ? ヤダよ、無理。おまけで水着撮影あるじゃん」
「あぁぁぁちょっと! それを先に言っちゃ〜! おいおい説明してくとこだったんですから。ほらぁこちらのお嬢さんの柔らかそうな体のラインを見て下さい。
絶対に読者受けすると思うんです!」
「うん、だからこの子だけはダメね。露出の多い格好なんかでメンズ誌に載って、読者様に妙な想像でもされたら困るからさ」
力なく項垂れる彼女にピシャリとそう言い放って、しーちゃんは私の体をクルリと自分に向けて回転させた。
「読モがダメとは言わないけどさ。セリもちゃんと話を聞いてから返事しなよね」
有無を言わさず手の中の名刺を抜き取られ、私は反抗して唇を尖らせる。
「別に、水着だっていいのに……」
「はあ? あんなカッコやこんなカッコとか要求されるよ。セリは調子に乗って何でもやっちゃうでしょ? 僕にも見せた事ないとこ他のヤツらに見せてどーすんのさ」
「ちょっ……! 誤解を招くような言い方しないでよぉ」
身勝手な理由に、不必要な束縛。
普段なら反発してそうな場面なのに、今日の私は不思議とイヤじゃないから困るの。
やだ。顔が熱い…………。
「撮影一段落したんだ。2階で休憩とってイイって言うからさ、セリも一緒においで」
しーちゃんはそう言うと私の手首を掴んで、カフェ店内へと歩き出した。
「ほら、樹さんも」
「あ、はいっ」
同行を促された彼女は状況が飲みこめず、オロオロしながら追いかけてくる。
私の手を引いたまま見物人の脇を堂々と通り抜けるしーちゃん。樹さんは周囲をチラチラと気にしながら、口元に手を添えて小声で尋ねる。
「あの〜。シキ君とこちらのお嬢さんの関係って……」
しーちゃんは「う〜ん」と困ったように唸ってから、彼女ではなく私に振り返る。
「ねー、何て説明すればいい?」
う……真顔で分かってる事を聞かないでよ。つい言葉に躓いちゃうじゃない。
「幼なじみ……です」
「ふふ、だって樹さん。まー明日は違うかもしれないんだけどね」
「しーちゃん!?」
意味深な台詞を吐くしーちゃんに、どう返していいものか困ってわざとそっぽを向いた。
「はいはい。ふくれないでねー」
しーちゃんは尽かさず私のほっぺたを摘まんで顔の向きを戻させると、ニヤリと唇の端を上げる。
だからそういうのヤメてってば……。意志とは裏腹に赤面しちゃうじゃない。
「仲良しなんですね」
樹さんは私達に視線を向けて、きょとんと眼を丸くした。
「もう6年のお付き合いになりますけど、初めて見ましたよ。シキ君ってばあなたの事はいつもこんな風に見つめるんですか? カメラの前でもそのカオしてくれたら最強なのに」
白い板壁に囲まれ、ダークブラウンにペイントされた木のテーブルセットが並ぶシャビーな雰囲気の店内。
渋くてお洒落な空間はメンズファッション誌で取り上げるにぴったりなカフェだなと思う。
ふわりと香るコーヒー豆の芳ばしさと、焼き菓子の甘いバターの匂い。
絶妙なハーモニーを鼻で楽しみながら、私はしーちゃんに続いて右奥にある階段を上った。
「お疲れさまです」
居心地の良さそうなソファーがコの字型に置かれた2階のティールームでは、7、8人の関係者が和気あいあいと談笑していた。
撮影カメラマンさんとアシスタントさん。そしてたぶん編集者の人たち。
細くしなやかな手を振っている女の子達はもう素材がぜんぜん違うから、モデルさんなんだって一目で分かる。
「シキ、お疲れ!」
「遅いよ〜。アイスコーヒーで良かったよね?」
しーちゃんが輪に加わるとみんなが柔らかい表情で迎え入れるのを見て、ここでもしーちゃんは特別な存在なんだって感じた。
触れ合う人を片っ端からトリコにして、どこにいっても居場所を確保できる才能。
誇らしくも妬ましくもあって、私は入口手前で立ち止まった。
「セリ、おいで」
しーちゃんが振り向いて、ここに座れと手招きする。
それを合図に室内にいた全員が一斉にこちらに注目したから、私は焦って会釈をした。
「初めまして……お邪魔します」
「え? なになに? シキのこれ?」
年長者の男性が小指をたててニヤニヤと笑う。
「あ〜、だからブルーベリーミルクフローズンなのね。おかしいと思ったわ、シキ君がこんな激甘オーダーするなんて」
撮影の小道具らしき雑貨を数えていた女性は、振り返って甲高い声をあげた。
周囲の大人たちに私との事をからかわれたしーちゃんは、反論することなくただ困ったように苦笑った。
「はいはい、もういいでしょ」
テレ隠しにぶっきらぼうに返答し、子供っぽく口を一文字に結ぶ姿なんて珍しい。
レアなものが見れたなあって、私はちょっと愉快な気持ちでソファーに座る。
「はい。これセリのね」
「……ありがと」
甘酸っぱいブルーベリーとシャリシャリした氷の触感を楽しんでいると、少ししてカフェの店員さんがやって来た。
テーブルの中央にカラフルな焼き菓子を並べて「当店からのサービスです」なんて嬉しいことを言ってくれる。
イチゴやオレンジのマドレーヌ。チョコや抹茶のフィナンシェ。ピスタチオやカシスのマカロンなんて、まるで宝石みたいにキレイ。
「わ〜おいしそう♥」
心の歓声が思わず口に出て、私は慌てて両手で覆う。
だって誰も手を伸ばしたりしてないんだもの。甘いものが好きじゃないのか、飛びついたりしないのがマナーなのか……。
とにかく、目の前にこんなに心躍る魅力的なスイーツが広がっているのに、周囲の人達はびっくりするくらい無関心なの。
う……食べたいなぁ。
でもさすがに部外者の私が現場の差し入れに手をつけるわけにはいかないよね。
「何てカオしてるわけ?」
そんな私の葛藤に気付いたしーちゃんは、隣でクスクスと可笑しそうに笑った。
「頂きなよ。大好物じゃん」
「でも、誰も食べてないのに……」
「大丈夫。どうせこういうのいつも余っちゃうんだよね。だからほら、セリに食べてもらわないと困るって」
しーちゃんにそう言われて恐る恐る周囲を見渡すと、樹さんが「どうぞどうぞ〜」と取り皿とヒメフォークを手渡してくれた。
それはまるで免罪符。
丁寧にお礼を言って身を乗り出し、私はますますテンションを上げる。
「ね〜しーちゃん、このマカロンころころしててすっごく可愛いね! 全種類食べたくなっちゃうけどちょっと我慢して、コレとコレだけ頂こうかな。
あ〜〜でもやっぱり、こっちとそっちも食べていい?」
一応、許可を得てからと思って振り返ったのに、しーちゃんは何がツボだったのかお腹を抱えて笑ってるの。
「う……食いしん坊とかって言いたいんでしょ?」
欲しいものはしっかりお皿にとって、私は拗ねながら自分の席に戻る。
しーちゃんは私の頬にかかった髪を指先ではじきながら、ただ優しい目を返した。
「今日は連れてきたかいがあったよ。ほらこの前は、蒼に先を越されちゃって悔しかったからさ」
私の頭をクシャリと撫でたしーちゃんは、その後スタッフさんに呼ばれて颯爽と階段を降りて行く。
この前って、カフェテリアでの新作ケーキのこと? もお、何よ。ワンコの餌付けじゃないんだから!
遠ざかる背中に向かって心で毒づいてみたものの、裏腹に顔が上気していくのを止められない。
しーちゃんに見つめられていつもと同じように触れられただけなのに、こんなにもドキドキしちゃうなんていったい私ってばどうしたんだろう。
違う、私じゃない。しーちゃんがおかしいの。何か甘すぎるの!
気にしないフリをしていた『縁側でのキス』が急にフラッシュバックして、恥ずかしさで1人悶えそうになる。
『覚悟』なんてできない。このままじゃ心臓がもたないよ。
しーちゃんの本気に飲みこまれそうになる感情を振り切りたくて、私はお皿に残っていたマカロンをつまむと丸ごと口の中に放り投げた。
「よくそんなに食べられるわね」
驚きと呆れを含んだ物言いで、そう声をかけてきた女の子がいた。
170センチは超えてるだろう長身に、サラサラのロングヘアー。シンプルなスキニ―パンツにタンクトップを重ね着しただけのファッションだけど、
そこから伸びた細長い手足がまるでアクセサリーみたいでお洒落に映る。
私より少しだけ年上かな? 涼しげな目元がアジアンビューティーと呼ぶのにぴったりだって思った。
「あの……」
「あ、いきなりゴメンね。気持ちイイくらいの食べっぷりだから、体重とかスタイルとか気になんないもんかなと、ふと疑問で」
突然のことに思わず体を強張らせた私を気遣ってから、彼女はサバサバした笑顔を見せる。
言葉に微妙な棘があるような気もするけど、嫌味というわけでもないみたい。
キレイな髪から香る爽やかなグリーンアップル。これがこの女の人のイメージだと思うと悪い印象はなくて、私は多少戸惑いながらも口角を上げる。
「体重はもちろん気にはなりますよ。でもそれ以上に甘いものに目がなくて」
「へ〜ある意味勇気あるね。アタシも甘いもの大好きだけど、やっぱすごく気を付けてるから」
「そうですよね。モデルさんは大変ですもんね」
「あぁ、アタシはモデルじゃないよ。ただシキって男のくせに驚くくらい整ってるじゃない? 横に並びたいんだったら、それなりの努力はしとかないとね」
「へ?」
急にしーちゃんの名前を出されて、思わず目を丸く見開いてしまった。
そんな私にクスリと小さな笑いを零し、彼女は去り際に軽く肩を叩いて囁いたの。
「あなた、まだ彼女とかじゃないんでしょ? アタシ明日、告白予定なので邪魔しないでね」
そこまで言われて、鈍い私はやっとハッとする。
この美人は一体だあれ?? って。
「いや、ゴメンネ。それ却下で」
しーちゃんが私の自由を奪ったまま、代わりに彼女に頭を下げる。
どこから現れたの? 撮影は終わったの? こんなとこに出てきちゃって大丈夫なの!?
思いがけない人気モデルの登場。動揺したのは私だけじゃなかったらしく、エディターさんもぽかんと口を開いて表情に困惑の色を見せる。
「はわわゎゎ……シキ君? 何でですか?」
「だってそれ今朝言ってたやつでしょ? ヤダよ、無理。おまけで水着撮影あるじゃん」
「あぁぁぁちょっと! それを先に言っちゃ〜! おいおい説明してくとこだったんですから。ほらぁこちらのお嬢さんの柔らかそうな体のラインを見て下さい。
絶対に読者受けすると思うんです!」
「うん、だからこの子だけはダメね。露出の多い格好なんかでメンズ誌に載って、読者様に妙な想像でもされたら困るからさ」
力なく項垂れる彼女にピシャリとそう言い放って、しーちゃんは私の体をクルリと自分に向けて回転させた。
「読モがダメとは言わないけどさ。セリもちゃんと話を聞いてから返事しなよね」
有無を言わさず手の中の名刺を抜き取られ、私は反抗して唇を尖らせる。
「別に、水着だっていいのに……」
「はあ? あんなカッコやこんなカッコとか要求されるよ。セリは調子に乗って何でもやっちゃうでしょ? 僕にも見せた事ないとこ他のヤツらに見せてどーすんのさ」
「ちょっ……! 誤解を招くような言い方しないでよぉ」
身勝手な理由に、不必要な束縛。
普段なら反発してそうな場面なのに、今日の私は不思議とイヤじゃないから困るの。
やだ。顔が熱い…………。
「撮影一段落したんだ。2階で休憩とってイイって言うからさ、セリも一緒においで」
しーちゃんはそう言うと私の手首を掴んで、カフェ店内へと歩き出した。
「ほら、樹さんも」
「あ、はいっ」
同行を促された彼女は状況が飲みこめず、オロオロしながら追いかけてくる。
私の手を引いたまま見物人の脇を堂々と通り抜けるしーちゃん。樹さんは周囲をチラチラと気にしながら、口元に手を添えて小声で尋ねる。
「あの〜。シキ君とこちらのお嬢さんの関係って……」
しーちゃんは「う〜ん」と困ったように唸ってから、彼女ではなく私に振り返る。
「ねー、何て説明すればいい?」
う……真顔で分かってる事を聞かないでよ。つい言葉に躓いちゃうじゃない。
「幼なじみ……です」
「ふふ、だって樹さん。まー明日は違うかもしれないんだけどね」
「しーちゃん!?」
意味深な台詞を吐くしーちゃんに、どう返していいものか困ってわざとそっぽを向いた。
「はいはい。ふくれないでねー」
しーちゃんは尽かさず私のほっぺたを摘まんで顔の向きを戻させると、ニヤリと唇の端を上げる。
だからそういうのヤメてってば……。意志とは裏腹に赤面しちゃうじゃない。
「仲良しなんですね」
樹さんは私達に視線を向けて、きょとんと眼を丸くした。
「もう6年のお付き合いになりますけど、初めて見ましたよ。シキ君ってばあなたの事はいつもこんな風に見つめるんですか? カメラの前でもそのカオしてくれたら最強なのに」
白い板壁に囲まれ、ダークブラウンにペイントされた木のテーブルセットが並ぶシャビーな雰囲気の店内。
渋くてお洒落な空間はメンズファッション誌で取り上げるにぴったりなカフェだなと思う。
ふわりと香るコーヒー豆の芳ばしさと、焼き菓子の甘いバターの匂い。
絶妙なハーモニーを鼻で楽しみながら、私はしーちゃんに続いて右奥にある階段を上った。
「お疲れさまです」
居心地の良さそうなソファーがコの字型に置かれた2階のティールームでは、7、8人の関係者が和気あいあいと談笑していた。
撮影カメラマンさんとアシスタントさん。そしてたぶん編集者の人たち。
細くしなやかな手を振っている女の子達はもう素材がぜんぜん違うから、モデルさんなんだって一目で分かる。
「シキ、お疲れ!」
「遅いよ〜。アイスコーヒーで良かったよね?」
しーちゃんが輪に加わるとみんなが柔らかい表情で迎え入れるのを見て、ここでもしーちゃんは特別な存在なんだって感じた。
触れ合う人を片っ端からトリコにして、どこにいっても居場所を確保できる才能。
誇らしくも妬ましくもあって、私は入口手前で立ち止まった。
「セリ、おいで」
しーちゃんが振り向いて、ここに座れと手招きする。
それを合図に室内にいた全員が一斉にこちらに注目したから、私は焦って会釈をした。
「初めまして……お邪魔します」
「え? なになに? シキのこれ?」
年長者の男性が小指をたててニヤニヤと笑う。
「あ〜、だからブルーベリーミルクフローズンなのね。おかしいと思ったわ、シキ君がこんな激甘オーダーするなんて」
撮影の小道具らしき雑貨を数えていた女性は、振り返って甲高い声をあげた。
周囲の大人たちに私との事をからかわれたしーちゃんは、反論することなくただ困ったように苦笑った。
「はいはい、もういいでしょ」
テレ隠しにぶっきらぼうに返答し、子供っぽく口を一文字に結ぶ姿なんて珍しい。
レアなものが見れたなあって、私はちょっと愉快な気持ちでソファーに座る。
「はい。これセリのね」
「……ありがと」
甘酸っぱいブルーベリーとシャリシャリした氷の触感を楽しんでいると、少ししてカフェの店員さんがやって来た。
テーブルの中央にカラフルな焼き菓子を並べて「当店からのサービスです」なんて嬉しいことを言ってくれる。
イチゴやオレンジのマドレーヌ。チョコや抹茶のフィナンシェ。ピスタチオやカシスのマカロンなんて、まるで宝石みたいにキレイ。
「わ〜おいしそう♥」
心の歓声が思わず口に出て、私は慌てて両手で覆う。
だって誰も手を伸ばしたりしてないんだもの。甘いものが好きじゃないのか、飛びついたりしないのがマナーなのか……。
とにかく、目の前にこんなに心躍る魅力的なスイーツが広がっているのに、周囲の人達はびっくりするくらい無関心なの。
う……食べたいなぁ。
でもさすがに部外者の私が現場の差し入れに手をつけるわけにはいかないよね。
「何てカオしてるわけ?」
そんな私の葛藤に気付いたしーちゃんは、隣でクスクスと可笑しそうに笑った。
「頂きなよ。大好物じゃん」
「でも、誰も食べてないのに……」
「大丈夫。どうせこういうのいつも余っちゃうんだよね。だからほら、セリに食べてもらわないと困るって」
しーちゃんにそう言われて恐る恐る周囲を見渡すと、樹さんが「どうぞどうぞ〜」と取り皿とヒメフォークを手渡してくれた。
それはまるで免罪符。
丁寧にお礼を言って身を乗り出し、私はますますテンションを上げる。
「ね〜しーちゃん、このマカロンころころしててすっごく可愛いね! 全種類食べたくなっちゃうけどちょっと我慢して、コレとコレだけ頂こうかな。
あ〜〜でもやっぱり、こっちとそっちも食べていい?」
一応、許可を得てからと思って振り返ったのに、しーちゃんは何がツボだったのかお腹を抱えて笑ってるの。
「う……食いしん坊とかって言いたいんでしょ?」
欲しいものはしっかりお皿にとって、私は拗ねながら自分の席に戻る。
しーちゃんは私の頬にかかった髪を指先ではじきながら、ただ優しい目を返した。
「今日は連れてきたかいがあったよ。ほらこの前は、蒼に先を越されちゃって悔しかったからさ」
私の頭をクシャリと撫でたしーちゃんは、その後スタッフさんに呼ばれて颯爽と階段を降りて行く。
この前って、カフェテリアでの新作ケーキのこと? もお、何よ。ワンコの餌付けじゃないんだから!
遠ざかる背中に向かって心で毒づいてみたものの、裏腹に顔が上気していくのを止められない。
しーちゃんに見つめられていつもと同じように触れられただけなのに、こんなにもドキドキしちゃうなんていったい私ってばどうしたんだろう。
違う、私じゃない。しーちゃんがおかしいの。何か甘すぎるの!
気にしないフリをしていた『縁側でのキス』が急にフラッシュバックして、恥ずかしさで1人悶えそうになる。
『覚悟』なんてできない。このままじゃ心臓がもたないよ。
しーちゃんの本気に飲みこまれそうになる感情を振り切りたくて、私はお皿に残っていたマカロンをつまむと丸ごと口の中に放り投げた。
「よくそんなに食べられるわね」
驚きと呆れを含んだ物言いで、そう声をかけてきた女の子がいた。
170センチは超えてるだろう長身に、サラサラのロングヘアー。シンプルなスキニ―パンツにタンクトップを重ね着しただけのファッションだけど、
そこから伸びた細長い手足がまるでアクセサリーみたいでお洒落に映る。
私より少しだけ年上かな? 涼しげな目元がアジアンビューティーと呼ぶのにぴったりだって思った。
「あの……」
「あ、いきなりゴメンね。気持ちイイくらいの食べっぷりだから、体重とかスタイルとか気になんないもんかなと、ふと疑問で」
突然のことに思わず体を強張らせた私を気遣ってから、彼女はサバサバした笑顔を見せる。
言葉に微妙な棘があるような気もするけど、嫌味というわけでもないみたい。
キレイな髪から香る爽やかなグリーンアップル。これがこの女の人のイメージだと思うと悪い印象はなくて、私は多少戸惑いながらも口角を上げる。
「体重はもちろん気にはなりますよ。でもそれ以上に甘いものに目がなくて」
「へ〜ある意味勇気あるね。アタシも甘いもの大好きだけど、やっぱすごく気を付けてるから」
「そうですよね。モデルさんは大変ですもんね」
「あぁ、アタシはモデルじゃないよ。ただシキって男のくせに驚くくらい整ってるじゃない? 横に並びたいんだったら、それなりの努力はしとかないとね」
「へ?」
急にしーちゃんの名前を出されて、思わず目を丸く見開いてしまった。
そんな私にクスリと小さな笑いを零し、彼女は去り際に軽く肩を叩いて囁いたの。
「あなた、まだ彼女とかじゃないんでしょ? アタシ明日、告白予定なので邪魔しないでね」
そこまで言われて、鈍い私はやっとハッとする。
この美人は一体だあれ?? って。
<<前へ 5話へ>>
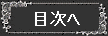
 形の良い唇。さっきから頬に触れていた柔らかい羽根の正体はコレだったのかって思う。
眠気眼をこすってぼんやりと天井を眺めると、ベッドの縁に腰かけていたしーちゃんがそのまま腕を伸ばして頭上のカーテンを開けた。
「もう10時まわってるよ。休講? サボり? とりあえずフリーって思っていいわけ?」
高いところから差し込む日差しが、完全に私を覚醒させる。
枕元を手探ってスマホをつかむと、空しくも2時間前にアラームを消した痕跡があった。
「うそぉ〜〜〜〜」
情けなく叫んで、上半身を勢いよく跳ね上げる。
2限の英文の先生は気まぐれに出席をとる事で有名なんだ。今日がその日だとヤマをはっていたのに、そんな朝に限って寝坊しちゃうなんてついてない。
「もうちょっと早く起こして欲しかったよ〜」
呆れ顔の幼なじみにそう身勝手に泣きついて、腰から下を布団にくるまったままどうにか座る。
毛先の引っかかった長い髪を無意識に指でといていると、それを手伝うようにしーちゃんも指を絡めて一房すくった。
「なに? 昨日、夜遊びでもしてたわけ?」
「違うよ、そんなことしてないもん。たまたま見つけたユーチューブの動画にはまっちゃって……」
そこまで普通に会話して、ふと重大な違和感に気づく。
「ちょっとしーちゃんってば、いつの間に私の部屋に来たの??」
倒れたマニキュアの瓶と食べかけのチョコが混在する机。
2人がけのソファーには脱いだカーディガンが裏返っておいてあるし、フローリングには読みかけのファッション誌がそのままになっている。
キレイにしてるとは言い難い自室を予告なく暴かれたのが恥ずかしくて、私は半ば本気で両の拳を振り上げた。
「来る時はラインとか入れてよ〜。せめてノックするとか」
「何で? 今更じゃない。セリだって僕の部屋にアポなしで乱入してくるくせに」
「いいじゃない、しーちゃんは。生活感のないモデルルームみたいなお部屋で、見られて困るものとかも置かない主義なんだから」
「はぁ。そこね」
不満を訴えた私をしーちゃんはどこか白っとした目で見る。
「ったく、危なっかしいなあ」
「何?」
「もっと警戒心もちなよ。寝ている隙に勝手に肌に触れられて、嫌悪感も示さずスルーなんてさ。普通の男だったら調子にのるよ?」
「なっ……!?」
無遠慮に入ってきて寝込みを襲ったくせに、何て勝手な言い草だろうと思う。
私は唇を尖らせてプイッとわざとらしくそっぽを向いた。
「だってしーちゃんじゃない。どこ触られたって、別にどーも思わないもん」
「ふ〜ん。じゃあもっとちゃんと意識してもらわなきゃね」
抑揚のない声でそう言うと、しーちゃんは私の腰に巻きついていた肌掛け布団の端をペロンと捲る。
そして片手で私の体を跨いですり寄り、吐息がかかる距離まで顔を近づけてきたの。
「ほら、目をつむって」
伏し目がちな色っぽい眼差しとチロリと垣間見える赤い舌先が、あの夜の絡みつくようなキスを思い出させる。
「あ……ヤッ……」
また無理やりされるかもしれない。
そう考えたら急に鼓動がうるさくなって、体温が上昇していくのを止められなかった。
「ふふ。顔赤いよ」
しーちゃんは満足げに囁くと私の前髪を人差し指で左右にかきわけて…………そこに容赦なくデコピンしたんだ!?
「いたっ!」
「あはは。何かイチイチ反応が新鮮。ねーそろそろ起きたら? 頬にくっきり枕ジワついててヤバいよ」
「!!??※※?!」
からかわれた!? う……百戦錬磨めぇ〜!
やり場のない怒りと恥ずかしさ、拍子抜けしたやら悔しいやらで。私は指摘を受けたほっぺを手の甲でゴシゴシ擦りながら、上目づかいで睨みつける。
「しーちゃんのそういうとこ、どーかと思う。女の子みんながみんな、しーちゃんのS系のノリを受け入れると思わないでよね」
厭味を込めて吐き捨ててみたのに、しーちゃんは私から奪った枕を胸に抱きながらしれっとした顔を返すの。
「ん、別に。セリにしかしないし」
ちょっとぉ! 私、Mとかじゃないからね!?
思わず叫びかけたんだけどまた絶対からかわれるのが分かって、グッと口を一文字に結んだ。
その様子がよっぽど間抜けだったのか、しーちゃんは珍しく声を出して笑う。
「飽きないわけだよね。20年一緒にいても、まだまだ見た事ないカオがあるんだからさ」
屈託ない笑顔に、私の胸はドキンと跳ねた。
こっちこそ! だよ。もう何なの?
優しかったり意地悪だったり。甘く迫ってくると思ったら、また子供扱いして……。
しーちゃんの想いを知ってしまってから、悔しいことに私は振り回されっぱなしだ。
声とか、表情とか、仕種とか。しーちゃんから奏でられるもの全部に敏感になって、否応なしに心が乱されてしまう。
意識したら何だか少し気恥ずかしくなって、私はラベンダー色のパジャマの襟を軽く整えた。
そしてベッドから脚を下し、今からどうしようかなとぼんやり思う。
すでに2限目も中途半端だし、午後の授業はもともと休講。お天気が良さそうだからどこかに遊びに行きたいけど、誘える相手も思い浮かばない。
手持無沙汰にフローリングに置いてあった雑誌をラックに戻したりしていると、ベッドに浅く座ったままのしーちゃんと目が合った。
「あ、そう言えば何か用事だったんじゃ……」
「ねえ、午後暇になったんでしょ? だったら撮影付き合ってくれない?」
「えぇ? 何のために?」
「う〜ん。理由が必要なら『荷物持ち』ってことで」
「えぇぇ!?」
普段スマホとお財布しか持ち歩かないくせに! って反論すると、「僕の仕事への協力は惜しまない的なこと言ってなかったっけ?」なんてイジワル顔で返される。
「ほら、20分で準備してよ。ついでにセリのお腹も満たしてあげるからさ」
青山のスタジオかと思った撮影現場は、郊外のお洒落なカフェだった。
私もよく読んでる女性ファッション誌とのコラボ企画らしく、人気モデルの女の子としーちゃんがデートしてるとこばかりをカメラが追いかけている。
休日を楽しむ初々しい社会人カップルの設定?
モノレール下で待ち合わせて、レンガ道を手を繋いで歩いて。2人は雑貨屋さんをひと回りした後、黄色い三角屋根のオープンカフェで足を止めるの。
抹茶のフローズンドリンクを嬉しそうにオーダーする彼女。
その同じストローに口をつけてデレるカレシ=しーちゃんの姿を、私は集まったギャラリーに混じって遠巻きに眺めていた。
かれこれ2時間もこんなシーンばかりを見せつけられると、さすがの私にも複雑な感情が生まれる。
何でしーちゃんはわざわざこんな撮影に呼んだのかなぁ。
『モデルのシキ』はしーちゃんのもう1つの生活の場で、天力者とか守り役とかから離れられる唯一の世界。だからずっと私の侵略を拒んでたように思うの。
こんなふうに仕事をしてるとこを見せてくれたことなんてなかったし、こっそり覗きに行って毒づかれた事もあった。
なのに何で今日? 美人さんを見習って女子力をもっと磨けってこと?
モデルの女の子達は雑誌で見るよりずっと細くて、肌なんて真っ白で。女の私でも見惚れちゃうくらいキレイ。
その隣に引け目なく並べるしーちゃんが、今更ながらに眩しい存在に思える。
「ねー、あのYURIちゃんと撮ってる男の子だれ?」
「あれだよ、あれ! カルペスのCMの!」
ランチ帰りに通りがかったぽいOLさん達が、しーちゃんを見つけて興奮気味にギャラリーの輪に加わってきた。
「も〜ヤバイ! 何であんなにカッコいいの〜!? シキさんが神すぎてツラいんですけどっっ!」
前方にいる女子高生グループは熱狂的なファンみたい。
この時間に制服のままそんなに目立っちゃって大丈夫なの? とこちらが心配になっちゃうくらい、黄色い声をあげてはしゃいでいる。
しーちゃんはすごくカッコいいんだ、たぶん。
でもずっとそばにいた私はすっかり遠視気味。遠くのものがよく見えて、すぐ近くは手探らないと分からないの。
貸切のオープンカフェの最前列で、撮影中のしーちゃんはシャッター音が途切れるとファンに向かって軽く会釈した。
でも特別に私に視線を向けることはしない。
当然かもしれないけどそれがやけに悔しくて、自分でも理解できないくらいイライラする。
あ、もしかして、自分の存在を誇示するために私を仕事場に連れてきたんじゃないの?
こんなにモテモテの僕がプロポーズしてあげてるんだから、さっさとOKしろよ〜的な?
しーちゃんがそんなタイプじゃないことくらい百も承知なのに、胸から棘が生え出すようにどこか攻撃的な気持ちになった。
やだ。何よこれ……。
着ていたワンピースの胸元を鷲づかみ、たまらなくなって踵を返す。
手を伸ばしても届かない距離から、しーちゃんを見るのは何かイヤだ。
だから見物人たちを壁にして待っていようと思ったのに、数歩離れただけのところで突然見知らぬ人に通せんぼされた。
「あのっ、アナスイワンピのお嬢さん! 読者モデルやってみませんか?」
黒いパンツスーツに赤いフレーム眼鏡がインパクト大の30代半ばの女性。
業界人? キャッチ? 華やかさもケバさも感じられないけど……。
「いえ、けっこうです」
不審に思ってあからさまに目を背けると、その人は慌てて両手で名刺を差し出す。
「急に声をかけて、びっくりさせてしまいスミマセン! 私、宝船社で『REAL』というファッション誌を担当してます及川と申しますが――」
「え? リアル?」
聞き慣れた単語と、名刺に印刷された見慣れたロゴとを照らし合わせて、驚いて顔を上げた。
「REALのエディターさん……なんですか?」
私の反応を脈ありととったのか、彼女は子供みたいにパーッと表情を明るめると、早口でどんな事をするのか説明してくれる。
「今回は男性ファッション誌の夏祭り企画なんです。浴衣姿を数カット撮らせてもらえると嬉しいんですけどー」
この人はもちろん、私としーちゃんが繋がってることを知らない。
真剣に誘ってくれてるのが申し訳なくて、「ちょっと待って下さい」といったん制する。
「あのREALは、私ちょっと……」
「あぁすいません。今回の依頼はREALじゃないんですよ。大学生向けの兄弟誌で、急きょ女の子をお願いされてまして」
「そう……なんですか?」
少し考えて、それならと思う。
人前に出て目立つようなことは苦手だけど、ちょっと華やかな世界に出ることで自信に繋がるなら嬉しい。
しーちゃんも切っ掛けは読モだった。
あんな風にキラキラ輝けたら『天力者の姫』なんていう肩書がなくても、存在価値を確かめることができるのかなぁ。
「じゃあ私、やってみまグフぅっ……」
悩んだ末の前向きな返事は、突然伸びてきた大きな手に羽交い絞めにされ、口を塞がれる形で言葉尻を潰されてしまった。
形の良い唇。さっきから頬に触れていた柔らかい羽根の正体はコレだったのかって思う。
眠気眼をこすってぼんやりと天井を眺めると、ベッドの縁に腰かけていたしーちゃんがそのまま腕を伸ばして頭上のカーテンを開けた。
「もう10時まわってるよ。休講? サボり? とりあえずフリーって思っていいわけ?」
高いところから差し込む日差しが、完全に私を覚醒させる。
枕元を手探ってスマホをつかむと、空しくも2時間前にアラームを消した痕跡があった。
「うそぉ〜〜〜〜」
情けなく叫んで、上半身を勢いよく跳ね上げる。
2限の英文の先生は気まぐれに出席をとる事で有名なんだ。今日がその日だとヤマをはっていたのに、そんな朝に限って寝坊しちゃうなんてついてない。
「もうちょっと早く起こして欲しかったよ〜」
呆れ顔の幼なじみにそう身勝手に泣きついて、腰から下を布団にくるまったままどうにか座る。
毛先の引っかかった長い髪を無意識に指でといていると、それを手伝うようにしーちゃんも指を絡めて一房すくった。
「なに? 昨日、夜遊びでもしてたわけ?」
「違うよ、そんなことしてないもん。たまたま見つけたユーチューブの動画にはまっちゃって……」
そこまで普通に会話して、ふと重大な違和感に気づく。
「ちょっとしーちゃんってば、いつの間に私の部屋に来たの??」
倒れたマニキュアの瓶と食べかけのチョコが混在する机。
2人がけのソファーには脱いだカーディガンが裏返っておいてあるし、フローリングには読みかけのファッション誌がそのままになっている。
キレイにしてるとは言い難い自室を予告なく暴かれたのが恥ずかしくて、私は半ば本気で両の拳を振り上げた。
「来る時はラインとか入れてよ〜。せめてノックするとか」
「何で? 今更じゃない。セリだって僕の部屋にアポなしで乱入してくるくせに」
「いいじゃない、しーちゃんは。生活感のないモデルルームみたいなお部屋で、見られて困るものとかも置かない主義なんだから」
「はぁ。そこね」
不満を訴えた私をしーちゃんはどこか白っとした目で見る。
「ったく、危なっかしいなあ」
「何?」
「もっと警戒心もちなよ。寝ている隙に勝手に肌に触れられて、嫌悪感も示さずスルーなんてさ。普通の男だったら調子にのるよ?」
「なっ……!?」
無遠慮に入ってきて寝込みを襲ったくせに、何て勝手な言い草だろうと思う。
私は唇を尖らせてプイッとわざとらしくそっぽを向いた。
「だってしーちゃんじゃない。どこ触られたって、別にどーも思わないもん」
「ふ〜ん。じゃあもっとちゃんと意識してもらわなきゃね」
抑揚のない声でそう言うと、しーちゃんは私の腰に巻きついていた肌掛け布団の端をペロンと捲る。
そして片手で私の体を跨いですり寄り、吐息がかかる距離まで顔を近づけてきたの。
「ほら、目をつむって」
伏し目がちな色っぽい眼差しとチロリと垣間見える赤い舌先が、あの夜の絡みつくようなキスを思い出させる。
「あ……ヤッ……」
また無理やりされるかもしれない。
そう考えたら急に鼓動がうるさくなって、体温が上昇していくのを止められなかった。
「ふふ。顔赤いよ」
しーちゃんは満足げに囁くと私の前髪を人差し指で左右にかきわけて…………そこに容赦なくデコピンしたんだ!?
「いたっ!」
「あはは。何かイチイチ反応が新鮮。ねーそろそろ起きたら? 頬にくっきり枕ジワついててヤバいよ」
「!!??※※?!」
からかわれた!? う……百戦錬磨めぇ〜!
やり場のない怒りと恥ずかしさ、拍子抜けしたやら悔しいやらで。私は指摘を受けたほっぺを手の甲でゴシゴシ擦りながら、上目づかいで睨みつける。
「しーちゃんのそういうとこ、どーかと思う。女の子みんながみんな、しーちゃんのS系のノリを受け入れると思わないでよね」
厭味を込めて吐き捨ててみたのに、しーちゃんは私から奪った枕を胸に抱きながらしれっとした顔を返すの。
「ん、別に。セリにしかしないし」
ちょっとぉ! 私、Mとかじゃないからね!?
思わず叫びかけたんだけどまた絶対からかわれるのが分かって、グッと口を一文字に結んだ。
その様子がよっぽど間抜けだったのか、しーちゃんは珍しく声を出して笑う。
「飽きないわけだよね。20年一緒にいても、まだまだ見た事ないカオがあるんだからさ」
屈託ない笑顔に、私の胸はドキンと跳ねた。
こっちこそ! だよ。もう何なの?
優しかったり意地悪だったり。甘く迫ってくると思ったら、また子供扱いして……。
しーちゃんの想いを知ってしまってから、悔しいことに私は振り回されっぱなしだ。
声とか、表情とか、仕種とか。しーちゃんから奏でられるもの全部に敏感になって、否応なしに心が乱されてしまう。
意識したら何だか少し気恥ずかしくなって、私はラベンダー色のパジャマの襟を軽く整えた。
そしてベッドから脚を下し、今からどうしようかなとぼんやり思う。
すでに2限目も中途半端だし、午後の授業はもともと休講。お天気が良さそうだからどこかに遊びに行きたいけど、誘える相手も思い浮かばない。
手持無沙汰にフローリングに置いてあった雑誌をラックに戻したりしていると、ベッドに浅く座ったままのしーちゃんと目が合った。
「あ、そう言えば何か用事だったんじゃ……」
「ねえ、午後暇になったんでしょ? だったら撮影付き合ってくれない?」
「えぇ? 何のために?」
「う〜ん。理由が必要なら『荷物持ち』ってことで」
「えぇぇ!?」
普段スマホとお財布しか持ち歩かないくせに! って反論すると、「僕の仕事への協力は惜しまない的なこと言ってなかったっけ?」なんてイジワル顔で返される。
「ほら、20分で準備してよ。ついでにセリのお腹も満たしてあげるからさ」
青山のスタジオかと思った撮影現場は、郊外のお洒落なカフェだった。
私もよく読んでる女性ファッション誌とのコラボ企画らしく、人気モデルの女の子としーちゃんがデートしてるとこばかりをカメラが追いかけている。
休日を楽しむ初々しい社会人カップルの設定?
モノレール下で待ち合わせて、レンガ道を手を繋いで歩いて。2人は雑貨屋さんをひと回りした後、黄色い三角屋根のオープンカフェで足を止めるの。
抹茶のフローズンドリンクを嬉しそうにオーダーする彼女。
その同じストローに口をつけてデレるカレシ=しーちゃんの姿を、私は集まったギャラリーに混じって遠巻きに眺めていた。
かれこれ2時間もこんなシーンばかりを見せつけられると、さすがの私にも複雑な感情が生まれる。
何でしーちゃんはわざわざこんな撮影に呼んだのかなぁ。
『モデルのシキ』はしーちゃんのもう1つの生活の場で、天力者とか守り役とかから離れられる唯一の世界。だからずっと私の侵略を拒んでたように思うの。
こんなふうに仕事をしてるとこを見せてくれたことなんてなかったし、こっそり覗きに行って毒づかれた事もあった。
なのに何で今日? 美人さんを見習って女子力をもっと磨けってこと?
モデルの女の子達は雑誌で見るよりずっと細くて、肌なんて真っ白で。女の私でも見惚れちゃうくらいキレイ。
その隣に引け目なく並べるしーちゃんが、今更ながらに眩しい存在に思える。
「ねー、あのYURIちゃんと撮ってる男の子だれ?」
「あれだよ、あれ! カルペスのCMの!」
ランチ帰りに通りがかったぽいOLさん達が、しーちゃんを見つけて興奮気味にギャラリーの輪に加わってきた。
「も〜ヤバイ! 何であんなにカッコいいの〜!? シキさんが神すぎてツラいんですけどっっ!」
前方にいる女子高生グループは熱狂的なファンみたい。
この時間に制服のままそんなに目立っちゃって大丈夫なの? とこちらが心配になっちゃうくらい、黄色い声をあげてはしゃいでいる。
しーちゃんはすごくカッコいいんだ、たぶん。
でもずっとそばにいた私はすっかり遠視気味。遠くのものがよく見えて、すぐ近くは手探らないと分からないの。
貸切のオープンカフェの最前列で、撮影中のしーちゃんはシャッター音が途切れるとファンに向かって軽く会釈した。
でも特別に私に視線を向けることはしない。
当然かもしれないけどそれがやけに悔しくて、自分でも理解できないくらいイライラする。
あ、もしかして、自分の存在を誇示するために私を仕事場に連れてきたんじゃないの?
こんなにモテモテの僕がプロポーズしてあげてるんだから、さっさとOKしろよ〜的な?
しーちゃんがそんなタイプじゃないことくらい百も承知なのに、胸から棘が生え出すようにどこか攻撃的な気持ちになった。
やだ。何よこれ……。
着ていたワンピースの胸元を鷲づかみ、たまらなくなって踵を返す。
手を伸ばしても届かない距離から、しーちゃんを見るのは何かイヤだ。
だから見物人たちを壁にして待っていようと思ったのに、数歩離れただけのところで突然見知らぬ人に通せんぼされた。
「あのっ、アナスイワンピのお嬢さん! 読者モデルやってみませんか?」
黒いパンツスーツに赤いフレーム眼鏡がインパクト大の30代半ばの女性。
業界人? キャッチ? 華やかさもケバさも感じられないけど……。
「いえ、けっこうです」
不審に思ってあからさまに目を背けると、その人は慌てて両手で名刺を差し出す。
「急に声をかけて、びっくりさせてしまいスミマセン! 私、宝船社で『REAL』というファッション誌を担当してます及川と申しますが――」
「え? リアル?」
聞き慣れた単語と、名刺に印刷された見慣れたロゴとを照らし合わせて、驚いて顔を上げた。
「REALのエディターさん……なんですか?」
私の反応を脈ありととったのか、彼女は子供みたいにパーッと表情を明るめると、早口でどんな事をするのか説明してくれる。
「今回は男性ファッション誌の夏祭り企画なんです。浴衣姿を数カット撮らせてもらえると嬉しいんですけどー」
この人はもちろん、私としーちゃんが繋がってることを知らない。
真剣に誘ってくれてるのが申し訳なくて、「ちょっと待って下さい」といったん制する。
「あのREALは、私ちょっと……」
「あぁすいません。今回の依頼はREALじゃないんですよ。大学生向けの兄弟誌で、急きょ女の子をお願いされてまして」
「そう……なんですか?」
少し考えて、それならと思う。
人前に出て目立つようなことは苦手だけど、ちょっと華やかな世界に出ることで自信に繋がるなら嬉しい。
しーちゃんも切っ掛けは読モだった。
あんな風にキラキラ輝けたら『天力者の姫』なんていう肩書がなくても、存在価値を確かめることができるのかなぁ。
「じゃあ私、やってみまグフぅっ……」
悩んだ末の前向きな返事は、突然伸びてきた大きな手に羽交い絞めにされ、口を塞がれる形で言葉尻を潰されてしまった。
 「いや、ゴメンネ。それ却下で」
しーちゃんが私の自由を奪ったまま、代わりに彼女に頭を下げる。
どこから現れたの? 撮影は終わったの? こんなとこに出てきちゃって大丈夫なの!?
思いがけない人気モデルの登場。動揺したのは私だけじゃなかったらしく、エディターさんもぽかんと口を開いて表情に困惑の色を見せる。
「はわわゎゎ……シキ君? 何でですか?」
「だってそれ今朝言ってたやつでしょ? ヤダよ、無理。おまけで水着撮影あるじゃん」
「あぁぁぁちょっと! それを先に言っちゃ〜! おいおい説明してくとこだったんですから。ほらぁこちらのお嬢さんの柔らかそうな体のラインを見て下さい。
絶対に読者受けすると思うんです!」
「うん、だからこの子だけはダメね。露出の多い格好なんかでメンズ誌に載って、読者様に妙な想像でもされたら困るからさ」
力なく項垂れる彼女にピシャリとそう言い放って、しーちゃんは私の体をクルリと自分に向けて回転させた。
「読モがダメとは言わないけどさ。セリもちゃんと話を聞いてから返事しなよね」
有無を言わさず手の中の名刺を抜き取られ、私は反抗して唇を尖らせる。
「別に、水着だっていいのに……」
「はあ? あんなカッコやこんなカッコとか要求されるよ。セリは調子に乗って何でもやっちゃうでしょ? 僕にも見せた事ないとこ他のヤツらに見せてどーすんのさ」
「ちょっ……! 誤解を招くような言い方しないでよぉ」
身勝手な理由に、不必要な束縛。
普段なら反発してそうな場面なのに、今日の私は不思議とイヤじゃないから困るの。
やだ。顔が熱い…………。
「撮影一段落したんだ。2階で休憩とってイイって言うからさ、セリも一緒においで」
しーちゃんはそう言うと私の手首を掴んで、カフェ店内へと歩き出した。
「ほら、樹さんも」
「あ、はいっ」
同行を促された彼女は状況が飲みこめず、オロオロしながら追いかけてくる。
私の手を引いたまま見物人の脇を堂々と通り抜けるしーちゃん。樹さんは周囲をチラチラと気にしながら、口元に手を添えて小声で尋ねる。
「あの〜。シキ君とこちらのお嬢さんの関係って……」
しーちゃんは「う〜ん」と困ったように唸ってから、彼女ではなく私に振り返る。
「ねー、何て説明すればいい?」
う……真顔で分かってる事を聞かないでよ。つい言葉に躓いちゃうじゃない。
「幼なじみ……です」
「ふふ、だって樹さん。まー明日は違うかもしれないんだけどね」
「しーちゃん!?」
意味深な台詞を吐くしーちゃんに、どう返していいものか困ってわざとそっぽを向いた。
「はいはい。ふくれないでねー」
しーちゃんは尽かさず私のほっぺたを摘まんで顔の向きを戻させると、ニヤリと唇の端を上げる。
だからそういうのヤメてってば……。意志とは裏腹に赤面しちゃうじゃない。
「仲良しなんですね」
樹さんは私達に視線を向けて、きょとんと眼を丸くした。
「もう6年のお付き合いになりますけど、初めて見ましたよ。シキ君ってばあなたの事はいつもこんな風に見つめるんですか? カメラの前でもそのカオしてくれたら最強なのに」
白い板壁に囲まれ、ダークブラウンにペイントされた木のテーブルセットが並ぶシャビーな雰囲気の店内。
渋くてお洒落な空間はメンズファッション誌で取り上げるにぴったりなカフェだなと思う。
ふわりと香るコーヒー豆の芳ばしさと、焼き菓子の甘いバターの匂い。
絶妙なハーモニーを鼻で楽しみながら、私はしーちゃんに続いて右奥にある階段を上った。
「お疲れさまです」
居心地の良さそうなソファーがコの字型に置かれた2階のティールームでは、7、8人の関係者が和気あいあいと談笑していた。
撮影カメラマンさんとアシスタントさん。そしてたぶん編集者の人たち。
細くしなやかな手を振っている女の子達はもう素材がぜんぜん違うから、モデルさんなんだって一目で分かる。
「シキ、お疲れ!」
「遅いよ〜。アイスコーヒーで良かったよね?」
しーちゃんが輪に加わるとみんなが柔らかい表情で迎え入れるのを見て、ここでもしーちゃんは特別な存在なんだって感じた。
触れ合う人を片っ端からトリコにして、どこにいっても居場所を確保できる才能。
誇らしくも妬ましくもあって、私は入口手前で立ち止まった。
「セリ、おいで」
しーちゃんが振り向いて、ここに座れと手招きする。
それを合図に室内にいた全員が一斉にこちらに注目したから、私は焦って会釈をした。
「初めまして……お邪魔します」
「え? なになに? シキのこれ?」
年長者の男性が小指をたててニヤニヤと笑う。
「あ〜、だからブルーベリーミルクフローズンなのね。おかしいと思ったわ、シキ君がこんな激甘オーダーするなんて」
撮影の小道具らしき雑貨を数えていた女性は、振り返って甲高い声をあげた。
周囲の大人たちに私との事をからかわれたしーちゃんは、反論することなくただ困ったように苦笑った。
「はいはい、もういいでしょ」
テレ隠しにぶっきらぼうに返答し、子供っぽく口を一文字に結ぶ姿なんて珍しい。
レアなものが見れたなあって、私はちょっと愉快な気持ちでソファーに座る。
「はい。これセリのね」
「……ありがと」
甘酸っぱいブルーベリーとシャリシャリした氷の触感を楽しんでいると、少ししてカフェの店員さんがやって来た。
テーブルの中央にカラフルな焼き菓子を並べて「当店からのサービスです」なんて嬉しいことを言ってくれる。
イチゴやオレンジのマドレーヌ。チョコや抹茶のフィナンシェ。ピスタチオやカシスのマカロンなんて、まるで宝石みたいにキレイ。
「わ〜おいしそう♥」
心の歓声が思わず口に出て、私は慌てて両手で覆う。
だって誰も手を伸ばしたりしてないんだもの。甘いものが好きじゃないのか、飛びついたりしないのがマナーなのか……。
とにかく、目の前にこんなに心躍る魅力的なスイーツが広がっているのに、周囲の人達はびっくりするくらい無関心なの。
う……食べたいなぁ。
でもさすがに部外者の私が現場の差し入れに手をつけるわけにはいかないよね。
「何てカオしてるわけ?」
そんな私の葛藤に気付いたしーちゃんは、隣でクスクスと可笑しそうに笑った。
「頂きなよ。大好物じゃん」
「でも、誰も食べてないのに……」
「大丈夫。どうせこういうのいつも余っちゃうんだよね。だからほら、セリに食べてもらわないと困るって」
しーちゃんにそう言われて恐る恐る周囲を見渡すと、樹さんが「どうぞどうぞ〜」と取り皿とヒメフォークを手渡してくれた。
それはまるで免罪符。
丁寧にお礼を言って身を乗り出し、私はますますテンションを上げる。
「ね〜しーちゃん、このマカロンころころしててすっごく可愛いね! 全種類食べたくなっちゃうけどちょっと我慢して、コレとコレだけ頂こうかな。
あ〜〜でもやっぱり、こっちとそっちも食べていい?」
一応、許可を得てからと思って振り返ったのに、しーちゃんは何がツボだったのかお腹を抱えて笑ってるの。
「う……食いしん坊とかって言いたいんでしょ?」
欲しいものはしっかりお皿にとって、私は拗ねながら自分の席に戻る。
しーちゃんは私の頬にかかった髪を指先ではじきながら、ただ優しい目を返した。
「今日は連れてきたかいがあったよ。ほらこの前は、蒼に先を越されちゃって悔しかったからさ」
私の頭をクシャリと撫でたしーちゃんは、その後スタッフさんに呼ばれて颯爽と階段を降りて行く。
この前って、カフェテリアでの新作ケーキのこと? もお、何よ。ワンコの餌付けじゃないんだから!
遠ざかる背中に向かって心で毒づいてみたものの、裏腹に顔が上気していくのを止められない。
しーちゃんに見つめられていつもと同じように触れられただけなのに、こんなにもドキドキしちゃうなんていったい私ってばどうしたんだろう。
違う、私じゃない。しーちゃんがおかしいの。何か甘すぎるの!
気にしないフリをしていた『縁側でのキス』が急にフラッシュバックして、恥ずかしさで1人悶えそうになる。
『覚悟』なんてできない。このままじゃ心臓がもたないよ。
しーちゃんの本気に飲みこまれそうになる感情を振り切りたくて、私はお皿に残っていたマカロンをつまむと丸ごと口の中に放り投げた。
「よくそんなに食べられるわね」
驚きと呆れを含んだ物言いで、そう声をかけてきた女の子がいた。
170センチは超えてるだろう長身に、サラサラのロングヘアー。シンプルなスキニ―パンツにタンクトップを重ね着しただけのファッションだけど、
そこから伸びた細長い手足がまるでアクセサリーみたいでお洒落に映る。
私より少しだけ年上かな? 涼しげな目元がアジアンビューティーと呼ぶのにぴったりだって思った。
「あの……」
「あ、いきなりゴメンね。気持ちイイくらいの食べっぷりだから、体重とかスタイルとか気になんないもんかなと、ふと疑問で」
突然のことに思わず体を強張らせた私を気遣ってから、彼女はサバサバした笑顔を見せる。
言葉に微妙な棘があるような気もするけど、嫌味というわけでもないみたい。
キレイな髪から香る爽やかなグリーンアップル。これがこの女の人のイメージだと思うと悪い印象はなくて、私は多少戸惑いながらも口角を上げる。
「体重はもちろん気にはなりますよ。でもそれ以上に甘いものに目がなくて」
「へ〜ある意味勇気あるね。アタシも甘いもの大好きだけど、やっぱすごく気を付けてるから」
「そうですよね。モデルさんは大変ですもんね」
「あぁ、アタシはモデルじゃないよ。ただシキって男のくせに驚くくらい整ってるじゃない? 横に並びたいんだったら、それなりの努力はしとかないとね」
「へ?」
急にしーちゃんの名前を出されて、思わず目を丸く見開いてしまった。
そんな私にクスリと小さな笑いを零し、彼女は去り際に軽く肩を叩いて囁いたの。
「あなた、まだ彼女とかじゃないんでしょ? アタシ明日、告白予定なので邪魔しないでね」
そこまで言われて、鈍い私はやっとハッとする。
この美人は一体だあれ?? って。
「いや、ゴメンネ。それ却下で」
しーちゃんが私の自由を奪ったまま、代わりに彼女に頭を下げる。
どこから現れたの? 撮影は終わったの? こんなとこに出てきちゃって大丈夫なの!?
思いがけない人気モデルの登場。動揺したのは私だけじゃなかったらしく、エディターさんもぽかんと口を開いて表情に困惑の色を見せる。
「はわわゎゎ……シキ君? 何でですか?」
「だってそれ今朝言ってたやつでしょ? ヤダよ、無理。おまけで水着撮影あるじゃん」
「あぁぁぁちょっと! それを先に言っちゃ〜! おいおい説明してくとこだったんですから。ほらぁこちらのお嬢さんの柔らかそうな体のラインを見て下さい。
絶対に読者受けすると思うんです!」
「うん、だからこの子だけはダメね。露出の多い格好なんかでメンズ誌に載って、読者様に妙な想像でもされたら困るからさ」
力なく項垂れる彼女にピシャリとそう言い放って、しーちゃんは私の体をクルリと自分に向けて回転させた。
「読モがダメとは言わないけどさ。セリもちゃんと話を聞いてから返事しなよね」
有無を言わさず手の中の名刺を抜き取られ、私は反抗して唇を尖らせる。
「別に、水着だっていいのに……」
「はあ? あんなカッコやこんなカッコとか要求されるよ。セリは調子に乗って何でもやっちゃうでしょ? 僕にも見せた事ないとこ他のヤツらに見せてどーすんのさ」
「ちょっ……! 誤解を招くような言い方しないでよぉ」
身勝手な理由に、不必要な束縛。
普段なら反発してそうな場面なのに、今日の私は不思議とイヤじゃないから困るの。
やだ。顔が熱い…………。
「撮影一段落したんだ。2階で休憩とってイイって言うからさ、セリも一緒においで」
しーちゃんはそう言うと私の手首を掴んで、カフェ店内へと歩き出した。
「ほら、樹さんも」
「あ、はいっ」
同行を促された彼女は状況が飲みこめず、オロオロしながら追いかけてくる。
私の手を引いたまま見物人の脇を堂々と通り抜けるしーちゃん。樹さんは周囲をチラチラと気にしながら、口元に手を添えて小声で尋ねる。
「あの〜。シキ君とこちらのお嬢さんの関係って……」
しーちゃんは「う〜ん」と困ったように唸ってから、彼女ではなく私に振り返る。
「ねー、何て説明すればいい?」
う……真顔で分かってる事を聞かないでよ。つい言葉に躓いちゃうじゃない。
「幼なじみ……です」
「ふふ、だって樹さん。まー明日は違うかもしれないんだけどね」
「しーちゃん!?」
意味深な台詞を吐くしーちゃんに、どう返していいものか困ってわざとそっぽを向いた。
「はいはい。ふくれないでねー」
しーちゃんは尽かさず私のほっぺたを摘まんで顔の向きを戻させると、ニヤリと唇の端を上げる。
だからそういうのヤメてってば……。意志とは裏腹に赤面しちゃうじゃない。
「仲良しなんですね」
樹さんは私達に視線を向けて、きょとんと眼を丸くした。
「もう6年のお付き合いになりますけど、初めて見ましたよ。シキ君ってばあなたの事はいつもこんな風に見つめるんですか? カメラの前でもそのカオしてくれたら最強なのに」
白い板壁に囲まれ、ダークブラウンにペイントされた木のテーブルセットが並ぶシャビーな雰囲気の店内。
渋くてお洒落な空間はメンズファッション誌で取り上げるにぴったりなカフェだなと思う。
ふわりと香るコーヒー豆の芳ばしさと、焼き菓子の甘いバターの匂い。
絶妙なハーモニーを鼻で楽しみながら、私はしーちゃんに続いて右奥にある階段を上った。
「お疲れさまです」
居心地の良さそうなソファーがコの字型に置かれた2階のティールームでは、7、8人の関係者が和気あいあいと談笑していた。
撮影カメラマンさんとアシスタントさん。そしてたぶん編集者の人たち。
細くしなやかな手を振っている女の子達はもう素材がぜんぜん違うから、モデルさんなんだって一目で分かる。
「シキ、お疲れ!」
「遅いよ〜。アイスコーヒーで良かったよね?」
しーちゃんが輪に加わるとみんなが柔らかい表情で迎え入れるのを見て、ここでもしーちゃんは特別な存在なんだって感じた。
触れ合う人を片っ端からトリコにして、どこにいっても居場所を確保できる才能。
誇らしくも妬ましくもあって、私は入口手前で立ち止まった。
「セリ、おいで」
しーちゃんが振り向いて、ここに座れと手招きする。
それを合図に室内にいた全員が一斉にこちらに注目したから、私は焦って会釈をした。
「初めまして……お邪魔します」
「え? なになに? シキのこれ?」
年長者の男性が小指をたててニヤニヤと笑う。
「あ〜、だからブルーベリーミルクフローズンなのね。おかしいと思ったわ、シキ君がこんな激甘オーダーするなんて」
撮影の小道具らしき雑貨を数えていた女性は、振り返って甲高い声をあげた。
周囲の大人たちに私との事をからかわれたしーちゃんは、反論することなくただ困ったように苦笑った。
「はいはい、もういいでしょ」
テレ隠しにぶっきらぼうに返答し、子供っぽく口を一文字に結ぶ姿なんて珍しい。
レアなものが見れたなあって、私はちょっと愉快な気持ちでソファーに座る。
「はい。これセリのね」
「……ありがと」
甘酸っぱいブルーベリーとシャリシャリした氷の触感を楽しんでいると、少ししてカフェの店員さんがやって来た。
テーブルの中央にカラフルな焼き菓子を並べて「当店からのサービスです」なんて嬉しいことを言ってくれる。
イチゴやオレンジのマドレーヌ。チョコや抹茶のフィナンシェ。ピスタチオやカシスのマカロンなんて、まるで宝石みたいにキレイ。
「わ〜おいしそう♥」
心の歓声が思わず口に出て、私は慌てて両手で覆う。
だって誰も手を伸ばしたりしてないんだもの。甘いものが好きじゃないのか、飛びついたりしないのがマナーなのか……。
とにかく、目の前にこんなに心躍る魅力的なスイーツが広がっているのに、周囲の人達はびっくりするくらい無関心なの。
う……食べたいなぁ。
でもさすがに部外者の私が現場の差し入れに手をつけるわけにはいかないよね。
「何てカオしてるわけ?」
そんな私の葛藤に気付いたしーちゃんは、隣でクスクスと可笑しそうに笑った。
「頂きなよ。大好物じゃん」
「でも、誰も食べてないのに……」
「大丈夫。どうせこういうのいつも余っちゃうんだよね。だからほら、セリに食べてもらわないと困るって」
しーちゃんにそう言われて恐る恐る周囲を見渡すと、樹さんが「どうぞどうぞ〜」と取り皿とヒメフォークを手渡してくれた。
それはまるで免罪符。
丁寧にお礼を言って身を乗り出し、私はますますテンションを上げる。
「ね〜しーちゃん、このマカロンころころしててすっごく可愛いね! 全種類食べたくなっちゃうけどちょっと我慢して、コレとコレだけ頂こうかな。
あ〜〜でもやっぱり、こっちとそっちも食べていい?」
一応、許可を得てからと思って振り返ったのに、しーちゃんは何がツボだったのかお腹を抱えて笑ってるの。
「う……食いしん坊とかって言いたいんでしょ?」
欲しいものはしっかりお皿にとって、私は拗ねながら自分の席に戻る。
しーちゃんは私の頬にかかった髪を指先ではじきながら、ただ優しい目を返した。
「今日は連れてきたかいがあったよ。ほらこの前は、蒼に先を越されちゃって悔しかったからさ」
私の頭をクシャリと撫でたしーちゃんは、その後スタッフさんに呼ばれて颯爽と階段を降りて行く。
この前って、カフェテリアでの新作ケーキのこと? もお、何よ。ワンコの餌付けじゃないんだから!
遠ざかる背中に向かって心で毒づいてみたものの、裏腹に顔が上気していくのを止められない。
しーちゃんに見つめられていつもと同じように触れられただけなのに、こんなにもドキドキしちゃうなんていったい私ってばどうしたんだろう。
違う、私じゃない。しーちゃんがおかしいの。何か甘すぎるの!
気にしないフリをしていた『縁側でのキス』が急にフラッシュバックして、恥ずかしさで1人悶えそうになる。
『覚悟』なんてできない。このままじゃ心臓がもたないよ。
しーちゃんの本気に飲みこまれそうになる感情を振り切りたくて、私はお皿に残っていたマカロンをつまむと丸ごと口の中に放り投げた。
「よくそんなに食べられるわね」
驚きと呆れを含んだ物言いで、そう声をかけてきた女の子がいた。
170センチは超えてるだろう長身に、サラサラのロングヘアー。シンプルなスキニ―パンツにタンクトップを重ね着しただけのファッションだけど、
そこから伸びた細長い手足がまるでアクセサリーみたいでお洒落に映る。
私より少しだけ年上かな? 涼しげな目元がアジアンビューティーと呼ぶのにぴったりだって思った。
「あの……」
「あ、いきなりゴメンね。気持ちイイくらいの食べっぷりだから、体重とかスタイルとか気になんないもんかなと、ふと疑問で」
突然のことに思わず体を強張らせた私を気遣ってから、彼女はサバサバした笑顔を見せる。
言葉に微妙な棘があるような気もするけど、嫌味というわけでもないみたい。
キレイな髪から香る爽やかなグリーンアップル。これがこの女の人のイメージだと思うと悪い印象はなくて、私は多少戸惑いながらも口角を上げる。
「体重はもちろん気にはなりますよ。でもそれ以上に甘いものに目がなくて」
「へ〜ある意味勇気あるね。アタシも甘いもの大好きだけど、やっぱすごく気を付けてるから」
「そうですよね。モデルさんは大変ですもんね」
「あぁ、アタシはモデルじゃないよ。ただシキって男のくせに驚くくらい整ってるじゃない? 横に並びたいんだったら、それなりの努力はしとかないとね」
「へ?」
急にしーちゃんの名前を出されて、思わず目を丸く見開いてしまった。
そんな私にクスリと小さな笑いを零し、彼女は去り際に軽く肩を叩いて囁いたの。
「あなた、まだ彼女とかじゃないんでしょ? アタシ明日、告白予定なので邪魔しないでね」
そこまで言われて、鈍い私はやっとハッとする。
この美人は一体だあれ?? って。