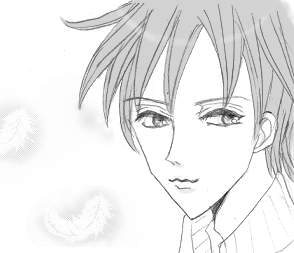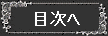二度寝することを諦めて、俺は重い体をゆっくりと起こした。
冷水で顔を洗い、鏡の中の自分と向き合って。
――また、天海のことを思い出す。
林の浄化にすごいエネルギーを消費したはずなのに、アイツは次の日もピンピンしてたっけ。
俺だったら間違いなく3日は嘔吐してるだろうに、何でもない顔でモデルの仕事も普通にこなしたりして。
力の差を感じた。
そりゃあ超えられるなんて思ったことはねーけど。
俺も浄化を何度か繰りかえして、そこそこに自信があったのかもしれない。
天海と肩を並べられる自信が――。思い上がりもいいところだ。
ってなことも有り、俺はあの日以来に会うタイミングを失っている。
天海の話だと正面から妖力を受けたアイツは、しばらく眠り続けたらしい。
5日目には全回復して必修だけは受けてたみてーだけど、学内ですれ違うこともカフェテリアで会うこともなかった。
メールぐらい入れようかって、散々考えてはみた。
でも本家に毎日顔出してるだろう天海があいつの状態を事細かに報告してくれたから、今さら「体平気か?」も、ねー気がして。
掴んだ携帯を、何度もパタリと閉じた。
(……を心配するのは、天海の専売特許だ。俺の出る幕じゃない)
思い上がったとしても、最低限わきまえてる。
そこまで阿呆じゃねーよ。
二度寝することを諦めて、俺は重い体をゆっくりと起こした。
冷水で顔を洗い、鏡の中の自分と向き合って。
――また、天海のことを思い出す。
林の浄化にすごいエネルギーを消費したはずなのに、アイツは次の日もピンピンしてたっけ。
俺だったら間違いなく3日は嘔吐してるだろうに、何でもない顔でモデルの仕事も普通にこなしたりして。
力の差を感じた。
そりゃあ超えられるなんて思ったことはねーけど。
俺も浄化を何度か繰りかえして、そこそこに自信があったのかもしれない。
天海と肩を並べられる自信が――。思い上がりもいいところだ。
ってなことも有り、俺はあの日以来に会うタイミングを失っている。
天海の話だと正面から妖力を受けたアイツは、しばらく眠り続けたらしい。
5日目には全回復して必修だけは受けてたみてーだけど、学内ですれ違うこともカフェテリアで会うこともなかった。
メールぐらい入れようかって、散々考えてはみた。
でも本家に毎日顔出してるだろう天海があいつの状態を事細かに報告してくれたから、今さら「体平気か?」も、ねー気がして。
掴んだ携帯を、何度もパタリと閉じた。
(……を心配するのは、天海の専売特許だ。俺の出る幕じゃない)
思い上がったとしても、最低限わきまえてる。
そこまで阿呆じゃねーよ。
 「あら、蒼。おはよう。朝ごはん出来てるわよ」
「……」
そういえば、実家に戻ってきてたんだっけ……。
あったかい味噌汁の匂いに誘われて、足は自然と1階の居間へ向かっていた。
台所にたつお袋は忙しそうに鍋を揺すりながら、以前と変わらない様子でこちらに振り返る。
現在住んでいる吉祥寺のアパートから、電車で約1時間半。アップダウンの多い横浜市が俺の地元だった。
大学まで決して通えない距離じゃない。
でも天力者として仕事をするには不便で、「学業に集中したいから」と親を説得して、この家を出た。
「おはよう」
1人暮らしを初めてまだ3ヶ月だというのに、すでにこの家の空気が懐かしい。
5人用のダイニングテーブル。いつもの席に座って、差しだされた茶椀に箸をつける。
「親父は?」
「お父さんは病院よ。今日は検査の日なの」
「ふーん。じゃあ、
「あら、蒼。おはよう。朝ごはん出来てるわよ」
「……」
そういえば、実家に戻ってきてたんだっけ……。
あったかい味噌汁の匂いに誘われて、足は自然と1階の居間へ向かっていた。
台所にたつお袋は忙しそうに鍋を揺すりながら、以前と変わらない様子でこちらに振り返る。
現在住んでいる吉祥寺のアパートから、電車で約1時間半。アップダウンの多い横浜市が俺の地元だった。
大学まで決して通えない距離じゃない。
でも天力者として仕事をするには不便で、「学業に集中したいから」と親を説得して、この家を出た。
「おはよう」
1人暮らしを初めてまだ3ヶ月だというのに、すでにこの家の空気が懐かしい。
5人用のダイニングテーブル。いつもの席に座って、差しだされた茶椀に箸をつける。
「親父は?」
「お父さんは病院よ。今日は検査の日なの」
「ふーん。じゃあ、【 蒼くんおはよー。この前はおつかれ様でした〜。 あれから体調はへいきですか? 】 からだった。 時間は1時間前。絵文字だらけの
【 私は元気だよ〜。 ヒマでヒマで、朝からTVばっかり観てるの。 今ね、冬のスイーツ特集やってて。すっごく食べたくなっちゃって♪ 】 スイーツ特集? つけっぱなしだった居間のテレビに、ふと目をやった。 ああ。これか。和栗のパフェに、チョコレートのモンブラン……。ははっ。アイツが好きそうなやつばっかだ。 離れた場所にいるくせに同じものを見てる。そんな感覚に居心地の良さも感じつつ、「うまそうだな」と続けると……。 30秒後、思いがけない一言が返ってきた。
【 もし時間あれば、今日いっしょにリオンに行ってくれませんか? 】 リオン――。ああ、がよく行くケーキ屋の名前か。そっか、俺が実家にいるなんて知らないから。 【悪い。今、横浜で……】 そう打とうとして、ハッとあの約束を思い出す。 ―― 林の浄化がすんだら、私とデートして ―― 『デート』って響きに躊躇いがあって、気にはなってても忘れたフリをしてた。 でもあの時の礼はちゃんとしたくて、が望むならどこかに連れてってやりたいとも考えてる。 (横浜……か) 観覧車に展望台。この時季だったらイルミネーション。 ちょっと寒いかもしんねーけど、海を眺めながら散歩して。疲れたら近くで、甘いものとか食って……。 が好きそうなことのオンパレードじゃねーか。 そう思ったら胸が高鳴って、『天海』という存在を振りかえることなく携帯のボタンを連打してしまう。 【 桜木町まで、来れるか? 】 からのレスは最短記録の7秒後。 満面の笑顔が想像できる、それまで以上に絵文字多めの文面。
【 うん、行くよ〜♪ 今すぐ準備するからね (*⌒▽⌒*)ノ 】 クッ。なんか、本当。らしい、よな。
 待ち合わせは午後3時。ランドマークタワーのある、桜木町の高架下で。
10分前に現れたアイツは俺を見つけるなりバタバタと走りより、1m手前でいったん息を整えた。
「うわぁ、蒼くんゴメン。トイレがやけに混んでて……」
風ではねた前髪を気にして、細い指で何度も撫でるみたいに整える。
その仕種がやけに可愛くて――。
「久しぶり」の一言も口にできず、ただ見つめ返してしまった。
「蒼くん……? あの……」
「……あ、悪い…………」
「うぅっ。もしかして……この髪型、ヘン? ハーフアップっぽく結ってみたんだけどぉ……」
見え隠れする白いうなじ。
落ち着かない様子で数度いじりながら、上目づかいでテレ笑う。
「いや……変じゃない」
むしろ、そういうの……。
「好きだ」
「ありがとー」と明るく答えるとはクルリと俺に背中をむけて、奥に見えた観覧車を指さしながら甲高い声をあげた。
「蒼くん、後でアレ乗りたい!!」
俺のニットの袖をひっぱり子供みたいにはしゃぐと、着ていたワンピースの裾がふわりと揺れる。
黒地にボルドーのアンティークなそれは、のやわらかい雰囲気によく似合っていた。
「また、蝶だ。本当、好きなんだな」
後ろ肩にとまったように描かれた刺繍を見つけ、思わず呟く。
「あ、コレ? この前のご褒美にしーちゃんに貰ったヤツなんだけど、さっそく着てきちゃった。初おろしだよ〜」
(ああ。これが……)
天海からもらった服をうれしそうに着て、無邪気に俺に微笑みかける。
おい。いったいどこまで天然なんだよ……。
分かってたことだけど。初っ端から、苦笑いがこぼれた。
なー、。
いつの間にか、どうしようもないくらい惚れてた――とか言ったら、
お前はどんなカオで、俺を見る?
つかの間の休息。
冷たい潮風を頬にうけながら、俺はゆっくりと半歩前を歩く。
寄り添うことが許されないなら、せめて楯にでもなれればと思って。
待ち合わせは午後3時。ランドマークタワーのある、桜木町の高架下で。
10分前に現れたアイツは俺を見つけるなりバタバタと走りより、1m手前でいったん息を整えた。
「うわぁ、蒼くんゴメン。トイレがやけに混んでて……」
風ではねた前髪を気にして、細い指で何度も撫でるみたいに整える。
その仕種がやけに可愛くて――。
「久しぶり」の一言も口にできず、ただ見つめ返してしまった。
「蒼くん……? あの……」
「……あ、悪い…………」
「うぅっ。もしかして……この髪型、ヘン? ハーフアップっぽく結ってみたんだけどぉ……」
見え隠れする白いうなじ。
落ち着かない様子で数度いじりながら、上目づかいでテレ笑う。
「いや……変じゃない」
むしろ、そういうの……。
「好きだ」
「ありがとー」と明るく答えるとはクルリと俺に背中をむけて、奥に見えた観覧車を指さしながら甲高い声をあげた。
「蒼くん、後でアレ乗りたい!!」
俺のニットの袖をひっぱり子供みたいにはしゃぐと、着ていたワンピースの裾がふわりと揺れる。
黒地にボルドーのアンティークなそれは、のやわらかい雰囲気によく似合っていた。
「また、蝶だ。本当、好きなんだな」
後ろ肩にとまったように描かれた刺繍を見つけ、思わず呟く。
「あ、コレ? この前のご褒美にしーちゃんに貰ったヤツなんだけど、さっそく着てきちゃった。初おろしだよ〜」
(ああ。これが……)
天海からもらった服をうれしそうに着て、無邪気に俺に微笑みかける。
おい。いったいどこまで天然なんだよ……。
分かってたことだけど。初っ端から、苦笑いがこぼれた。
なー、。
いつの間にか、どうしようもないくらい惚れてた――とか言ったら、
お前はどんなカオで、俺を見る?
つかの間の休息。
冷たい潮風を頬にうけながら、俺はゆっくりと半歩前を歩く。
寄り添うことが許されないなら、せめて楯にでもなれればと思って。