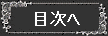◆第五章 1.初夏。すれ違う想い、離せない手
桜散っちゃったねーなんて話してたら、あっという間に風が温かくなって、気づけば梅雨入り前の爽やかな季節が巡ってきた。
大学2年生になった私は単位の取得に追われ始めたけど、それでもOLのフリをして妖力者を追っていた時のことを考えれば、穏やかすぎるほどの日常を送っている。
「悪い、。遅れた」
4限が終わった後の教育学部11号館ロビー。出入りする学生の波をよけて壁にもたれながら立っていると、蒼くんがいつものように駆け寄ってきてくれる。
ジーパンに黒い半袖Tシャツというシンプルなファッションが、硬派な蒼くんに似合っていてカッコイイ。
珍しく額にうっすら汗をかいているのを見つけて、ここまで走ってきてくれたのかなぁって嬉しくなった。
「大丈夫だよ。待ってる間 You Tube でお笑い観てた!」
スマホに繋いでたイヤホンをくるくる巻いてバッグのポケットにしまい、代わりにハンカチを出して蒼くんの額に手を伸ばす。
3年生になった彼は教員資格をとるためにコマ数も課題もドッと増えて、以前よりもずっと授業が忙しくなった。
もう何となく――で構内で会うことは難しくて、少しでも一緒にいたい私は学部を跨いでココで待つのが日課になっている。
「毎日大変だね。また授業伸びちゃったの?」
「いや、今日は研究室に呼ばれてた。実習先まだ決めかねてて」
「後期の教育実習のハナシ? もう決めなきゃダメなの?」
「まー希望があるなら早い方がって事らしーんだけど。うちの高校に行くか、母校の横浜に戻るか。あ、達の秀麗院の高等科も受け入れあったな。
どこにせよ日本史を教えられる高校を選ぼうと思ってる」
「うふふ。じゃあもし秀麗院にいったら、八純にこっそり動画撮ってもらわなきゃね」
「んーじゃあそこは却下だな。八純に恨まれる」
彼はそう言ってわざと困った顔を見せた後、背伸びをしながら汗をぬぐう私に「サンキュー」と笑んだ。
「17時とは思えないほど日が高いな」
大学の門を出て最寄駅まで続く幅の広い並木道で、蒼くんは私の歩調に合わせて並んでくれる。
ちょっと前まではピッタリ寄り添って月を見上げながらお喋りを楽しんでた帰り道。こんなに明るくてこんなに暑かったら、手を繋ぐのさえハードルが高い。
季節の変化がもどかしくて、私はちょっと無口になった。2人きりになりたい。夜の力を借りて恋人らしいことがしたい。
飲みにいこう……ううん。せめてゴハン食べて帰ろうって誘ってみようかなぁ。
意を決して顔を上げるけど、それより1秒早く蒼くんが唇を動かした。
「そう言えば、アパートに戻るのもう少し伸びるかもしれない」
私の方に首を傾けて、申し訳なさそうに目を細める。
「え? 大丈夫? 聖(ひじり)くんのケガ良くないの?」
「弟は退院後順調。ただ今回の事故で妹も不安になってるから、せめて親の仕事が落ち着くまでは実家から通おうかなと」
「うんそっか……そうだね!」
家まで送ってもらって、裏道でキスして別れた頃が何だか遠い。
寂しいから早く戻ってきて! なんてワガママだって分かってるから、口角を上げて聞き分け良く頷いた。
蒼くんの弟が事故にあった=奈良ちゃん事件が片付いたあの日以来、同じように私達がそばにいることは物理的にできなくなった。
毎日追われ気味の蒼くんとの距離が徒歩5分から電車で1時間になって、30分お茶に誘うのでさえ躊躇してしまう。
「ゴメン。夏までにはこっちに戻れるようにしておくから」
「大丈夫だよ、こうやって帰りにお喋りできるだけでも嬉しいし。それに休みに私が横浜に行けばもうちょっとは会えるでしょ? あ、土曜はどう? 久々に観覧車乗りたい!」
努めて明るい声を出すと、彼は余計に困った素振りをした。
「土曜は……わるい。親父の検査が入ってて付き添うことになってる」
「……うん……そっかぁ。じゃあまた今度、時間空いたら教えてね」
「うん、ほんとゴメン」
私の髪を控え目に撫でてこんな風に眉尻を下げる蒼くんを、あれから何度見てるだろう。
どうして「ゴメン」が多いの? 何で遠慮がちに触れるの? あの日駆けつけられなかった事なら、気にしないでって言ったじゃない。
そんな罪悪感より、もっとちゃんと捕まえてて欲しいのに……。
駅のホームは近隣の大学の学生たちで溢れかえっていた。
人波に流されないようにとか、高めのヒールだと転びそうだからとか。心の中でわざわざ理由づけて、彼の腕にそっと自分の腕を絡める。
でも上り電車に乗り込んだ途端、目に飛び込んできた光景に息をのみ、私は反射的にその手を引っ込めてしまった。
(しーちゃん!?)
その車両は見渡す限り、同じCMポスターで埋め尽くされていたの。
 「スゲーな、これ」
車内をグルリと眺めながら、蒼くんは驚いたように小さく呟く。
私の知る限りここまで2本のCMに出てるしーちゃん。スポーツドリンクを爽やかに飲みながらダンスする姿を、初めてテレビで見かけたのは2月頃だった。
たしかにインパクトはあったけど数人の内の1人って感じだったのに、それからたった数か月、今朝から流れたシリーズ第2弾はしーちゃんメインの内容だった。
注目のイケメン――そんな見出しの記事がネットサーフィン中に幾度となく引っかかり、そのたびに私は何とも言いようのない気持ちでスマホを閉じてしまう。
ふと横を向くと、2人の女子高生が黄色い声をあげながら、車内広告をスマホで撮影してるのが目に入った。
必死で腕を伸ばしてシャッター音を響かせては一喜一憂し、あーだこーだって目を輝かせて語っているのがすごく初々しくて可愛い。
ファンなのかな?
チラリと覗き込めば、大事そうに左手で抱えているのもしーちゃんが表紙の雑誌だった。
「スゲーな、これ」
車内をグルリと眺めながら、蒼くんは驚いたように小さく呟く。
私の知る限りここまで2本のCMに出てるしーちゃん。スポーツドリンクを爽やかに飲みながらダンスする姿を、初めてテレビで見かけたのは2月頃だった。
たしかにインパクトはあったけど数人の内の1人って感じだったのに、それからたった数か月、今朝から流れたシリーズ第2弾はしーちゃんメインの内容だった。
注目のイケメン――そんな見出しの記事がネットサーフィン中に幾度となく引っかかり、そのたびに私は何とも言いようのない気持ちでスマホを閉じてしまう。
ふと横を向くと、2人の女子高生が黄色い声をあげながら、車内広告をスマホで撮影してるのが目に入った。
必死で腕を伸ばしてシャッター音を響かせては一喜一憂し、あーだこーだって目を輝かせて語っているのがすごく初々しくて可愛い。
ファンなのかな?
チラリと覗き込めば、大事そうに左手で抱えているのもしーちゃんが表紙の雑誌だった。
 高校の終わりに専属になった、メンズ誌『REAL(リアル)』。
テレビの影響力ってすごいなぁ。
20代男子向けの正統派ファッション誌を、女の子が堂々と持ち歩くことなんて今までならなかったのに。
「天海のヤツ、すっかり芸能人って感じだな。こんなに目立って大丈夫なのかよ」
蒼くんが心配そうに顔を歪める横で、私はただ静かに苦笑った。
憂えてるのはきっと私のガードのこと。祟峻(すいしゅん)の鏡を取り戻したことで『女性天子』の力は認められたものの、子孫を残す前に何かあったら……って、
お父さんの監視はより厳しいものになった。
私の行動を制御できなかったことでしーちゃんはいつも以上に叱られただろうし、守護の役目をますます重く言いつけられたのは想像できる。
でも反抗するみたいに仕事をバンバン入れて、この数か月しーちゃんが家に立ち寄る事はほとんどなかった。
もしかしたら息苦しい世界とワガママな私に、ついに愛想を尽かしちゃったのかもしれない。
「ひどいよね。ゴールデンウィーク前にちょこっと会いに来たきりなの。もう1週間以上も電話もないし」
思わずこぼしたそんな台詞を、私はどんなカオで口にしたんだろう。
蒼くんは微かに目を見開いた後すぐさま整った笑顔を見せて、何気なくこちらから視線を外した。
「改札に来てると思う」
「え?」
「昨夜別件で連絡入って、を迎えに来るって言ってたから」
駅ビルにダイレクトに続く自動改札機の前。行き交う人々のあらゆる想いを含んだ視線を集めて、しーちゃんは涼しい顔で私たちに向かって左手をあげた。
長い脚を引き立てるホワイトジーンズのパンツに、意外と筋肉質な上半身を浮き立たせるぴったりとした濃い色味のカットソー。
何でもないファッションがやけに目立つのは、醸し出すオーラにさらに磨きがかかったせいかもしれない。
(何か恥ずかしい。地元の駅で待ち合わせなんて最近なかったから)
しーちゃんの歩みと目線の先を追いかけて、周囲の注目がパラパラとこちらに移る。
焦った私は手を振り返すこともしないで、蒼くんの背中に隠れるようにゆっくりとSuicaをかざした。
「これと、これが来週の授業の課題だから。忘れずに出席しろよ」
「毎度の事ながらアリガトね。蒼がいてくれて本当助かる」
軽い挨拶を交わして分厚いプリントを受け渡す2人。私は輪には加わらず、一歩下がった所でそのやりとりを見ていた。
「忙しそうだな。大学にほとんど顔出してないみてーだけど、単位大丈夫なのか?」
蒼くんがぽつりと問いかけると、しーちゃんは「おかげさまで」なんて柔らかく口角を上げる。
「去年までに拾えるものは拾ったし、蒼みたいに教職とるわけじゃないからさ。前期はのんびり通おうかなーって」
「昨日も徹夜だったんじゃねーの? モデルってあんな時間まで働くのかよ」
「あぁ、深夜にLINEごめんね。違うよ、あれは本業の方。妖人(ようびと)の小さい浄化の依頼が入っちゃってさ」
「この多忙な状況で、そっちもかよ」
蒼くんはフゥと小さく息をつき「どんだけストイックなんだ」って突っ込んだ後、急に声のトーンを落としてボソリと呟く。
「悪いな、お前の負担を分散させる為の『契約』でもあったのに。こんな時に動けなくて」
もどかしそうな、悔しそうな横顔。
そんな気持ちを受け止めるようにしーちゃんはいったん口をつぐみ、少し間をおいてから蒼くんの肩をトンッと拳で突く。
「お互い様でしょ? 蒼がいてくれるから、僕も自由にやれるんだし」
そして蒼くんの陰にいた私にいきなり視線を投げ、前屈みになって顔を近づけた。
「で、何? はさっきから何で隠れてるわけ?」
「! べ、別に隠れてなんか……」
眼鏡越しに見つめられるのは苦手。
しどろもどろになって目を逸らすと、つれない態度にカチンときたのか、しーちゃんは私の腕を掴んで強引に前へと引きずり出す。
「ほら、そろそろ時間だよ。蒼も僕も多忙なんだからさ、早く何か言いなって」
「え? え? 何よ急に……」
体をクルッと回転させられて押さえつけられたまま、蒼くんの正面へと突き出される。
見上げると彼はちょっと切ないカオを返して、「悪い」なんてまた謝ったの。
(だから……それはどんな意味なのよ……)
『蒼をこの世界にあんま縛り付けないであげたら?』
昔しーちゃんに釘を刺されたことが脳裏をよぎった。
彼にとって天力者であることは義務じゃない。負担に思われるのだけは辛くて、私は思わず声を張り上げる。
「蒼くんはいいの! 無理しない範囲で一緒にいてくれれば、それで嬉しいんだから!」
「……」
「私はあれから稽古も続けてるし、自分の事は自分で守れるようにするよ。蒼くんが動けない分、代わりに仕事をこなしたって平気なんだから」
助かるよって肩の力を抜いて欲しかったのに、私の言葉を聞いた蒼くんはますます険しい表情になった。
「……それじゃあ意味ねーだろ」
「え?」
「いや、うん。サンキュー。また月曜な」
蒼くんと駅で別れた後、当たり前だけどしーちゃんと2人きりになった。
日の当たる時間帯に並んで帰宅するのはずいぶん久しぶりのこと。他愛もないお喋りさえちょっとくすぐったくて、私は少し距離をとって歩く。
「ねー。寄り道して……※※とか買ってく?」
「ん? なに? 何か買うの?」
すれ違う人達の話し声と車の音が邪魔をして、ここまででもう3回も聞き返してしまった。
活気あるアーケード商店街の入り口に差しかかったところで、しーちゃんはさすがにうんざりした顔で立ち止まる。
「だからさー、何なわけソレ。かくれんぼ流行ってんの? さっきから会話遠いんだけど」
「だって……」
隣になんて並びづらい。
しーちゃんがふわりと髪を弾ませるたびに人波が乱れて、唇の形が変わるごとに四方八方から視線が飛んでくる気がするの。
「目立ちすぎだよ。落ち着かないもん」
往生際悪くそれでもまだ少し後ろにいると、しーちゃんは私が肩にかけているバッグの端を捕まえて、私ごと自分の場所まで引き寄せる。
「慣れてよ。とりあえずこの1年は我武者羅にやってみようって決めたからさ」
ガムシャラなんて言葉しーちゃんには似合わない。
自分のペースを守って、それでも周囲を認めさせて。楽しんでモデルの仕事をこなしてくんだとばかり思ってたのに。
「どーして急に?」
改めて隣を歩きながらそう聞いてみると、どこか憂いを帯びた表情をした。
「廃刊の危機なんだよね『REAL』」
「そうなの!?」
「上の命令で今期はとにかく部数さばけ! って事になったらしくてさ。まずは話題性で持ってくために、モデルが各々カオ売る作戦に出たわけ」
「大変なんだね。でもそれだけで雑誌が売れるの?」
「新規開拓、いわゆる『ジャケ買い』ってヤツ? それに合わせて内容も一時的にゆる〜くしてる感はあるけどね」
「あぁ……だから……」
車両一面を飾っていたカルペスの広告と、女子高生が抱えていた新刊の表紙がシンクロしてたのを思い出す。
REALにしては爽やかで安っぽい――イマドキなキャッチコピーが綴ってあった。
どっちかと言うとマニアックな、好きな人は見るよね! 的なメンズファッション誌のイメージが強かったから、砕けたそれらが「あれ?」って引っかかったんだ。
ブランド色が弱まったのは残念。でもTVで見かける男の子が出てる雑誌だからきっと、女の子達がお金を出して買うんだ。
「イメチェンって事なんだね。う〜ん、でもそれって何か……」
現場も知らないし出版物に思いを巡らせた事なんかもないけど、しーちゃんが真剣だから私も考え込んでしまう。
「言い方悪いけど、戦略があざといよね」
「ん?」
「だって根本的に売れるものを作るっていうのとは違うんでしょ? 本質で勝負がモットーのしーちゃんらしくない攻め方だと思うんだけど」
何の気なしに吐いた台詞に、しーちゃんがピクッと眉を動かして過剰に反応した。
あ、やばい。言い過ぎた?
不機嫌に目を背けられるのがイヤで咄嗟に服の裾を捕まえると、しーちゃんは私の前髪をクシャリと撫でて小さく笑う。
「もう、正攻法だけでいくのは止めたんだ。キレイに決めても欲しいものに手が届かなきゃ、結局意味ないって分かったからさ。色々とね」
清々しいほどはっきりした口調。言葉の真意は読み取れなかったけど、自分の意志で迷いなく進んでるんだって事は分かる。
なら、大丈夫だね、昔からそうだもの。傍からみたら無謀な事もしーちゃんがやると正解になるの。
理想を現実に変えるだけの努力を惜しみなくしてる人。
「応援……じゃなくて、私もちゃんと協力するからねっ。出来ることがあれば手伝わせて」
頑張ってるしーちゃんの役に少しでも立てればって思った。さっき蒼くんにも伝えたけど、自分の身を守れるくらいの稽古は今だって続けてる。
天力者として浄化を引き受けてもいいし、お父さんに直談判して守護のお役目を減らすようにお願いしてもいい。
前までは天力を宿すのもイヤでイヤで仕方なかくて逃げることばかり考えていたけど、前回の事件を切っ掛けに、ちょっとは自分の役割と立ち位置を理解した気がするの。
だから仕事の分担について話をするつもりだった。
「ふーん、言ったね? じゃあ早速」
でもしーちゃんは前を向いたまま私のバッグをさり気なく自分に肩掛けすると、フリーになった右手をすくうように握って歩き出す。
「え? なに?」
指を絡めるこんなつなぎ方はまるで恋人同士みたい。トロトロ歩く私に痺れをきらして、メンドウくさそうに手を引くのとはぜんぜん違う。
温もりが熱くて、優しいのに強くて。相手はしーちゃんなのに胸がトクンって鳴った。
指先から全身に緊張が走るからさっき以上に落ち着かない。
「しーちゃん、ちょっと待って。これ……」
反応に困って振りほどこうとしたら、「シッ」と小さくたしなめられる。
「リア充アピール付き合って」
「??」
しーちゃんが一瞥した斜め前方を同じようにチラリと伺うと、5、6人の女の子集団がこちらに一直線に近づいてくるのが見えた。
興奮気味に体を弾ませながら、手にはスマホと例の雑誌。
ファンに間違いないから「一緒に写真お願いします!」とかって取り囲もうとしてたのかもしれない。
でも私の存在を勘違いしたからかな? 彼女たちはプライベートな領域に足を踏み入れるのを躊躇って、いったん足を止めた。
その横をわざと気づかない素振りで私の手を引き、しーちゃんは悪びれもなく颯爽とスリ抜ける。
「……もお。ダシに使わないでよぉ」
さすがだなぁって感心しちゃうような鮮やかな交わし方だけど、無駄にドキドキさせられた私は何だか腑に落ちない。
高校の終わりに専属になった、メンズ誌『REAL(リアル)』。
テレビの影響力ってすごいなぁ。
20代男子向けの正統派ファッション誌を、女の子が堂々と持ち歩くことなんて今までならなかったのに。
「天海のヤツ、すっかり芸能人って感じだな。こんなに目立って大丈夫なのかよ」
蒼くんが心配そうに顔を歪める横で、私はただ静かに苦笑った。
憂えてるのはきっと私のガードのこと。祟峻(すいしゅん)の鏡を取り戻したことで『女性天子』の力は認められたものの、子孫を残す前に何かあったら……って、
お父さんの監視はより厳しいものになった。
私の行動を制御できなかったことでしーちゃんはいつも以上に叱られただろうし、守護の役目をますます重く言いつけられたのは想像できる。
でも反抗するみたいに仕事をバンバン入れて、この数か月しーちゃんが家に立ち寄る事はほとんどなかった。
もしかしたら息苦しい世界とワガママな私に、ついに愛想を尽かしちゃったのかもしれない。
「ひどいよね。ゴールデンウィーク前にちょこっと会いに来たきりなの。もう1週間以上も電話もないし」
思わずこぼしたそんな台詞を、私はどんなカオで口にしたんだろう。
蒼くんは微かに目を見開いた後すぐさま整った笑顔を見せて、何気なくこちらから視線を外した。
「改札に来てると思う」
「え?」
「昨夜別件で連絡入って、を迎えに来るって言ってたから」
駅ビルにダイレクトに続く自動改札機の前。行き交う人々のあらゆる想いを含んだ視線を集めて、しーちゃんは涼しい顔で私たちに向かって左手をあげた。
長い脚を引き立てるホワイトジーンズのパンツに、意外と筋肉質な上半身を浮き立たせるぴったりとした濃い色味のカットソー。
何でもないファッションがやけに目立つのは、醸し出すオーラにさらに磨きがかかったせいかもしれない。
(何か恥ずかしい。地元の駅で待ち合わせなんて最近なかったから)
しーちゃんの歩みと目線の先を追いかけて、周囲の注目がパラパラとこちらに移る。
焦った私は手を振り返すこともしないで、蒼くんの背中に隠れるようにゆっくりとSuicaをかざした。
「これと、これが来週の授業の課題だから。忘れずに出席しろよ」
「毎度の事ながらアリガトね。蒼がいてくれて本当助かる」
軽い挨拶を交わして分厚いプリントを受け渡す2人。私は輪には加わらず、一歩下がった所でそのやりとりを見ていた。
「忙しそうだな。大学にほとんど顔出してないみてーだけど、単位大丈夫なのか?」
蒼くんがぽつりと問いかけると、しーちゃんは「おかげさまで」なんて柔らかく口角を上げる。
「去年までに拾えるものは拾ったし、蒼みたいに教職とるわけじゃないからさ。前期はのんびり通おうかなーって」
「昨日も徹夜だったんじゃねーの? モデルってあんな時間まで働くのかよ」
「あぁ、深夜にLINEごめんね。違うよ、あれは本業の方。妖人(ようびと)の小さい浄化の依頼が入っちゃってさ」
「この多忙な状況で、そっちもかよ」
蒼くんはフゥと小さく息をつき「どんだけストイックなんだ」って突っ込んだ後、急に声のトーンを落としてボソリと呟く。
「悪いな、お前の負担を分散させる為の『契約』でもあったのに。こんな時に動けなくて」
もどかしそうな、悔しそうな横顔。
そんな気持ちを受け止めるようにしーちゃんはいったん口をつぐみ、少し間をおいてから蒼くんの肩をトンッと拳で突く。
「お互い様でしょ? 蒼がいてくれるから、僕も自由にやれるんだし」
そして蒼くんの陰にいた私にいきなり視線を投げ、前屈みになって顔を近づけた。
「で、何? はさっきから何で隠れてるわけ?」
「! べ、別に隠れてなんか……」
眼鏡越しに見つめられるのは苦手。
しどろもどろになって目を逸らすと、つれない態度にカチンときたのか、しーちゃんは私の腕を掴んで強引に前へと引きずり出す。
「ほら、そろそろ時間だよ。蒼も僕も多忙なんだからさ、早く何か言いなって」
「え? え? 何よ急に……」
体をクルッと回転させられて押さえつけられたまま、蒼くんの正面へと突き出される。
見上げると彼はちょっと切ないカオを返して、「悪い」なんてまた謝ったの。
(だから……それはどんな意味なのよ……)
『蒼をこの世界にあんま縛り付けないであげたら?』
昔しーちゃんに釘を刺されたことが脳裏をよぎった。
彼にとって天力者であることは義務じゃない。負担に思われるのだけは辛くて、私は思わず声を張り上げる。
「蒼くんはいいの! 無理しない範囲で一緒にいてくれれば、それで嬉しいんだから!」
「……」
「私はあれから稽古も続けてるし、自分の事は自分で守れるようにするよ。蒼くんが動けない分、代わりに仕事をこなしたって平気なんだから」
助かるよって肩の力を抜いて欲しかったのに、私の言葉を聞いた蒼くんはますます険しい表情になった。
「……それじゃあ意味ねーだろ」
「え?」
「いや、うん。サンキュー。また月曜な」
蒼くんと駅で別れた後、当たり前だけどしーちゃんと2人きりになった。
日の当たる時間帯に並んで帰宅するのはずいぶん久しぶりのこと。他愛もないお喋りさえちょっとくすぐったくて、私は少し距離をとって歩く。
「ねー。寄り道して……※※とか買ってく?」
「ん? なに? 何か買うの?」
すれ違う人達の話し声と車の音が邪魔をして、ここまででもう3回も聞き返してしまった。
活気あるアーケード商店街の入り口に差しかかったところで、しーちゃんはさすがにうんざりした顔で立ち止まる。
「だからさー、何なわけソレ。かくれんぼ流行ってんの? さっきから会話遠いんだけど」
「だって……」
隣になんて並びづらい。
しーちゃんがふわりと髪を弾ませるたびに人波が乱れて、唇の形が変わるごとに四方八方から視線が飛んでくる気がするの。
「目立ちすぎだよ。落ち着かないもん」
往生際悪くそれでもまだ少し後ろにいると、しーちゃんは私が肩にかけているバッグの端を捕まえて、私ごと自分の場所まで引き寄せる。
「慣れてよ。とりあえずこの1年は我武者羅にやってみようって決めたからさ」
ガムシャラなんて言葉しーちゃんには似合わない。
自分のペースを守って、それでも周囲を認めさせて。楽しんでモデルの仕事をこなしてくんだとばかり思ってたのに。
「どーして急に?」
改めて隣を歩きながらそう聞いてみると、どこか憂いを帯びた表情をした。
「廃刊の危機なんだよね『REAL』」
「そうなの!?」
「上の命令で今期はとにかく部数さばけ! って事になったらしくてさ。まずは話題性で持ってくために、モデルが各々カオ売る作戦に出たわけ」
「大変なんだね。でもそれだけで雑誌が売れるの?」
「新規開拓、いわゆる『ジャケ買い』ってヤツ? それに合わせて内容も一時的にゆる〜くしてる感はあるけどね」
「あぁ……だから……」
車両一面を飾っていたカルペスの広告と、女子高生が抱えていた新刊の表紙がシンクロしてたのを思い出す。
REALにしては爽やかで安っぽい――イマドキなキャッチコピーが綴ってあった。
どっちかと言うとマニアックな、好きな人は見るよね! 的なメンズファッション誌のイメージが強かったから、砕けたそれらが「あれ?」って引っかかったんだ。
ブランド色が弱まったのは残念。でもTVで見かける男の子が出てる雑誌だからきっと、女の子達がお金を出して買うんだ。
「イメチェンって事なんだね。う〜ん、でもそれって何か……」
現場も知らないし出版物に思いを巡らせた事なんかもないけど、しーちゃんが真剣だから私も考え込んでしまう。
「言い方悪いけど、戦略があざといよね」
「ん?」
「だって根本的に売れるものを作るっていうのとは違うんでしょ? 本質で勝負がモットーのしーちゃんらしくない攻め方だと思うんだけど」
何の気なしに吐いた台詞に、しーちゃんがピクッと眉を動かして過剰に反応した。
あ、やばい。言い過ぎた?
不機嫌に目を背けられるのがイヤで咄嗟に服の裾を捕まえると、しーちゃんは私の前髪をクシャリと撫でて小さく笑う。
「もう、正攻法だけでいくのは止めたんだ。キレイに決めても欲しいものに手が届かなきゃ、結局意味ないって分かったからさ。色々とね」
清々しいほどはっきりした口調。言葉の真意は読み取れなかったけど、自分の意志で迷いなく進んでるんだって事は分かる。
なら、大丈夫だね、昔からそうだもの。傍からみたら無謀な事もしーちゃんがやると正解になるの。
理想を現実に変えるだけの努力を惜しみなくしてる人。
「応援……じゃなくて、私もちゃんと協力するからねっ。出来ることがあれば手伝わせて」
頑張ってるしーちゃんの役に少しでも立てればって思った。さっき蒼くんにも伝えたけど、自分の身を守れるくらいの稽古は今だって続けてる。
天力者として浄化を引き受けてもいいし、お父さんに直談判して守護のお役目を減らすようにお願いしてもいい。
前までは天力を宿すのもイヤでイヤで仕方なかくて逃げることばかり考えていたけど、前回の事件を切っ掛けに、ちょっとは自分の役割と立ち位置を理解した気がするの。
だから仕事の分担について話をするつもりだった。
「ふーん、言ったね? じゃあ早速」
でもしーちゃんは前を向いたまま私のバッグをさり気なく自分に肩掛けすると、フリーになった右手をすくうように握って歩き出す。
「え? なに?」
指を絡めるこんなつなぎ方はまるで恋人同士みたい。トロトロ歩く私に痺れをきらして、メンドウくさそうに手を引くのとはぜんぜん違う。
温もりが熱くて、優しいのに強くて。相手はしーちゃんなのに胸がトクンって鳴った。
指先から全身に緊張が走るからさっき以上に落ち着かない。
「しーちゃん、ちょっと待って。これ……」
反応に困って振りほどこうとしたら、「シッ」と小さくたしなめられる。
「リア充アピール付き合って」
「??」
しーちゃんが一瞥した斜め前方を同じようにチラリと伺うと、5、6人の女の子集団がこちらに一直線に近づいてくるのが見えた。
興奮気味に体を弾ませながら、手にはスマホと例の雑誌。
ファンに間違いないから「一緒に写真お願いします!」とかって取り囲もうとしてたのかもしれない。
でも私の存在を勘違いしたからかな? 彼女たちはプライベートな領域に足を踏み入れるのを躊躇って、いったん足を止めた。
その横をわざと気づかない素振りで私の手を引き、しーちゃんは悪びれもなく颯爽とスリ抜ける。
「……もお。ダシに使わないでよぉ」
さすがだなぁって感心しちゃうような鮮やかな交わし方だけど、無駄にドキドキさせられた私は何だか腑に落ちない。
 バス通りに到着するとしーちゃんはやっと歩くスピードを緩め「まあ、機嫌なおしてよ」って、空いているもう一方の手でなだめるように頭を撫でた。
「の為に早く帰宅したかったんだからさ。お土産があるんだよ」
お洋服? アクセ? それともクッキーやマカロンかな?
含みのある言葉尻が引っかかって答えを催促してみたけれど、ただ悪戯っぽい笑みを返して、またちょっと繋いだ手に力をこめる。
バス通りに到着するとしーちゃんはやっと歩くスピードを緩め「まあ、機嫌なおしてよ」って、空いているもう一方の手でなだめるように頭を撫でた。
「の為に早く帰宅したかったんだからさ。お土産があるんだよ」
お洋服? アクセ? それともクッキーやマカロンかな?
含みのある言葉尻が引っかかって答えを催促してみたけれど、ただ悪戯っぽい笑みを返して、またちょっと繋いだ手に力をこめる。
 西日が反射するオレンジ色の道。
キラキラしすぎて目が眩むから、私はその手を離せずにいたんだ。
西日が反射するオレンジ色の道。
キラキラしすぎて目が眩むから、私はその手を離せずにいたんだ。
<<前へ 2話へ>>
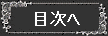
 「スゲーな、これ」
車内をグルリと眺めながら、蒼くんは驚いたように小さく呟く。
私の知る限りここまで2本のCMに出てるしーちゃん。スポーツドリンクを爽やかに飲みながらダンスする姿を、初めてテレビで見かけたのは2月頃だった。
たしかにインパクトはあったけど数人の内の1人って感じだったのに、それからたった数か月、今朝から流れたシリーズ第2弾はしーちゃんメインの内容だった。
注目のイケメン――そんな見出しの記事がネットサーフィン中に幾度となく引っかかり、そのたびに私は何とも言いようのない気持ちでスマホを閉じてしまう。
ふと横を向くと、2人の女子高生が黄色い声をあげながら、車内広告をスマホで撮影してるのが目に入った。
必死で腕を伸ばしてシャッター音を響かせては一喜一憂し、あーだこーだって目を輝かせて語っているのがすごく初々しくて可愛い。
ファンなのかな?
チラリと覗き込めば、大事そうに左手で抱えているのもしーちゃんが表紙の雑誌だった。
「スゲーな、これ」
車内をグルリと眺めながら、蒼くんは驚いたように小さく呟く。
私の知る限りここまで2本のCMに出てるしーちゃん。スポーツドリンクを爽やかに飲みながらダンスする姿を、初めてテレビで見かけたのは2月頃だった。
たしかにインパクトはあったけど数人の内の1人って感じだったのに、それからたった数か月、今朝から流れたシリーズ第2弾はしーちゃんメインの内容だった。
注目のイケメン――そんな見出しの記事がネットサーフィン中に幾度となく引っかかり、そのたびに私は何とも言いようのない気持ちでスマホを閉じてしまう。
ふと横を向くと、2人の女子高生が黄色い声をあげながら、車内広告をスマホで撮影してるのが目に入った。
必死で腕を伸ばしてシャッター音を響かせては一喜一憂し、あーだこーだって目を輝かせて語っているのがすごく初々しくて可愛い。
ファンなのかな?
チラリと覗き込めば、大事そうに左手で抱えているのもしーちゃんが表紙の雑誌だった。
 高校の終わりに専属になった、メンズ誌『REAL(リアル)』。
テレビの影響力ってすごいなぁ。
20代男子向けの正統派ファッション誌を、女の子が堂々と持ち歩くことなんて今までならなかったのに。
「天海のヤツ、すっかり芸能人って感じだな。こんなに目立って大丈夫なのかよ」
蒼くんが心配そうに顔を歪める横で、私はただ静かに苦笑った。
憂えてるのはきっと私のガードのこと。祟峻(すいしゅん)の鏡を取り戻したことで『女性天子』の力は認められたものの、子孫を残す前に何かあったら……って、
お父さんの監視はより厳しいものになった。
私の行動を制御できなかったことでしーちゃんはいつも以上に叱られただろうし、守護の役目をますます重く言いつけられたのは想像できる。
でも反抗するみたいに仕事をバンバン入れて、この数か月しーちゃんが家に立ち寄る事はほとんどなかった。
もしかしたら息苦しい世界とワガママな私に、ついに愛想を尽かしちゃったのかもしれない。
「ひどいよね。ゴールデンウィーク前にちょこっと会いに来たきりなの。もう1週間以上も電話もないし」
思わずこぼしたそんな台詞を、私はどんなカオで口にしたんだろう。
蒼くんは微かに目を見開いた後すぐさま整った笑顔を見せて、何気なくこちらから視線を外した。
「改札に来てると思う」
「え?」
「昨夜別件で連絡入って、を迎えに来るって言ってたから」
駅ビルにダイレクトに続く自動改札機の前。行き交う人々のあらゆる想いを含んだ視線を集めて、しーちゃんは涼しい顔で私たちに向かって左手をあげた。
長い脚を引き立てるホワイトジーンズのパンツに、意外と筋肉質な上半身を浮き立たせるぴったりとした濃い色味のカットソー。
何でもないファッションがやけに目立つのは、醸し出すオーラにさらに磨きがかかったせいかもしれない。
(何か恥ずかしい。地元の駅で待ち合わせなんて最近なかったから)
しーちゃんの歩みと目線の先を追いかけて、周囲の注目がパラパラとこちらに移る。
焦った私は手を振り返すこともしないで、蒼くんの背中に隠れるようにゆっくりとSuicaをかざした。
「これと、これが来週の授業の課題だから。忘れずに出席しろよ」
「毎度の事ながらアリガトね。蒼がいてくれて本当助かる」
軽い挨拶を交わして分厚いプリントを受け渡す2人。私は輪には加わらず、一歩下がった所でそのやりとりを見ていた。
「忙しそうだな。大学にほとんど顔出してないみてーだけど、単位大丈夫なのか?」
蒼くんがぽつりと問いかけると、しーちゃんは「おかげさまで」なんて柔らかく口角を上げる。
「去年までに拾えるものは拾ったし、蒼みたいに教職とるわけじゃないからさ。前期はのんびり通おうかなーって」
「昨日も徹夜だったんじゃねーの? モデルってあんな時間まで働くのかよ」
「あぁ、深夜にLINEごめんね。違うよ、あれは本業の方。妖人(ようびと)の小さい浄化の依頼が入っちゃってさ」
「この多忙な状況で、そっちもかよ」
蒼くんはフゥと小さく息をつき「どんだけストイックなんだ」って突っ込んだ後、急に声のトーンを落としてボソリと呟く。
「悪いな、お前の負担を分散させる為の『契約』でもあったのに。こんな時に動けなくて」
もどかしそうな、悔しそうな横顔。
そんな気持ちを受け止めるようにしーちゃんはいったん口をつぐみ、少し間をおいてから蒼くんの肩をトンッと拳で突く。
「お互い様でしょ? 蒼がいてくれるから、僕も自由にやれるんだし」
そして蒼くんの陰にいた私にいきなり視線を投げ、前屈みになって顔を近づけた。
「で、何? はさっきから何で隠れてるわけ?」
「! べ、別に隠れてなんか……」
眼鏡越しに見つめられるのは苦手。
しどろもどろになって目を逸らすと、つれない態度にカチンときたのか、しーちゃんは私の腕を掴んで強引に前へと引きずり出す。
「ほら、そろそろ時間だよ。蒼も僕も多忙なんだからさ、早く何か言いなって」
「え? え? 何よ急に……」
体をクルッと回転させられて押さえつけられたまま、蒼くんの正面へと突き出される。
見上げると彼はちょっと切ないカオを返して、「悪い」なんてまた謝ったの。
(だから……それはどんな意味なのよ……)
『蒼をこの世界にあんま縛り付けないであげたら?』
昔しーちゃんに釘を刺されたことが脳裏をよぎった。
彼にとって天力者であることは義務じゃない。負担に思われるのだけは辛くて、私は思わず声を張り上げる。
「蒼くんはいいの! 無理しない範囲で一緒にいてくれれば、それで嬉しいんだから!」
「……」
「私はあれから稽古も続けてるし、自分の事は自分で守れるようにするよ。蒼くんが動けない分、代わりに仕事をこなしたって平気なんだから」
助かるよって肩の力を抜いて欲しかったのに、私の言葉を聞いた蒼くんはますます険しい表情になった。
「……それじゃあ意味ねーだろ」
「え?」
「いや、うん。サンキュー。また月曜な」
蒼くんと駅で別れた後、当たり前だけどしーちゃんと2人きりになった。
日の当たる時間帯に並んで帰宅するのはずいぶん久しぶりのこと。他愛もないお喋りさえちょっとくすぐったくて、私は少し距離をとって歩く。
「ねー。寄り道して……※※とか買ってく?」
「ん? なに? 何か買うの?」
すれ違う人達の話し声と車の音が邪魔をして、ここまででもう3回も聞き返してしまった。
活気あるアーケード商店街の入り口に差しかかったところで、しーちゃんはさすがにうんざりした顔で立ち止まる。
「だからさー、何なわけソレ。かくれんぼ流行ってんの? さっきから会話遠いんだけど」
「だって……」
隣になんて並びづらい。
しーちゃんがふわりと髪を弾ませるたびに人波が乱れて、唇の形が変わるごとに四方八方から視線が飛んでくる気がするの。
「目立ちすぎだよ。落ち着かないもん」
往生際悪くそれでもまだ少し後ろにいると、しーちゃんは私が肩にかけているバッグの端を捕まえて、私ごと自分の場所まで引き寄せる。
「慣れてよ。とりあえずこの1年は我武者羅にやってみようって決めたからさ」
ガムシャラなんて言葉しーちゃんには似合わない。
自分のペースを守って、それでも周囲を認めさせて。楽しんでモデルの仕事をこなしてくんだとばかり思ってたのに。
「どーして急に?」
改めて隣を歩きながらそう聞いてみると、どこか憂いを帯びた表情をした。
「廃刊の危機なんだよね『REAL』」
「そうなの!?」
「上の命令で今期はとにかく部数さばけ! って事になったらしくてさ。まずは話題性で持ってくために、モデルが各々カオ売る作戦に出たわけ」
「大変なんだね。でもそれだけで雑誌が売れるの?」
「新規開拓、いわゆる『ジャケ買い』ってヤツ? それに合わせて内容も一時的にゆる〜くしてる感はあるけどね」
「あぁ……だから……」
車両一面を飾っていたカルペスの広告と、女子高生が抱えていた新刊の表紙がシンクロしてたのを思い出す。
REALにしては爽やかで安っぽい――イマドキなキャッチコピーが綴ってあった。
どっちかと言うとマニアックな、好きな人は見るよね! 的なメンズファッション誌のイメージが強かったから、砕けたそれらが「あれ?」って引っかかったんだ。
ブランド色が弱まったのは残念。でもTVで見かける男の子が出てる雑誌だからきっと、女の子達がお金を出して買うんだ。
「イメチェンって事なんだね。う〜ん、でもそれって何か……」
現場も知らないし出版物に思いを巡らせた事なんかもないけど、しーちゃんが真剣だから私も考え込んでしまう。
「言い方悪いけど、戦略があざといよね」
「ん?」
「だって根本的に売れるものを作るっていうのとは違うんでしょ? 本質で勝負がモットーのしーちゃんらしくない攻め方だと思うんだけど」
何の気なしに吐いた台詞に、しーちゃんがピクッと眉を動かして過剰に反応した。
あ、やばい。言い過ぎた?
不機嫌に目を背けられるのがイヤで咄嗟に服の裾を捕まえると、しーちゃんは私の前髪をクシャリと撫でて小さく笑う。
「もう、正攻法だけでいくのは止めたんだ。キレイに決めても欲しいものに手が届かなきゃ、結局意味ないって分かったからさ。色々とね」
清々しいほどはっきりした口調。言葉の真意は読み取れなかったけど、自分の意志で迷いなく進んでるんだって事は分かる。
なら、大丈夫だね、昔からそうだもの。傍からみたら無謀な事もしーちゃんがやると正解になるの。
理想を現実に変えるだけの努力を惜しみなくしてる人。
「応援……じゃなくて、私もちゃんと協力するからねっ。出来ることがあれば手伝わせて」
頑張ってるしーちゃんの役に少しでも立てればって思った。さっき蒼くんにも伝えたけど、自分の身を守れるくらいの稽古は今だって続けてる。
天力者として浄化を引き受けてもいいし、お父さんに直談判して守護のお役目を減らすようにお願いしてもいい。
前までは天力を宿すのもイヤでイヤで仕方なかくて逃げることばかり考えていたけど、前回の事件を切っ掛けに、ちょっとは自分の役割と立ち位置を理解した気がするの。
だから仕事の分担について話をするつもりだった。
「ふーん、言ったね? じゃあ早速」
でもしーちゃんは前を向いたまま私のバッグをさり気なく自分に肩掛けすると、フリーになった右手をすくうように握って歩き出す。
「え? なに?」
指を絡めるこんなつなぎ方はまるで恋人同士みたい。トロトロ歩く私に痺れをきらして、メンドウくさそうに手を引くのとはぜんぜん違う。
温もりが熱くて、優しいのに強くて。相手はしーちゃんなのに胸がトクンって鳴った。
指先から全身に緊張が走るからさっき以上に落ち着かない。
「しーちゃん、ちょっと待って。これ……」
反応に困って振りほどこうとしたら、「シッ」と小さくたしなめられる。
「リア充アピール付き合って」
「??」
しーちゃんが一瞥した斜め前方を同じようにチラリと伺うと、5、6人の女の子集団がこちらに一直線に近づいてくるのが見えた。
興奮気味に体を弾ませながら、手にはスマホと例の雑誌。
ファンに間違いないから「一緒に写真お願いします!」とかって取り囲もうとしてたのかもしれない。
でも私の存在を勘違いしたからかな? 彼女たちはプライベートな領域に足を踏み入れるのを躊躇って、いったん足を止めた。
その横をわざと気づかない素振りで私の手を引き、しーちゃんは悪びれもなく颯爽とスリ抜ける。
「……もお。ダシに使わないでよぉ」
さすがだなぁって感心しちゃうような鮮やかな交わし方だけど、無駄にドキドキさせられた私は何だか腑に落ちない。
高校の終わりに専属になった、メンズ誌『REAL(リアル)』。
テレビの影響力ってすごいなぁ。
20代男子向けの正統派ファッション誌を、女の子が堂々と持ち歩くことなんて今までならなかったのに。
「天海のヤツ、すっかり芸能人って感じだな。こんなに目立って大丈夫なのかよ」
蒼くんが心配そうに顔を歪める横で、私はただ静かに苦笑った。
憂えてるのはきっと私のガードのこと。祟峻(すいしゅん)の鏡を取り戻したことで『女性天子』の力は認められたものの、子孫を残す前に何かあったら……って、
お父さんの監視はより厳しいものになった。
私の行動を制御できなかったことでしーちゃんはいつも以上に叱られただろうし、守護の役目をますます重く言いつけられたのは想像できる。
でも反抗するみたいに仕事をバンバン入れて、この数か月しーちゃんが家に立ち寄る事はほとんどなかった。
もしかしたら息苦しい世界とワガママな私に、ついに愛想を尽かしちゃったのかもしれない。
「ひどいよね。ゴールデンウィーク前にちょこっと会いに来たきりなの。もう1週間以上も電話もないし」
思わずこぼしたそんな台詞を、私はどんなカオで口にしたんだろう。
蒼くんは微かに目を見開いた後すぐさま整った笑顔を見せて、何気なくこちらから視線を外した。
「改札に来てると思う」
「え?」
「昨夜別件で連絡入って、を迎えに来るって言ってたから」
駅ビルにダイレクトに続く自動改札機の前。行き交う人々のあらゆる想いを含んだ視線を集めて、しーちゃんは涼しい顔で私たちに向かって左手をあげた。
長い脚を引き立てるホワイトジーンズのパンツに、意外と筋肉質な上半身を浮き立たせるぴったりとした濃い色味のカットソー。
何でもないファッションがやけに目立つのは、醸し出すオーラにさらに磨きがかかったせいかもしれない。
(何か恥ずかしい。地元の駅で待ち合わせなんて最近なかったから)
しーちゃんの歩みと目線の先を追いかけて、周囲の注目がパラパラとこちらに移る。
焦った私は手を振り返すこともしないで、蒼くんの背中に隠れるようにゆっくりとSuicaをかざした。
「これと、これが来週の授業の課題だから。忘れずに出席しろよ」
「毎度の事ながらアリガトね。蒼がいてくれて本当助かる」
軽い挨拶を交わして分厚いプリントを受け渡す2人。私は輪には加わらず、一歩下がった所でそのやりとりを見ていた。
「忙しそうだな。大学にほとんど顔出してないみてーだけど、単位大丈夫なのか?」
蒼くんがぽつりと問いかけると、しーちゃんは「おかげさまで」なんて柔らかく口角を上げる。
「去年までに拾えるものは拾ったし、蒼みたいに教職とるわけじゃないからさ。前期はのんびり通おうかなーって」
「昨日も徹夜だったんじゃねーの? モデルってあんな時間まで働くのかよ」
「あぁ、深夜にLINEごめんね。違うよ、あれは本業の方。妖人(ようびと)の小さい浄化の依頼が入っちゃってさ」
「この多忙な状況で、そっちもかよ」
蒼くんはフゥと小さく息をつき「どんだけストイックなんだ」って突っ込んだ後、急に声のトーンを落としてボソリと呟く。
「悪いな、お前の負担を分散させる為の『契約』でもあったのに。こんな時に動けなくて」
もどかしそうな、悔しそうな横顔。
そんな気持ちを受け止めるようにしーちゃんはいったん口をつぐみ、少し間をおいてから蒼くんの肩をトンッと拳で突く。
「お互い様でしょ? 蒼がいてくれるから、僕も自由にやれるんだし」
そして蒼くんの陰にいた私にいきなり視線を投げ、前屈みになって顔を近づけた。
「で、何? はさっきから何で隠れてるわけ?」
「! べ、別に隠れてなんか……」
眼鏡越しに見つめられるのは苦手。
しどろもどろになって目を逸らすと、つれない態度にカチンときたのか、しーちゃんは私の腕を掴んで強引に前へと引きずり出す。
「ほら、そろそろ時間だよ。蒼も僕も多忙なんだからさ、早く何か言いなって」
「え? え? 何よ急に……」
体をクルッと回転させられて押さえつけられたまま、蒼くんの正面へと突き出される。
見上げると彼はちょっと切ないカオを返して、「悪い」なんてまた謝ったの。
(だから……それはどんな意味なのよ……)
『蒼をこの世界にあんま縛り付けないであげたら?』
昔しーちゃんに釘を刺されたことが脳裏をよぎった。
彼にとって天力者であることは義務じゃない。負担に思われるのだけは辛くて、私は思わず声を張り上げる。
「蒼くんはいいの! 無理しない範囲で一緒にいてくれれば、それで嬉しいんだから!」
「……」
「私はあれから稽古も続けてるし、自分の事は自分で守れるようにするよ。蒼くんが動けない分、代わりに仕事をこなしたって平気なんだから」
助かるよって肩の力を抜いて欲しかったのに、私の言葉を聞いた蒼くんはますます険しい表情になった。
「……それじゃあ意味ねーだろ」
「え?」
「いや、うん。サンキュー。また月曜な」
蒼くんと駅で別れた後、当たり前だけどしーちゃんと2人きりになった。
日の当たる時間帯に並んで帰宅するのはずいぶん久しぶりのこと。他愛もないお喋りさえちょっとくすぐったくて、私は少し距離をとって歩く。
「ねー。寄り道して……※※とか買ってく?」
「ん? なに? 何か買うの?」
すれ違う人達の話し声と車の音が邪魔をして、ここまででもう3回も聞き返してしまった。
活気あるアーケード商店街の入り口に差しかかったところで、しーちゃんはさすがにうんざりした顔で立ち止まる。
「だからさー、何なわけソレ。かくれんぼ流行ってんの? さっきから会話遠いんだけど」
「だって……」
隣になんて並びづらい。
しーちゃんがふわりと髪を弾ませるたびに人波が乱れて、唇の形が変わるごとに四方八方から視線が飛んでくる気がするの。
「目立ちすぎだよ。落ち着かないもん」
往生際悪くそれでもまだ少し後ろにいると、しーちゃんは私が肩にかけているバッグの端を捕まえて、私ごと自分の場所まで引き寄せる。
「慣れてよ。とりあえずこの1年は我武者羅にやってみようって決めたからさ」
ガムシャラなんて言葉しーちゃんには似合わない。
自分のペースを守って、それでも周囲を認めさせて。楽しんでモデルの仕事をこなしてくんだとばかり思ってたのに。
「どーして急に?」
改めて隣を歩きながらそう聞いてみると、どこか憂いを帯びた表情をした。
「廃刊の危機なんだよね『REAL』」
「そうなの!?」
「上の命令で今期はとにかく部数さばけ! って事になったらしくてさ。まずは話題性で持ってくために、モデルが各々カオ売る作戦に出たわけ」
「大変なんだね。でもそれだけで雑誌が売れるの?」
「新規開拓、いわゆる『ジャケ買い』ってヤツ? それに合わせて内容も一時的にゆる〜くしてる感はあるけどね」
「あぁ……だから……」
車両一面を飾っていたカルペスの広告と、女子高生が抱えていた新刊の表紙がシンクロしてたのを思い出す。
REALにしては爽やかで安っぽい――イマドキなキャッチコピーが綴ってあった。
どっちかと言うとマニアックな、好きな人は見るよね! 的なメンズファッション誌のイメージが強かったから、砕けたそれらが「あれ?」って引っかかったんだ。
ブランド色が弱まったのは残念。でもTVで見かける男の子が出てる雑誌だからきっと、女の子達がお金を出して買うんだ。
「イメチェンって事なんだね。う〜ん、でもそれって何か……」
現場も知らないし出版物に思いを巡らせた事なんかもないけど、しーちゃんが真剣だから私も考え込んでしまう。
「言い方悪いけど、戦略があざといよね」
「ん?」
「だって根本的に売れるものを作るっていうのとは違うんでしょ? 本質で勝負がモットーのしーちゃんらしくない攻め方だと思うんだけど」
何の気なしに吐いた台詞に、しーちゃんがピクッと眉を動かして過剰に反応した。
あ、やばい。言い過ぎた?
不機嫌に目を背けられるのがイヤで咄嗟に服の裾を捕まえると、しーちゃんは私の前髪をクシャリと撫でて小さく笑う。
「もう、正攻法だけでいくのは止めたんだ。キレイに決めても欲しいものに手が届かなきゃ、結局意味ないって分かったからさ。色々とね」
清々しいほどはっきりした口調。言葉の真意は読み取れなかったけど、自分の意志で迷いなく進んでるんだって事は分かる。
なら、大丈夫だね、昔からそうだもの。傍からみたら無謀な事もしーちゃんがやると正解になるの。
理想を現実に変えるだけの努力を惜しみなくしてる人。
「応援……じゃなくて、私もちゃんと協力するからねっ。出来ることがあれば手伝わせて」
頑張ってるしーちゃんの役に少しでも立てればって思った。さっき蒼くんにも伝えたけど、自分の身を守れるくらいの稽古は今だって続けてる。
天力者として浄化を引き受けてもいいし、お父さんに直談判して守護のお役目を減らすようにお願いしてもいい。
前までは天力を宿すのもイヤでイヤで仕方なかくて逃げることばかり考えていたけど、前回の事件を切っ掛けに、ちょっとは自分の役割と立ち位置を理解した気がするの。
だから仕事の分担について話をするつもりだった。
「ふーん、言ったね? じゃあ早速」
でもしーちゃんは前を向いたまま私のバッグをさり気なく自分に肩掛けすると、フリーになった右手をすくうように握って歩き出す。
「え? なに?」
指を絡めるこんなつなぎ方はまるで恋人同士みたい。トロトロ歩く私に痺れをきらして、メンドウくさそうに手を引くのとはぜんぜん違う。
温もりが熱くて、優しいのに強くて。相手はしーちゃんなのに胸がトクンって鳴った。
指先から全身に緊張が走るからさっき以上に落ち着かない。
「しーちゃん、ちょっと待って。これ……」
反応に困って振りほどこうとしたら、「シッ」と小さくたしなめられる。
「リア充アピール付き合って」
「??」
しーちゃんが一瞥した斜め前方を同じようにチラリと伺うと、5、6人の女の子集団がこちらに一直線に近づいてくるのが見えた。
興奮気味に体を弾ませながら、手にはスマホと例の雑誌。
ファンに間違いないから「一緒に写真お願いします!」とかって取り囲もうとしてたのかもしれない。
でも私の存在を勘違いしたからかな? 彼女たちはプライベートな領域に足を踏み入れるのを躊躇って、いったん足を止めた。
その横をわざと気づかない素振りで私の手を引き、しーちゃんは悪びれもなく颯爽とスリ抜ける。
「……もお。ダシに使わないでよぉ」
さすがだなぁって感心しちゃうような鮮やかな交わし方だけど、無駄にドキドキさせられた私は何だか腑に落ちない。
 バス通りに到着するとしーちゃんはやっと歩くスピードを緩め「まあ、機嫌なおしてよ」って、空いているもう一方の手でなだめるように頭を撫でた。
「の為に早く帰宅したかったんだからさ。お土産があるんだよ」
お洋服? アクセ? それともクッキーやマカロンかな?
含みのある言葉尻が引っかかって答えを催促してみたけれど、ただ悪戯っぽい笑みを返して、またちょっと繋いだ手に力をこめる。
バス通りに到着するとしーちゃんはやっと歩くスピードを緩め「まあ、機嫌なおしてよ」って、空いているもう一方の手でなだめるように頭を撫でた。
「の為に早く帰宅したかったんだからさ。お土産があるんだよ」
お洋服? アクセ? それともクッキーやマカロンかな?
含みのある言葉尻が引っかかって答えを催促してみたけれど、ただ悪戯っぽい笑みを返して、またちょっと繋いだ手に力をこめる。
 西日が反射するオレンジ色の道。
キラキラしすぎて目が眩むから、私はその手を離せずにいたんだ。
西日が反射するオレンジ色の道。
キラキラしすぎて目が眩むから、私はその手を離せずにいたんだ。