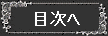◆ 2.月下のプロポーズ
「芹七さんお帰りなさい」
宮家の裏玄関から帰宅した私としーちゃんを迎えてくれたのは、お母さんの優しい笑顔だった。
着けていたエプロンを華奢な肩から脱ぎとり、クルんと巻いた髪を弾ませながら歩み寄ってきてくれる。
数か月ぶりの再会。
しーちゃんが言ってた『お土産』の意味が分かって、嬉しくて切なくて思わず子供みたいに飛びついてしまった。
「いつ来たの? 何で電話くれなかったの?」
「ほらほら、はしたないわよ。まずは帰宅の挨拶が先でしょう」
「あ、うん。お母さんお帰りなさい!」
「ただいま。もうこれじゃ、どちらがどちらだか分からないわね」
ふふふと品よく声を出して笑って、ちょっとだけ背の高い私を愛おしそうに見上げる。
クリスマスの蒼くんとのお泊りを容認してくれたことでお父さんの怒りをかい、鎌倉のお祖母ちゃんの家に強制帰宅させられてしまっていたお母さん。
ごめんなさいは何度も電話で伝えたけど、こうやって直に話ができるのは久しぶり。
ああ! とにかくやっと帰ってきてくれた。ちゃんと謝って説明しなきゃ。
「あのねっ……」
急かされるように口を開くと、お母さんは「もういいのよ」というように私の唇に自分の人差し指をそっと当てる。
「2人とも、まずは手洗いうがいをしていらっしゃいな。少し早いけど夕食にしましょう。紫己さんはビールで良いかしら?」
「いえ、僕はここで……今夜は久しぶりの家族団らんですし」
「そんなこと言わないでお夕飯くらい済ませていきなさい。美味しいシラスも持ち帰ってきたのよ」
お母さんはしっとりとした声音で強制参加を促し、そのまま台所に消えてしまう。
しーちゃんと私は言葉なく目を合わせ静かに苦笑した。
「おば様は変わらず元気そうだね。安心した」
「うん。今日はお父さんも外泊みたいだし、いいタイミングで帰ってこれたのかも」
そして私は張りつめていた糸が切れたみたいに、並んでいたしーちゃんの腕に頬を撫でつけてしがみついた。
「ありがとう。お母さんを迎えに行ってくれたんでしょ?」
許可が出ていたにも関わらず、厳格な主人を恐れてか諦めてか。戻る切っ掛けをつかめなかったらしいお母さん。
それが分かっていながらも、手を差し伸べずに放っておいたお父さん。
しーちゃんが間に入って強引に連れ帰ってくれたことで、大義名分が立ったのだと思う。
「おば様の玉子焼きが食べたくて、セリに禁断症状が出てる〜なんてさ。珍しく八純に頼まれたからね」
茶目っ気たっぷりにそう返すしーちゃんだけど、大学とスタジオをギリギリで行き来する中で鎌倉まで車を飛ばすことはきっと簡単じゃなかったはず。
ちゃんと寝れてるのかな? 栄養のあるご飯は食べれてるのかな?
今まで申し訳ないくらいしーちゃんの身体に無関心だったけど、薄手のカットソー越しに感じるしーちゃんの腕が初夏だというのにやけに冷んやりしていて……。
心配になって、絡みついたまま無言で視線だけを上げた。
それを『要求』ととったのか、しーちゃんはポンポンと私の頭を撫でて口角を上げる。
「分かってるよ。せっかくだし素直にご馳走になってく。大丈夫だよ。おば様の誘いを無下に断って、がっかりさせるような真似はしないって」
「え? ちがっ。そんなの別に」
「それにいい機会だから、ちゃんと挨拶もしておきたいしね」
「何? 改まって……」
戸惑って口ごもる私を穏やかに見つめた後、しーちゃんはスルリと体を離し「今夜は飲むかな!」と、どこか割り切ったカオで天井に向かって伸びをした。
うなじで跳ねる栗色の髪がふわりと弾むのを、私は何だか腑に落ちない気分で見送る。
光の間の座卓にはすでにいくつかの小鉢料理と、瓶ビールが数本並べられていた。
しーちゃんが襖近くの席にあぐらをかくと、お母さんは満足そうに向かいの席に膝を折る。
「さあ、とりあえず始めましょうよ。お食事は八純さんが帰ってからでいいかしら?」
「すみません」
冷えた瓶の口をうきうきした面持ちで差し出す母に、しーちゃんはちょっと恐縮した様子でグラスを持ち上げて応えた。
コポコポと小気味のいい音をたてて、小麦色の液体がなみなみと注がれる。
高い声で「おつかれさま」と声をかけ、グラス半分ほど一気に飲んだお母さんは何だかすごく楽しそう。
私は2人の間――お誕生日席にあひる座りをして、わずかな泡をチロリと舌先で舐めた。
ビールはまだ苦手。だから見かけによらずよく飲むお母さんに、しーちゃんがこうやって付き合ってくれるのは私も嬉しかった。
まもなくして八純が帰宅すると、宴はますます華やかになる。
野菜を牛肉で巻いて醤油で味つけした焼き物とか、旬の穴子を一口サイズにした天ぷらとか。
お母さんお得意の料理をお腹いっぱい堪能して、私達4人は他愛もない会話に花を咲かせた。
「あ、しーちゃんのCM。このバージョンは初めて観たな」
デザートタイムに差しかかって何気なく付けたテレビ。
軽快な音楽と共に流れた清涼飲料水のコマーシャルを見つけて、八純はからかうような視線を投げる。
「オレのクラスでも話題になってたよ。女子達にとってしーちゃんは『カッコカワイイ』存在らしい。あんがい辛辣な性格してるってことは、
営業妨害に当たる可能性を考えて黙っておいたけど」
「あはは。ありがとうって言っておくね、一応」
しーちゃんが照れを交えて苦笑うと、続けてお母さんが問いかける。
「蘭子ちゃんは紫己さんが芸能活動の幅を広げたことを、何て言ってるのかしら?」
「いえ、母は知らないと思います。日本のテレビ番組をわざわざ観るタイプでもないですし」
「たしかにそうねー。学生の頃からあまり興味がないという感じだったわ。今もまだフランスに?」
「ええ、お陰さまで自由人ですよ。あ、でも年内には1度、セリのドレスのサイズを測りに帰るって言ってました。まだ先だっていうのに、待ちきれないらしくて」
そういうところも相変わらずですと付け加えて、しーちゃんはわざと困ったように笑う。
ほがらかな様子の2人を横目に、私は1人絶句した。
ドレス……って何?
あまりにもサラリと言うものだから、つい流してしまいそうになったけど。まさか……。
信じがたい思いでしーちゃんを凝視すると、淡々と続ける言葉の先にもう一度その話題があがって明白になる。
「母の強い希望らしいんですよね。セリのウエディングドレスを生地からプロデュースするのが」
「しーちゃん!!」
思わず大声を出してしまう。
だってお母さんは私と蒼くんのクリスマスイヴの事を知ってるの。
それなのにしーちゃんが急にそんな話をしたら、混乱して対応に困るじゃない!?
せっかくの温かい食事会が張りつめた空気に変わるのが嫌で、私はしーちゃんの服の袖を引っ張り「今はやめて」と目で訴えた。
でもそんなことはただの杞憂だったみたい。
お母さんが少しも動揺することなく口元を綻ばせて頷いたのを見て、じわじわと状況を察する。
そっか。家を離れてたからって、お母さんが何も知らないはずはない。
結婚は天力者の血をより濃く残し、閨閥を結んで社会的地位を高める為のもの。そういう考えに反発せずに、この宮家に嫁いできた人だものね。
「…………」
私はそこから何も言えなくなって、小さく下唇を噛む。
「芹七さんのお相手が紫己さんであってくれて良かったと、心から感謝しているわ」
何杯目か分からないビールをしーちゃんのグラスにつぎながら、お母さんは控え目に言葉を返す。
「でも若いうちはキラキラしたものが多すぎて、たった一つを選ぶのはとても難しいものでしょう?」
だからあまり焦らないであげてね。
そう最後にやんわりと強い意志をこめたお母さんの台詞に、同じ道を辿る娘への思いやりが込められている気がした。
3人の話題が時事ネタに突入したところを見計らって、私は眠くなったふりをして一足先に光の間を後にした。
手の中のスマホの暗転を解くと、時刻は21時40分。
自分の部屋にこもるのはまだ早い気がして、冷蔵庫からウーロン茶を持ち出すとそのまま縁側に腰を下ろす。
ひんやりと心地のいい夜風を浴びながら、手入れの行き届いた日本庭園をぼんやりと眺めた。
「ウエディングドレスかぁ……」
そりゃあ、憧れがないわけじゃない。プリンセスラインがいいか、やっぱりマーメードか〜なんて。
『結婚』を意識せざるを得なくなってから、雑誌の広告画像を見つけては自分に置きかえて妄想したこともある。
ヘッドアクセは生花? それともティアラやクラウン? ベールとグローブは光沢のあるレースを使って、新郎に寄り添った時にキラキラしたら素敵。
あっ、それならやっぱり、しーちゃんは真っ白いタキシードかな?
シルバーとブラックで縁取られた華やかなデザインを見かけたこともあるけど、やっぱり王子様は白がカッコいい。
もともとの素材がイイしーちゃんだからこそ、正統派なデザインで決めて…………。
そこまで考えて、私はハッと我に返った。
何で相手をしーちゃんで想像しちゃうのよ!?
縁側からぶらりと垂らした脚を乱暴に蹴りあげ、不要な妄想をあわてて一掃する。
私は気を取り直すように藍色の空を見上げた。
東南の空に浮かぶ三日月がすごくキレイだったから、スマホで写真を撮ってそのまま蒼くんに送信する。
【1人お茶中です (^_-)-☆】
数分後、シンプルな返信が届く。
【風邪ひくなよ】
あったかい一言が嬉しくて、思わずニヤケてしまった。
勉強中だったかな?
邪魔にならないか気にはなったけど、我慢できなくてもう一度ラインを返す。
【蒼くんはもうご飯食べた?】
【ちょうど今食ってたとこ。誰もいなくて久々に5分飯つくった】
【5分メシって??】
【5分でできるどんぶり飯。豚肉やいて生卵のっけてみた】
【おいしそう(*^。^*) 私にも今度つくってね♪】
【いや、宮と食うならもっとウマいもんの方がいいだろ】
何気ないやりとりが幸せ。
既読を確認してつながりを確信できることに、ただただ安心した。
こうやっていることで、霞がかった自分の立ち位置をしっかり把握することができる気がするの。
蒼くんの彼女なんだって、もっと実感したい。
触れ合えない距離をこの小さな画面で補って、やっと私たちは『恋人』だった。
【来週末は遊びに行こう。どこかいい?】
蒼くんからそう尋ねられて、喜びのスタンプを返そうとした矢先。「せり」と頭上にしーちゃんの声が降りかかった。
私は咄嗟にスマホにロックをかけて、画面の色を落とす。
別に隠す必要もなかったのだけど、どこか後ろめたい気持ちがそうさせた。
「なに?」
あたふたとスマホを床に伏せて、しーちゃんに短く応答した。
「今夜泊まってくことになったからさ。八純の後でお風呂借りるね」
「あ、うん。ごゆっくり。私は最後で大丈夫だから」
しーちゃんがうちに泊まるのは珍しくない。中庭をはさんで西側にある離れは、今やしーちゃんの別邸だ。
会話の流れからすぐに立ち去ると思ったしーちゃんだけど、私の手元にあったウーロン茶を見つけて足を止める。
「それ、一口ちょうだい」
「え? これ? もうヌルいかもだけど……」
「イイよ別に。あ、やっぱ残り全部ちょうだい」
「ええ!?」
了解も待たずにペットボトルをすくいあげ、私の斜め後ろにさりげなく座り込む。
しーちゃんはよっぽど喉が渇いていたのか、片膝をたててあぐらをかき美味しそうに喉をならした。
シャープな顎から続く男らしい首筋と、ゴツゴツした鎖骨のラインが変に色っぽい。
目のやり場に困った私は、庭の池にむりやり視線を移す。
「ねえ、髪ずっと伸ばしてるよね。セリのショートヘアって記憶にないんだけど」
ふとして、しーちゃんが背後から私の髪に触れた。
一房とっては指に巻きつけてクルリと滑らし、それを数度くり返す。
「……だ……だって、くせ毛なんだもん。長くしてないと広がっちゃって大惨事だし」
指先がたまにうなじをかする。じれったい動きに妙な心地を覚えて、私はわずかに身をよじった。
それを目ざとく見つけて、しーちゃんは笑いを含んだ声をあげる。
「ふ〜ん。相変わらずこのあたり弱いんだ。覚えてる? 小学生のころ髪留めつけてあげるのに、じっとしてられなくて苦労させられたんだよね」
「え、そうだっけ?」
「うん。だからこうやって、後ろから動かないように押さえてさ〜」
そう言うとしーちゃんは脇から私のお腹に手を回し入れ、グイッと自分の元に引き寄せた。
「きゃっ」
座ったまま両膝の間にすっぽりと包まれて、しーちゃんの胸に背を預ける体勢になる。
たしかにこれなら身動きがとれない。とれないんだけどぉ…………。
 「懐かしいでしょ? で、こんなふうに髪を結ってあげてさ〜」
しーちゃんは平然と続けて思い出を語るけど、私の心臓はただならぬ音を立てていてそれどころじゃなかった。
もう子供じゃないんだから、この距離は反則でしょ!?
だけどしーちゃんがあまりにも普段と変わらないから、自分だけ意識してるのを悟られないように「そうだっけ?」なんて素っ気なく返す。
しーちゃんは可笑しそうに笑った。
「この年にもなると、さすがにセリの髪をどうこうで押さえつけることもなくなったよね」
「あ……当たり前じゃない! もうチビっこじゃないんだからそんな必要ないもん。ほら、分かったからもう離して……」
「あっ、でもこの体勢って、大人になってもわりと使えるかも」
「な、何それ。どんな時よ」
「んー、例えばキスする時とか?」
「!!?」
さすがにしーちゃんの言動がおかしい。
酔ってるの?
冗談だとしても慣れない甘さにむせ返りそうになって、平静を装うのは限界だった。
「もお! 飲みすぎだよ!」
笑顔で叱咤しながら、立ち上がろうと体を起こす。
でも途中で腕を掴まれて、また再び胸の中に引き戻されてしまった。
それも今度は横抱きに膝に乗せられたものだから、視線がバッチリとぶつかって動揺を隠しきれない。
「あ……」
私を至近距離で見下ろすしーちゃんは、すごく真剣なカオをしていた。何か逃げづらい。
困って目を泳がせていると、長い睫毛が瞬く音がしてフッと穏やかに息もがれる。
「僕のところにおいでよ」
「え……」
「たしかにまだ若いし、たった一つを選ぶのは怖いかもしれないけどさ。それでも幸せだって思えるくらい、セリを大切にするから」
「しーちゃん……?」
「大学を卒業したら、僕と結婚して欲しい」
何を言われたのか理解したのは数秒だってからだった。
思いがけない直球のプロポーズ。
熱をおびた真っ直ぐな瞳にこのまま溶かされちゃうんじゃないかって思った。
しーちゃんの本気が私の全身を痺れさせて、息さえもうまくできない。
「正直……さ」
硬直した私の左手を絡めとって握り、しーちゃんは囁くように語る。
「ここまで来るのにずいぶん悩みもしたよ。一生お世話役に徹した方が楽に決まってるし、蒼との事を知った時にはそういうのもアリかな、とも思った」
そして大きく息をついた。
「でもやっぱヤなんだよね。僕が一番じゃないのはさ」
自分勝手ともとれる台詞を、清々しいほどはっきりと口にする。
「甘えさせるのも叱るのも、僕だけでいい。そう思ったらこの先セリを手離すことなんて、考えられなくなったんだ」
私に言ってる……の?
役目としてではなく、幼なじみとしてでもなく。しーちゃんが1人の女の子として私に想いを寄せるなんて信じられなかった。
だっていつだって子供扱いしてたじゃない。私ではない誰かと恋愛してたじゃない。
驚きと甘酸っぱい喜びで胸が痛くなり、頭の中は真っ白になった。
思考回路が遮断して言語能力を失っていると、しーちゃんの形のいい唇がゆっくりと近づいてくる。
「あ……ダメ……」
流されそうになるギリギリのところで蒼くんの顔が浮かんだ。
理性を取り戻した私は隠すみたいに顔を背ける。
でもそんな小さな抵抗が通用したのは一瞬で、すぐさま頭ごと引き寄せられて強引に唇をふさがれた。
「んっ……」
わずかな隙間を割って入ってきた舌が、私のものにぬらりと絡みつく。
チュッと音がなって恥ずかしさで首をすくめると、体が大きく傾いて、抱きかかえられたまま床に押し倒されてしまう。
「懐かしいでしょ? で、こんなふうに髪を結ってあげてさ〜」
しーちゃんは平然と続けて思い出を語るけど、私の心臓はただならぬ音を立てていてそれどころじゃなかった。
もう子供じゃないんだから、この距離は反則でしょ!?
だけどしーちゃんがあまりにも普段と変わらないから、自分だけ意識してるのを悟られないように「そうだっけ?」なんて素っ気なく返す。
しーちゃんは可笑しそうに笑った。
「この年にもなると、さすがにセリの髪をどうこうで押さえつけることもなくなったよね」
「あ……当たり前じゃない! もうチビっこじゃないんだからそんな必要ないもん。ほら、分かったからもう離して……」
「あっ、でもこの体勢って、大人になってもわりと使えるかも」
「な、何それ。どんな時よ」
「んー、例えばキスする時とか?」
「!!?」
さすがにしーちゃんの言動がおかしい。
酔ってるの?
冗談だとしても慣れない甘さにむせ返りそうになって、平静を装うのは限界だった。
「もお! 飲みすぎだよ!」
笑顔で叱咤しながら、立ち上がろうと体を起こす。
でも途中で腕を掴まれて、また再び胸の中に引き戻されてしまった。
それも今度は横抱きに膝に乗せられたものだから、視線がバッチリとぶつかって動揺を隠しきれない。
「あ……」
私を至近距離で見下ろすしーちゃんは、すごく真剣なカオをしていた。何か逃げづらい。
困って目を泳がせていると、長い睫毛が瞬く音がしてフッと穏やかに息もがれる。
「僕のところにおいでよ」
「え……」
「たしかにまだ若いし、たった一つを選ぶのは怖いかもしれないけどさ。それでも幸せだって思えるくらい、セリを大切にするから」
「しーちゃん……?」
「大学を卒業したら、僕と結婚して欲しい」
何を言われたのか理解したのは数秒だってからだった。
思いがけない直球のプロポーズ。
熱をおびた真っ直ぐな瞳にこのまま溶かされちゃうんじゃないかって思った。
しーちゃんの本気が私の全身を痺れさせて、息さえもうまくできない。
「正直……さ」
硬直した私の左手を絡めとって握り、しーちゃんは囁くように語る。
「ここまで来るのにずいぶん悩みもしたよ。一生お世話役に徹した方が楽に決まってるし、蒼との事を知った時にはそういうのもアリかな、とも思った」
そして大きく息をついた。
「でもやっぱヤなんだよね。僕が一番じゃないのはさ」
自分勝手ともとれる台詞を、清々しいほどはっきりと口にする。
「甘えさせるのも叱るのも、僕だけでいい。そう思ったらこの先セリを手離すことなんて、考えられなくなったんだ」
私に言ってる……の?
役目としてではなく、幼なじみとしてでもなく。しーちゃんが1人の女の子として私に想いを寄せるなんて信じられなかった。
だっていつだって子供扱いしてたじゃない。私ではない誰かと恋愛してたじゃない。
驚きと甘酸っぱい喜びで胸が痛くなり、頭の中は真っ白になった。
思考回路が遮断して言語能力を失っていると、しーちゃんの形のいい唇がゆっくりと近づいてくる。
「あ……ダメ……」
流されそうになるギリギリのところで蒼くんの顔が浮かんだ。
理性を取り戻した私は隠すみたいに顔を背ける。
でもそんな小さな抵抗が通用したのは一瞬で、すぐさま頭ごと引き寄せられて強引に唇をふさがれた。
「んっ……」
わずかな隙間を割って入ってきた舌が、私のものにぬらりと絡みつく。
チュッと音がなって恥ずかしさで首をすくめると、体が大きく傾いて、抱きかかえられたまま床に押し倒されてしまう。
 角度を変えて味わうように、さらに深くなる口付け。
遠のく理性を呼び戻さなきゃと、しーちゃんの服をつかんで必死に頭を振った。
「……逃げないで」
なのに、内側から聞こえるくぐもった声が耳までをも犯す。
なめらかな舌で口内を撫でながら、時おりしーちゃんは吐息混じりの熱っぽい声で私の名を呼ぶの。
「ん……セリ……」
隅々まで愛撫される感覚が気持ち良くて、頭の芯がぼんやりと鈍くなっていくのを感じた。
イタズラじゃない、大人のキス。
舌の先端を優しく吸われ、粘膜が擦れ合う度にピチャと厭らしく水音が跳ねる。
「ぅん……っ」
唇が拘束を解かれたのは、私がすっかり脱力してからだった。
冷えた縁側の板にぐったりと転がったままの私を、しーちゃんは愛でるように見つめてフッと口角を上げる。
「ここから、覚悟しておいてね」
何の覚悟? いや。ダメ、もうこんな事しないで。
しーちゃんの本気は抗いきれなくて、自分の立ち位置がまたあやふやになる。
飛べない綿毛になったようで怖いの。
角度を変えて味わうように、さらに深くなる口付け。
遠のく理性を呼び戻さなきゃと、しーちゃんの服をつかんで必死に頭を振った。
「……逃げないで」
なのに、内側から聞こえるくぐもった声が耳までをも犯す。
なめらかな舌で口内を撫でながら、時おりしーちゃんは吐息混じりの熱っぽい声で私の名を呼ぶの。
「ん……セリ……」
隅々まで愛撫される感覚が気持ち良くて、頭の芯がぼんやりと鈍くなっていくのを感じた。
イタズラじゃない、大人のキス。
舌の先端を優しく吸われ、粘膜が擦れ合う度にピチャと厭らしく水音が跳ねる。
「ぅん……っ」
唇が拘束を解かれたのは、私がすっかり脱力してからだった。
冷えた縁側の板にぐったりと転がったままの私を、しーちゃんは愛でるように見つめてフッと口角を上げる。
「ここから、覚悟しておいてね」
何の覚悟? いや。ダメ、もうこんな事しないで。
しーちゃんの本気は抗いきれなくて、自分の立ち位置がまたあやふやになる。
飛べない綿毛になったようで怖いの。
<<前へ 3話へ>>
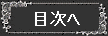
 「懐かしいでしょ? で、こんなふうに髪を結ってあげてさ〜」
しーちゃんは平然と続けて思い出を語るけど、私の心臓はただならぬ音を立てていてそれどころじゃなかった。
もう子供じゃないんだから、この距離は反則でしょ!?
だけどしーちゃんがあまりにも普段と変わらないから、自分だけ意識してるのを悟られないように「そうだっけ?」なんて素っ気なく返す。
しーちゃんは可笑しそうに笑った。
「この年にもなると、さすがにセリの髪をどうこうで押さえつけることもなくなったよね」
「あ……当たり前じゃない! もうチビっこじゃないんだからそんな必要ないもん。ほら、分かったからもう離して……」
「あっ、でもこの体勢って、大人になってもわりと使えるかも」
「な、何それ。どんな時よ」
「んー、例えばキスする時とか?」
「!!?」
さすがにしーちゃんの言動がおかしい。
酔ってるの?
冗談だとしても慣れない甘さにむせ返りそうになって、平静を装うのは限界だった。
「もお! 飲みすぎだよ!」
笑顔で叱咤しながら、立ち上がろうと体を起こす。
でも途中で腕を掴まれて、また再び胸の中に引き戻されてしまった。
それも今度は横抱きに膝に乗せられたものだから、視線がバッチリとぶつかって動揺を隠しきれない。
「あ……」
私を至近距離で見下ろすしーちゃんは、すごく真剣なカオをしていた。何か逃げづらい。
困って目を泳がせていると、長い睫毛が瞬く音がしてフッと穏やかに息もがれる。
「僕のところにおいでよ」
「え……」
「たしかにまだ若いし、たった一つを選ぶのは怖いかもしれないけどさ。それでも幸せだって思えるくらい、セリを大切にするから」
「しーちゃん……?」
「大学を卒業したら、僕と結婚して欲しい」
何を言われたのか理解したのは数秒だってからだった。
思いがけない直球のプロポーズ。
熱をおびた真っ直ぐな瞳にこのまま溶かされちゃうんじゃないかって思った。
しーちゃんの本気が私の全身を痺れさせて、息さえもうまくできない。
「正直……さ」
硬直した私の左手を絡めとって握り、しーちゃんは囁くように語る。
「ここまで来るのにずいぶん悩みもしたよ。一生お世話役に徹した方が楽に決まってるし、蒼との事を知った時にはそういうのもアリかな、とも思った」
そして大きく息をついた。
「でもやっぱヤなんだよね。僕が一番じゃないのはさ」
自分勝手ともとれる台詞を、清々しいほどはっきりと口にする。
「甘えさせるのも叱るのも、僕だけでいい。そう思ったらこの先セリを手離すことなんて、考えられなくなったんだ」
私に言ってる……の?
役目としてではなく、幼なじみとしてでもなく。しーちゃんが1人の女の子として私に想いを寄せるなんて信じられなかった。
だっていつだって子供扱いしてたじゃない。私ではない誰かと恋愛してたじゃない。
驚きと甘酸っぱい喜びで胸が痛くなり、頭の中は真っ白になった。
思考回路が遮断して言語能力を失っていると、しーちゃんの形のいい唇がゆっくりと近づいてくる。
「あ……ダメ……」
流されそうになるギリギリのところで蒼くんの顔が浮かんだ。
理性を取り戻した私は隠すみたいに顔を背ける。
でもそんな小さな抵抗が通用したのは一瞬で、すぐさま頭ごと引き寄せられて強引に唇をふさがれた。
「んっ……」
わずかな隙間を割って入ってきた舌が、私のものにぬらりと絡みつく。
チュッと音がなって恥ずかしさで首をすくめると、体が大きく傾いて、抱きかかえられたまま床に押し倒されてしまう。
「懐かしいでしょ? で、こんなふうに髪を結ってあげてさ〜」
しーちゃんは平然と続けて思い出を語るけど、私の心臓はただならぬ音を立てていてそれどころじゃなかった。
もう子供じゃないんだから、この距離は反則でしょ!?
だけどしーちゃんがあまりにも普段と変わらないから、自分だけ意識してるのを悟られないように「そうだっけ?」なんて素っ気なく返す。
しーちゃんは可笑しそうに笑った。
「この年にもなると、さすがにセリの髪をどうこうで押さえつけることもなくなったよね」
「あ……当たり前じゃない! もうチビっこじゃないんだからそんな必要ないもん。ほら、分かったからもう離して……」
「あっ、でもこの体勢って、大人になってもわりと使えるかも」
「な、何それ。どんな時よ」
「んー、例えばキスする時とか?」
「!!?」
さすがにしーちゃんの言動がおかしい。
酔ってるの?
冗談だとしても慣れない甘さにむせ返りそうになって、平静を装うのは限界だった。
「もお! 飲みすぎだよ!」
笑顔で叱咤しながら、立ち上がろうと体を起こす。
でも途中で腕を掴まれて、また再び胸の中に引き戻されてしまった。
それも今度は横抱きに膝に乗せられたものだから、視線がバッチリとぶつかって動揺を隠しきれない。
「あ……」
私を至近距離で見下ろすしーちゃんは、すごく真剣なカオをしていた。何か逃げづらい。
困って目を泳がせていると、長い睫毛が瞬く音がしてフッと穏やかに息もがれる。
「僕のところにおいでよ」
「え……」
「たしかにまだ若いし、たった一つを選ぶのは怖いかもしれないけどさ。それでも幸せだって思えるくらい、セリを大切にするから」
「しーちゃん……?」
「大学を卒業したら、僕と結婚して欲しい」
何を言われたのか理解したのは数秒だってからだった。
思いがけない直球のプロポーズ。
熱をおびた真っ直ぐな瞳にこのまま溶かされちゃうんじゃないかって思った。
しーちゃんの本気が私の全身を痺れさせて、息さえもうまくできない。
「正直……さ」
硬直した私の左手を絡めとって握り、しーちゃんは囁くように語る。
「ここまで来るのにずいぶん悩みもしたよ。一生お世話役に徹した方が楽に決まってるし、蒼との事を知った時にはそういうのもアリかな、とも思った」
そして大きく息をついた。
「でもやっぱヤなんだよね。僕が一番じゃないのはさ」
自分勝手ともとれる台詞を、清々しいほどはっきりと口にする。
「甘えさせるのも叱るのも、僕だけでいい。そう思ったらこの先セリを手離すことなんて、考えられなくなったんだ」
私に言ってる……の?
役目としてではなく、幼なじみとしてでもなく。しーちゃんが1人の女の子として私に想いを寄せるなんて信じられなかった。
だっていつだって子供扱いしてたじゃない。私ではない誰かと恋愛してたじゃない。
驚きと甘酸っぱい喜びで胸が痛くなり、頭の中は真っ白になった。
思考回路が遮断して言語能力を失っていると、しーちゃんの形のいい唇がゆっくりと近づいてくる。
「あ……ダメ……」
流されそうになるギリギリのところで蒼くんの顔が浮かんだ。
理性を取り戻した私は隠すみたいに顔を背ける。
でもそんな小さな抵抗が通用したのは一瞬で、すぐさま頭ごと引き寄せられて強引に唇をふさがれた。
「んっ……」
わずかな隙間を割って入ってきた舌が、私のものにぬらりと絡みつく。
チュッと音がなって恥ずかしさで首をすくめると、体が大きく傾いて、抱きかかえられたまま床に押し倒されてしまう。
 角度を変えて味わうように、さらに深くなる口付け。
遠のく理性を呼び戻さなきゃと、しーちゃんの服をつかんで必死に頭を振った。
「……逃げないで」
なのに、内側から聞こえるくぐもった声が耳までをも犯す。
なめらかな舌で口内を撫でながら、時おりしーちゃんは吐息混じりの熱っぽい声で私の名を呼ぶの。
「ん……セリ……」
隅々まで愛撫される感覚が気持ち良くて、頭の芯がぼんやりと鈍くなっていくのを感じた。
イタズラじゃない、大人のキス。
舌の先端を優しく吸われ、粘膜が擦れ合う度にピチャと厭らしく水音が跳ねる。
「ぅん……っ」
唇が拘束を解かれたのは、私がすっかり脱力してからだった。
冷えた縁側の板にぐったりと転がったままの私を、しーちゃんは愛でるように見つめてフッと口角を上げる。
「ここから、覚悟しておいてね」
何の覚悟? いや。ダメ、もうこんな事しないで。
しーちゃんの本気は抗いきれなくて、自分の立ち位置がまたあやふやになる。
飛べない綿毛になったようで怖いの。
角度を変えて味わうように、さらに深くなる口付け。
遠のく理性を呼び戻さなきゃと、しーちゃんの服をつかんで必死に頭を振った。
「……逃げないで」
なのに、内側から聞こえるくぐもった声が耳までをも犯す。
なめらかな舌で口内を撫でながら、時おりしーちゃんは吐息混じりの熱っぽい声で私の名を呼ぶの。
「ん……セリ……」
隅々まで愛撫される感覚が気持ち良くて、頭の芯がぼんやりと鈍くなっていくのを感じた。
イタズラじゃない、大人のキス。
舌の先端を優しく吸われ、粘膜が擦れ合う度にピチャと厭らしく水音が跳ねる。
「ぅん……っ」
唇が拘束を解かれたのは、私がすっかり脱力してからだった。
冷えた縁側の板にぐったりと転がったままの私を、しーちゃんは愛でるように見つめてフッと口角を上げる。
「ここから、覚悟しておいてね」
何の覚悟? いや。ダメ、もうこんな事しないで。
しーちゃんの本気は抗いきれなくて、自分の立ち位置がまたあやふやになる。
飛べない綿毛になったようで怖いの。