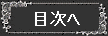◇ 6.お姫様への捧げもの 壱 〜 紫己 〜
モンブランでも、買ってくか――。
僕がそう思いついたのは3人で家へ向かう途中、ちょうどバス通りの交差点に差しかかった時だった。
時刻は16時半すぎ。沈みかけた太陽が、空をキレイなオレンジ色に染めている。
左隣ではが明るい声をあげ、いつものようにのんびりマイペースに歩いていた。
その向こうがわ1歩前に、まだ顔色が戻りきらない蒼が並ぶ。
青信号はすでに点滅を始めていた。
の足では、もう渡りきることはできない。っていうか、下手すれば躓く。
そう判断したのもあって、僕は数歩手前で足を止める。
「……あ。ねー、先に2人で行っててよ。僕は1軒、寄ってきたいトコがあるから」
 前ぶれのないセリフに驚いて、は勢いよく振り返った。逆光がまぶしかったのか、ちょっと色っぽく目を細める。
「え? どしたの、急に」
別に隠すことじゃない。
でも手に入らないかもしれない人気商品に、過度な期待をかけられるのは重くて。
問いには答えず、の形のイイ額を撫でるように小突いた。
「すぐ向かうからさ。蒼をよろしくね」
『リオン』というレストランのモンブランを買う。
別に今さら家への手土産というわけではない。
昨晩、妖力者を浄化したさいに、があやまって踏みつぶしたのがソレだった。
敵からの攻撃をさけるために、とっさに僕はの背中を突き飛ばした。
まあ多少、乱暴だったのは認める。
でも自分で落としておいて、自分でダメにしたくせに。
怒りと悲しみの入り混じった目で、こっちを睨みつけていた。
「しーちゃんのせいで、食べそこねた〜!」 って、が恨んでいるだろうことは容易に想像がつく。
そのフォロー。
(……ったく。何であんなに、甘いものへの執着が強いんだか。まるでガキじゃん)
ふわりと前髪をかきあげカオを歪ませると、心の中でそうボヤく。
幼なじみのはのんびりした子供っぽい性格で、こんな風にたまに僕をイラつかせた。
長く柔らかい髪。透き通るように白い肌。女らしい身体つき。
見かけは人形のようにカワイイ。それは認める。
でも温室育ちの世間知らずで、天然に周囲を振り回して。
やけに手がかかるところなんて、昔からちっとも変わってない。
18年来の『お世話係』としては、「いいかげんにしてくれ!」と両頬をつねってやりたいところ。
だからこそキツイ物言いをしてしまうし、泣かせてやりたいとサド的にもなる。
(でも、さ……)
結局、憎めない。
自分は良くても、他の誰かが傷つけるのは許せない。
可愛くて、大切なお姫さま。
店の前に到着した僕はフッとため息をついて、アンティークな金のドアノブに手をかけた。
モンブランを嬉しそうに頬張る、の無邪気な笑顔が想像できて、思わず顔がほころぶ。
(……結局、弱いんだよね……)
そんな時だった。
パンツの後ろポケットに無造作につっこんでおいた携帯が、小さくメロディーを奏でる。
「はい、もしもーし。今向かってるトコだけど、どうかした?」
相手は八純だった。
17時の約束にはまだ時間がある。
催促の電話じゃないとするなら、キャンセルだろうか。
次期天主という責を担う、IQ200のスーパー高校生。
彼の多忙さを十分すぎるほど知っている僕は、チラリとそんなことを考える。
まあ、ソレはそれで仕方がない。蒼には泣いてもらうってコトで――。
『しーちゃん、まだ駅の近くにいるかな?』
でも予想に反し、八純はそんなことを訊いてきた。
「今、リオンの前だけど? 何?」
『そうか、ちょうど良かった。1つ頼みたいことがあるんだ。寄り道してきてくれないかな』
寄り道の寄り道になるんだけど……。という言葉を飲み込んで、素直にOKと返事をする。
『姉さんたちは……そばにいる?』
「いないよ。蒼と一緒に、そろそろそっちに着く頃だと思うけど」
『なおさら好都合だな。実はしーちゃんに、裏通りのとある店舗を覗いてきて欲しいんだ』
「…………」
電話越しの声はどことなくこもり、イヤな重みがあった。
仕事の話に違いない……とすぐさま悟って、携帯を握りなおし『リオン』に背を向ける。
「――で、何があったの?」
『裏通り』と呼ばれているのは駅から北に真っ直ぐ伸びた細い路地で、夜はキャッチの行き交う繁華街だ。
いわゆる水商売系の店舗やラブホテルが立ち並び、女の子の1人歩きや制服姿での出入りはタブーとされている。
そんな通りに並ぶ店を見てこいと八純が言うのだから、仕事の話以外はあり得ない。
『実は昨日、八王子駅付近で、新たな妖人が発見されたんだ』
「!?」
八純の言葉に一瞬息をのむ。
妖人。妖力者に精神を喰われた人間、言わば被害者のこと。
外傷なく記憶や心の一部が欠落し、支離滅裂な言動をくり返すなどの状態で発見されるケースが多い。
昨日、と八純は言った。
自分たちが男の妖力者を浄化した、昨日だと――。
「何? 僕たちと出会う前に、1人喰らってたってこと? ずいぶん暴食じゃん」
皮肉めいたセリフを吐きながら、裏通りへと足を進める。
『それなら、まだマシだとオレは思ってる』
八純はさらに声のトーンを落とした。
『別の妖力者が現れた――ということも、否定はできない。だから見てきて欲しいんだ。そこにある『バンビーナ』っていう店を』
詳細は後ほど。
こちらからの質問を受けつけず、最後にそう穏やかに囁いた八純。
ヤレヤレ……と息をつき、僕は携帯をパタンと閉じた。
幼なじみであり、仕事の上司。
姉のとは正反対の、手のかからない完璧な弟。
兄弟のいない僕にとっては、可愛くも頼れる存在なんだけど……ね。
カラフルな光が点され始めた裏通りには、色香をふりまく外国人の女性とスーツ姿の若い男の出入りが目立った。
前ぶれのないセリフに驚いて、は勢いよく振り返った。逆光がまぶしかったのか、ちょっと色っぽく目を細める。
「え? どしたの、急に」
別に隠すことじゃない。
でも手に入らないかもしれない人気商品に、過度な期待をかけられるのは重くて。
問いには答えず、の形のイイ額を撫でるように小突いた。
「すぐ向かうからさ。蒼をよろしくね」
『リオン』というレストランのモンブランを買う。
別に今さら家への手土産というわけではない。
昨晩、妖力者を浄化したさいに、があやまって踏みつぶしたのがソレだった。
敵からの攻撃をさけるために、とっさに僕はの背中を突き飛ばした。
まあ多少、乱暴だったのは認める。
でも自分で落としておいて、自分でダメにしたくせに。
怒りと悲しみの入り混じった目で、こっちを睨みつけていた。
「しーちゃんのせいで、食べそこねた〜!」 って、が恨んでいるだろうことは容易に想像がつく。
そのフォロー。
(……ったく。何であんなに、甘いものへの執着が強いんだか。まるでガキじゃん)
ふわりと前髪をかきあげカオを歪ませると、心の中でそうボヤく。
幼なじみのはのんびりした子供っぽい性格で、こんな風にたまに僕をイラつかせた。
長く柔らかい髪。透き通るように白い肌。女らしい身体つき。
見かけは人形のようにカワイイ。それは認める。
でも温室育ちの世間知らずで、天然に周囲を振り回して。
やけに手がかかるところなんて、昔からちっとも変わってない。
18年来の『お世話係』としては、「いいかげんにしてくれ!」と両頬をつねってやりたいところ。
だからこそキツイ物言いをしてしまうし、泣かせてやりたいとサド的にもなる。
(でも、さ……)
結局、憎めない。
自分は良くても、他の誰かが傷つけるのは許せない。
可愛くて、大切なお姫さま。
店の前に到着した僕はフッとため息をついて、アンティークな金のドアノブに手をかけた。
モンブランを嬉しそうに頬張る、の無邪気な笑顔が想像できて、思わず顔がほころぶ。
(……結局、弱いんだよね……)
そんな時だった。
パンツの後ろポケットに無造作につっこんでおいた携帯が、小さくメロディーを奏でる。
「はい、もしもーし。今向かってるトコだけど、どうかした?」
相手は八純だった。
17時の約束にはまだ時間がある。
催促の電話じゃないとするなら、キャンセルだろうか。
次期天主という責を担う、IQ200のスーパー高校生。
彼の多忙さを十分すぎるほど知っている僕は、チラリとそんなことを考える。
まあ、ソレはそれで仕方がない。蒼には泣いてもらうってコトで――。
『しーちゃん、まだ駅の近くにいるかな?』
でも予想に反し、八純はそんなことを訊いてきた。
「今、リオンの前だけど? 何?」
『そうか、ちょうど良かった。1つ頼みたいことがあるんだ。寄り道してきてくれないかな』
寄り道の寄り道になるんだけど……。という言葉を飲み込んで、素直にOKと返事をする。
『姉さんたちは……そばにいる?』
「いないよ。蒼と一緒に、そろそろそっちに着く頃だと思うけど」
『なおさら好都合だな。実はしーちゃんに、裏通りのとある店舗を覗いてきて欲しいんだ』
「…………」
電話越しの声はどことなくこもり、イヤな重みがあった。
仕事の話に違いない……とすぐさま悟って、携帯を握りなおし『リオン』に背を向ける。
「――で、何があったの?」
『裏通り』と呼ばれているのは駅から北に真っ直ぐ伸びた細い路地で、夜はキャッチの行き交う繁華街だ。
いわゆる水商売系の店舗やラブホテルが立ち並び、女の子の1人歩きや制服姿での出入りはタブーとされている。
そんな通りに並ぶ店を見てこいと八純が言うのだから、仕事の話以外はあり得ない。
『実は昨日、八王子駅付近で、新たな妖人が発見されたんだ』
「!?」
八純の言葉に一瞬息をのむ。
妖人。妖力者に精神を喰われた人間、言わば被害者のこと。
外傷なく記憶や心の一部が欠落し、支離滅裂な言動をくり返すなどの状態で発見されるケースが多い。
昨日、と八純は言った。
自分たちが男の妖力者を浄化した、昨日だと――。
「何? 僕たちと出会う前に、1人喰らってたってこと? ずいぶん暴食じゃん」
皮肉めいたセリフを吐きながら、裏通りへと足を進める。
『それなら、まだマシだとオレは思ってる』
八純はさらに声のトーンを落とした。
『別の妖力者が現れた――ということも、否定はできない。だから見てきて欲しいんだ。そこにある『バンビーナ』っていう店を』
詳細は後ほど。
こちらからの質問を受けつけず、最後にそう穏やかに囁いた八純。
ヤレヤレ……と息をつき、僕は携帯をパタンと閉じた。
幼なじみであり、仕事の上司。
姉のとは正反対の、手のかからない完璧な弟。
兄弟のいない僕にとっては、可愛くも頼れる存在なんだけど……ね。
カラフルな光が点され始めた裏通りには、色香をふりまく外国人の女性とスーツ姿の若い男の出入りが目立った。
 指定された店『バンビーナ』の看板を見つけると、足を止めて視線を上げる。
7階建ての雑居ビル5階。予想通り、キャバクラといったところだけど。
灯りがついていない……?
まだ早かったか。
左腕のオメガに目をやると、17時5分を指し示していた。
オープンが8時として。その前に店舗の掃除。グラスや酒の確認。
日払いの給料の準備と、ミーティング。
暇つぶしに早々出勤するキャストたちの相手をすることもふまえると、もう誰かが店を開けていてもおかしくない時間だ。
しばらく様子を伺ってみる。
すると10分後、ようやくボーイらしき若い男が現れ、僕の存在に目をつけた。
「あ、お兄さ〜ん。どっかお店、お探しっスか〜?」
黒いスーツ姿の男はヘラヘラと安っぽい笑顔をふりまき、手にしていたビラを強引に押しつける。
そこに『バンビーナ』という文字を見つけ、思わず心の中でビンゴ! と叫んだ。
「……あれ? まだオープンしてないの?」
11月25日、記念感謝デー。ビールも飲み放題。
そんな添え書きに、ふと目がとまる。
「そ〜なんスよ。今週の金曜日オープンで。だから客ついてない、可愛い子いっぱいですよ〜!」
「ふーん。じゃあ、素人さんばっかりなんだ」
「いえいえ、そんなことないっスよ! うちは系列店で中野と立川、それに八王子にも店ありますし。今回、ベテランも
引っ張ってきてますんで」
ボーイの何気ない言葉に、額がピクリと揺れる。
「中野、立川、八王子……。それで、次はココ? ねえ、その全部のビラある?」
「いや、すんません。さすがにビラは……。あ! でもコレ持ってますんで、良ければ……」
そう言うと男はスーツの胸元から、自社のポケットティッシュを取りだした。
アルバイト募集の広告が挟まったソレを受け取り、僕はニコッと営業用の笑顔を見せる。
「分かった。必ず来るね。レギュラーメンバー指名で」
モデルらしくスマートに身を翻すと、そのまま繁華街を後にした。
足早にバス通りに戻りながら、広告に記載されたチェーン店の地図を確認する。
(……やっぱりね。この2週間で見つかった2人の妖人の場所と、ほぼ一致する)
八純が知りたかったのはきっとコレだ。
(そして新たに、八王子駅……)
3人目の妖人。
偶然なんてありえない。
まだ事件は終わっていなかった……?
疑惑が確信に変わる――。
少しでも早く、本家へ向かう必要があった。
八純の見解をもとに、次の作戦をたてなければいけない。
(……あ、ヤバイ。モンブラン……)
交差点に差しかかったところで、再びそんなことを思い出した。
一瞬迷いはしたものの、僕はもう一度体の向きを変える。
の機嫌をとっておく必要があるかもしれない。
そう判断して。
指定された店『バンビーナ』の看板を見つけると、足を止めて視線を上げる。
7階建ての雑居ビル5階。予想通り、キャバクラといったところだけど。
灯りがついていない……?
まだ早かったか。
左腕のオメガに目をやると、17時5分を指し示していた。
オープンが8時として。その前に店舗の掃除。グラスや酒の確認。
日払いの給料の準備と、ミーティング。
暇つぶしに早々出勤するキャストたちの相手をすることもふまえると、もう誰かが店を開けていてもおかしくない時間だ。
しばらく様子を伺ってみる。
すると10分後、ようやくボーイらしき若い男が現れ、僕の存在に目をつけた。
「あ、お兄さ〜ん。どっかお店、お探しっスか〜?」
黒いスーツ姿の男はヘラヘラと安っぽい笑顔をふりまき、手にしていたビラを強引に押しつける。
そこに『バンビーナ』という文字を見つけ、思わず心の中でビンゴ! と叫んだ。
「……あれ? まだオープンしてないの?」
11月25日、記念感謝デー。ビールも飲み放題。
そんな添え書きに、ふと目がとまる。
「そ〜なんスよ。今週の金曜日オープンで。だから客ついてない、可愛い子いっぱいですよ〜!」
「ふーん。じゃあ、素人さんばっかりなんだ」
「いえいえ、そんなことないっスよ! うちは系列店で中野と立川、それに八王子にも店ありますし。今回、ベテランも
引っ張ってきてますんで」
ボーイの何気ない言葉に、額がピクリと揺れる。
「中野、立川、八王子……。それで、次はココ? ねえ、その全部のビラある?」
「いや、すんません。さすがにビラは……。あ! でもコレ持ってますんで、良ければ……」
そう言うと男はスーツの胸元から、自社のポケットティッシュを取りだした。
アルバイト募集の広告が挟まったソレを受け取り、僕はニコッと営業用の笑顔を見せる。
「分かった。必ず来るね。レギュラーメンバー指名で」
モデルらしくスマートに身を翻すと、そのまま繁華街を後にした。
足早にバス通りに戻りながら、広告に記載されたチェーン店の地図を確認する。
(……やっぱりね。この2週間で見つかった2人の妖人の場所と、ほぼ一致する)
八純が知りたかったのはきっとコレだ。
(そして新たに、八王子駅……)
3人目の妖人。
偶然なんてありえない。
まだ事件は終わっていなかった……?
疑惑が確信に変わる――。
少しでも早く、本家へ向かう必要があった。
八純の見解をもとに、次の作戦をたてなければいけない。
(……あ、ヤバイ。モンブラン……)
交差点に差しかかったところで、再びそんなことを思い出した。
一瞬迷いはしたものの、僕はもう一度体の向きを変える。
の機嫌をとっておく必要があるかもしれない。
そう判断して。

<<前へ 7話へ>>
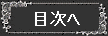
 前ぶれのないセリフに驚いて、は勢いよく振り返った。逆光がまぶしかったのか、ちょっと色っぽく目を細める。
「え? どしたの、急に」
別に隠すことじゃない。
でも手に入らないかもしれない人気商品に、過度な期待をかけられるのは重くて。
問いには答えず、の形のイイ額を撫でるように小突いた。
「すぐ向かうからさ。蒼をよろしくね」
『リオン』というレストランのモンブランを買う。
別に今さら家への手土産というわけではない。
昨晩、
前ぶれのないセリフに驚いて、は勢いよく振り返った。逆光がまぶしかったのか、ちょっと色っぽく目を細める。
「え? どしたの、急に」
別に隠すことじゃない。
でも手に入らないかもしれない人気商品に、過度な期待をかけられるのは重くて。
問いには答えず、の形のイイ額を撫でるように小突いた。
「すぐ向かうからさ。蒼をよろしくね」
『リオン』というレストランのモンブランを買う。
別に今さら家への手土産というわけではない。
昨晩、 指定された店『バンビーナ』の看板を見つけると、足を止めて視線を上げる。
7階建ての雑居ビル5階。予想通り、キャバクラといったところだけど。
灯りがついていない……?
まだ早かったか。
左腕のオメガに目をやると、17時5分を指し示していた。
オープンが8時として。その前に店舗の掃除。グラスや酒の確認。
日払いの給料の準備と、ミーティング。
暇つぶしに早々出勤するキャストたちの相手をすることもふまえると、もう誰かが店を開けていてもおかしくない時間だ。
しばらく様子を伺ってみる。
すると10分後、ようやくボーイらしき若い男が現れ、僕の存在に目をつけた。
「あ、お兄さ〜ん。どっかお店、お探しっスか〜?」
黒いスーツ姿の男はヘラヘラと安っぽい笑顔をふりまき、手にしていたビラを強引に押しつける。
そこに『バンビーナ』という文字を見つけ、思わず心の中でビンゴ! と叫んだ。
「……あれ? まだオープンしてないの?」
11月25日、記念感謝デー。ビールも飲み放題。
そんな添え書きに、ふと目がとまる。
「そ〜なんスよ。今週の金曜日オープンで。だから客ついてない、可愛い子いっぱいですよ〜!」
「ふーん。じゃあ、素人さんばっかりなんだ」
「いえいえ、そんなことないっスよ! うちは系列店で中野と立川、それに八王子にも店ありますし。今回、ベテランも
引っ張ってきてますんで」
ボーイの何気ない言葉に、額がピクリと揺れる。
「中野、立川、八王子……。それで、次はココ? ねえ、その全部のビラある?」
「いや、すんません。さすがにビラは……。あ! でもコレ持ってますんで、良ければ……」
そう言うと男はスーツの胸元から、自社のポケットティッシュを取りだした。
アルバイト募集の広告が挟まったソレを受け取り、僕はニコッと営業用の笑顔を見せる。
「分かった。必ず来るね。レギュラーメンバー指名で」
モデルらしくスマートに身を翻すと、そのまま繁華街を後にした。
足早にバス通りに戻りながら、広告に記載されたチェーン店の地図を確認する。
(……やっぱりね。この2週間で見つかった2人の妖人の場所と、ほぼ一致する)
八純が知りたかったのはきっとコレだ。
(そして新たに、八王子駅……)
3人目の妖人。
偶然なんてありえない。
まだ事件は終わっていなかった……?
疑惑が確信に変わる――。
少しでも早く、本家へ向かう必要があった。
八純の見解をもとに、次の作戦をたてなければいけない。
(……あ、ヤバイ。モンブラン……)
交差点に差しかかったところで、再びそんなことを思い出した。
一瞬迷いはしたものの、僕はもう一度体の向きを変える。
の機嫌をとっておく必要があるかもしれない。
そう判断して。
指定された店『バンビーナ』の看板を見つけると、足を止めて視線を上げる。
7階建ての雑居ビル5階。予想通り、キャバクラといったところだけど。
灯りがついていない……?
まだ早かったか。
左腕のオメガに目をやると、17時5分を指し示していた。
オープンが8時として。その前に店舗の掃除。グラスや酒の確認。
日払いの給料の準備と、ミーティング。
暇つぶしに早々出勤するキャストたちの相手をすることもふまえると、もう誰かが店を開けていてもおかしくない時間だ。
しばらく様子を伺ってみる。
すると10分後、ようやくボーイらしき若い男が現れ、僕の存在に目をつけた。
「あ、お兄さ〜ん。どっかお店、お探しっスか〜?」
黒いスーツ姿の男はヘラヘラと安っぽい笑顔をふりまき、手にしていたビラを強引に押しつける。
そこに『バンビーナ』という文字を見つけ、思わず心の中でビンゴ! と叫んだ。
「……あれ? まだオープンしてないの?」
11月25日、記念感謝デー。ビールも飲み放題。
そんな添え書きに、ふと目がとまる。
「そ〜なんスよ。今週の金曜日オープンで。だから客ついてない、可愛い子いっぱいですよ〜!」
「ふーん。じゃあ、素人さんばっかりなんだ」
「いえいえ、そんなことないっスよ! うちは系列店で中野と立川、それに八王子にも店ありますし。今回、ベテランも
引っ張ってきてますんで」
ボーイの何気ない言葉に、額がピクリと揺れる。
「中野、立川、八王子……。それで、次はココ? ねえ、その全部のビラある?」
「いや、すんません。さすがにビラは……。あ! でもコレ持ってますんで、良ければ……」
そう言うと男はスーツの胸元から、自社のポケットティッシュを取りだした。
アルバイト募集の広告が挟まったソレを受け取り、僕はニコッと営業用の笑顔を見せる。
「分かった。必ず来るね。レギュラーメンバー指名で」
モデルらしくスマートに身を翻すと、そのまま繁華街を後にした。
足早にバス通りに戻りながら、広告に記載されたチェーン店の地図を確認する。
(……やっぱりね。この2週間で見つかった2人の妖人の場所と、ほぼ一致する)
八純が知りたかったのはきっとコレだ。
(そして新たに、八王子駅……)
3人目の妖人。
偶然なんてありえない。
まだ事件は終わっていなかった……?
疑惑が確信に変わる――。
少しでも早く、本家へ向かう必要があった。
八純の見解をもとに、次の作戦をたてなければいけない。
(……あ、ヤバイ。モンブラン……)
交差点に差しかかったところで、再びそんなことを思い出した。
一瞬迷いはしたものの、僕はもう一度体の向きを変える。
の機嫌をとっておく必要があるかもしれない。
そう判断して。