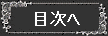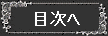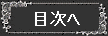決意してから半日もたってないっていうのに――。
翌日の朝食の席。
私はあっさりと、しーちゃんの半径2メートル以内に
入り込んでしまった。
「!? !? !!」
光の間のふすまをいつもみたいに、眠い目をこすりな
がら開けただけ。
なのにフツーに、お味噌汁をすすってるしーちゃんの
姿が飛びこんできて。思わず奇声をあげてしまう。
「おはよ、。ったく、朝一でよくそんな高音ひびか
せられるよね」
呆れたカオさえして、しーちゃんは短く皮肉めいた。
えっと……何でこんなトコにいるの?
いや、ちっちゃい頃からしーちゃんがウチでご飯を食
べるとかは日常なんだけど。
今の私たちって、そんな和やかに食卓を囲める仲じゃ
ないよね?
なのに、どうして。こんなに、いつもと一緒なわけ!?
(もう! 今は会いたくないんだってば!)
ざわついた心を悟られまいと、すぐさま体をUターン
させる。
その瞬間、背中に鋭い声が刺さった。
「ねえ、いいの? 今このタイミングで部屋を出ると、
玄関先でおじ様と鉢合わせるよ。そんなダラシナイ格好
のままじゃ、またお小言くらうんじゃない?」
(う……)
私は視線を下げて、ラベンダー色のパジャマの胸元を
ちょこっと摘んだ。
お休みとはいえ、もう朝の9時半。
レースひらひらの完全ナイトウェアに、ツインテール
姿なんて、たしかに……。
来客中のお父さんには、絶対に見せられない。
「それにさ、元旦の来賓客へのあいさつも、仕事の言い
訳つけて回避したでしょ。おじ様、相当ご機嫌悪かった
よ。ここは『イイコちゃん』のふりして、僕とゴハン食
べてた方が得策だと思うけど」
「…………」
「頭つかいなよ。じゃないとおば様が、いつまでたって
もご実家から戻れない」
「!?」
しーちゃんに背中を向けたまま、反論もできずにグッ
と唇をかんだ。
私の性格を悔しいくらいに理解して、なおかつウチの
事情を私よりもずっと把握してる人。
今は……勝ち目ない。
指示に従うしかなくて、しぶしぶ向かいの座布団に腰
を下ろした。
でも話をする気なんてナイんだからね!
拒絶オーラを思いっきり出して、目も合わせないまま
無言で箸をとる。
そんな私を数秒静かに見おろして、しーちゃんはわざ
とらしく「ふぅ」とため息をついた。
「携帯、着拒してるでしょ? どういうつもり? 僕も
年末年始は超多忙だから、この時間しか会いにこれない
んだけど」
「べ……別に……」
クリスマスの一件を電話で済まされるのがイヤだから、
着信拒否してたわけじゃない。
何も知りたくないんだもん。
早乙女さんとお見合いのはずが、何でしーちゃんと
『婚約』って話に変わったのか。
蒼くんと恋人になった私を、しーちゃんがどんな目で
見てるのか。そういうの全部……。
けど向き合った時点で、あるていど覚悟はできてた。
何を言われても驚いたり、傷ついたりしてやらないって。
威圧感に負けまいと、小さく呼吸を整えて睨みつける。
そんな私の心情とは裏腹に、しーちゃんは腹立たしい
ほどマイペースだった。
で、小皿の沢庵をポリポリかじりながら、予想外のセ
リフを吐いたの。
「今夜の奈良橋さんのガードだけど、僕が変わるからさ。
いいよ。蒼とデートしてきて」
「へっ?」
何を言われたのか理解できなくて、間抜けな声をあげ
てしまった。
たしかに今夜は、蒼くんの番で。
だから夜中の電話だけはしようねって……。
「つき合い初めってさ、毎日会っても飽き足りないんだ
よね。なんて初カレだし、尚更でしょ」
ふわりと揺れる前髪からのぞく瞳は、あまりにも平穏。
発せられる音は、ブレがなく伸びやか。
「だからイイよ。楽しんできなよ。正月休みが終わった
ら、またOLやってもらわなきゃだし。おじ様の方は上
手くやっとくから、羽のばしておいで」
「…………」
あっ気にとられるしかなかった。
こんな風に応えてくれることを期待してたはずだけど、
しっくりいかない。違和感と不信感でいっぱいになる。
(……なに、考えてるのよ)
その無関心さっていうか、余裕は何なわけ?
だって私と蒼くんがキスしてるとこ見た時は、あんな
に不機嫌そうだったじゃない。
もう怒ってないの?
っていうか、仮にも婚約者になったんだよね?
だったらもっと、それらしい言葉があってもイイと思
うのに。
そういうのどーでもいいくせに、私と結婚しようなん
て決めたの?
うぅっ……イライラする。
心の中にグルグルと渦が巻いて、頭が熱い。
そんな私におかまいなく、しーちゃんは台本を読むみ
たいにスラスラと話を続ける。
「――で、今後のスケジュールだけどさ。テスト期間中
の10日間は、盲腸にでもなったとかで職場に届け出し
て。その後の春休みを彼女のガードに専念ってコトで……」
ダンッ!!
私はテーブルを両手で力強く叩いて、たんたんと喋る
しーちゃんを遮った。
「何よ……ソレ……」
ムカつく。
サラッと受け流すとかぜんぜん無理で、中腰のままテー
ブルに体重をかけて、噛みつくみたいにすごんだ。
「何、って? それはこっちのセリフじゃん」
しーちゃんは私を一瞥し、しれっとした顔で再びお箸
を持つ手を動かす。
「別に。春休み全部つぶせとは言ってないよ。前半でカ
タをつけるつもりだし。このまま妖力者の尻尾をつかめ
なきゃ、撤退も考える。難しいことは強いてないと思う
けど」
「そうじゃないよ!」
「……じゃあ。なに、怒ってんの?」
「!?」
あー、もう! しーちゃんこそ!
何をのん気に、だし巻き玉子とか頬張っちゃってんの
よ!!
「柏原! いる!?」
八つ当たり気味に執事をよびつけて、私は例のエンゲー
ジリングを持ってくるように命じた。
そして手元に届くや否や、投げつけたい衝動をグッと
我慢して、しーちゃんの胸の前に突きつける。
「持って帰ってよね、コレ」
世間では一応、『愛の証』だと思うの。
それをクリスマスに引き続き、2回も拒否されたんだ
から。うん、ほら。もっと傷ついてくれても、良さそう
なもんなのに。
やっと手をとめたしーちゃんは顔を歪めることなく、
「ああ、コレね」なんて、まるでガムを貰うみたいに指
先だけで受け取る。
「!! ……なんで、そんなに普通なの? アッサリし
てるの?」
沈着冷静な態度が憎たらしくて、拳をつくってまたテ
ーブルを叩いてしまった。
「けっきょくしーちゃんにとって私は、ただ天力者の姫
でしかないんだよね!?」
前かがみになったパジャマの襟口から、蒼くんにもら
っていらい肌身離さずつけていたネックレスが、勢いあ
まって外に飛びだした。
シャラシャラと左右に揺れる、銀色の蝶。
それにフッと視線を注いだあと、しーちゃんは頬杖を
ついてアイスバーンみたいな目で私を見つめる。
「それ以上の何かを、は僕に望むわけ?」
抑揚のない声が、久しぶりに怖かった。
「あ……」
ハッと我に返って、慌てて顔をそむける。
……本当だ。
私ってば何を求めて、こんな台詞を口にしちゃったん
だろう……。
心が波立つ理由が見つからなくて、しばらく俯くしか
できない。
しーちゃんと私は周囲に創りあげられて育った、兄弟
みたいな幼なじみ。
その関係を疑ったことなんて、一度もないのに。
<<前へ 3話へ>>