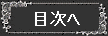◆ 7.不可解な熱 in car
朱理に圧倒されて剣先で触れることさえもできなかったあの日から2週間。
朝はメイクの時間を短縮して、夜は蒼くんとのデートを早めに切り上げて、私は柏原に剣の稽古をつけてもらってる。
休み時間だってムダになんかしてないよ。どれだけ素早く気を集めて、天力を廻らせられるか試してみたり。
とにかくこんなに頑張ったことはない! っていうくらい、能力を高めたくて必死だった。
奈良ちゃんを助けたい。朱理を浄化しなきゃいけない。
そうするにはまだまだ力が足りなくて…………。
 「やっと、天子としての自覚が芽生えたか」
日課になった朝稽古が終わって、出勤の準備も整った7時30分。
静かな朝食の席で、お父さんは厳しく目を細めて私を見つめた。
「八純、お前の狙いは当たりだったな。を最前に立たせる事で自己の力と立場を見直させるという」
「ふふ。オレそんな偉そうなこと言いましたっけ?」
八純はいったんお箸を動かす手を休め、黙々と俯きながら隣りでご飯を食べていた私の顔をふわりと覗き込む。
「でも姉さん近頃すごく頑張ってると思う。オーラの量も急に増したかな? 柏原も褒めてたんだ、今までになく心技体が揃ってるって」
「ホント……?」
「うん、姉さんは磨けば光る原石みたいな人なんだから。稽古を続けて経験を積めば、オレと同等の天力を扱える存在になるよ。本当はずっと頼りにしてるんだ」
柔らかい笑みと共に、ポンッと肩を叩かれた。
常にストイックな八純が認めてくれたのが嬉しい。私は視線を少しだけ上げる。
このまま頑張れば、誰かに守られなくても闘えるだけの力がつくのかな?
そしたら朱理を浄化して、妖力者を排除して。もしかしたら自由に…………。
「ふん。いつまで続くか」
私の淡い期待を嘲るみたいに、お父さんは冷たい声で一蹴した。
「中途半端に首を突っ込んで、その身が危険に晒されれば元も子もなかろう。の役目は子孫を残すことだけだ。多くの天力者を輩出することだけが、
宗家におけるお前の存在価値。それ以上は何も望まぬ。仕事も稽古も程々で構わない。大学など早々に辞め、紫己との間に早く子供を設けよ」
…………いつも同じ。
お父さんは何をやっても私にそれしか言ってくれない。
「私は……っ」
「――姉さん、この出汁巻き玉子、半分食べる? 好物だったよな」
反発心を抑えきれずに身を乗り出しかけた私を、八純はお父さんに気づかれないように左手を伸ばして止めた。
「帆立の貝柱と海苔が入った、少し甘めのヤツ。家政婦の清子さんに頼んで出してもらったんだ。お母さんの唯一の得意料理、そろそろ姉さんも恋しくなっただろうなって」
「あ……」
『お母さん』という言葉を出されて、私はフッと冷静さを取り戻す。
クリスマスイブの外泊をこっそり許してくれて、共犯者になったことでお父さんの怒りをかってしまったお母さん。
もう2ヶ月近く会ってない。鎌倉のお家に電話して元気なことは確認したのだけど……。
罪悪感からまた俯いてしまった私に気づくと、八純は目だけで笑んで庇うように私に背を向けた。
そして前方に向かって強気な声を投げる。
「ああ、そう言えば父さん。お母さんはいつ戻られます? 来月の三者面談の日程も確認したいので、迎えに行くのでしたらオレも一緒に行きますよ」
お父さんはちょっと不機嫌そうに視線を逸らし「お前に任せる」とだけ返した。
あ、うそ。お母さんの帰宅の許可出たの? これで戻ってこれる……?
浮き立つ気持ちを抑えて八純のシャツの背中をぎゅっと掴むと、後ろ手でそっとピースを作ってくれた。
ありがとう。何かあるといつも突破口を開いてくれるよね。
頼りになる弟を素直に尊敬しつつその強さが羨ましくて、一人で立ち向かうことのできない自分に歯がゆさを感じた。
「いってきます」
いつものようにお勝手口から外に出て、まず最初に青白い冬の空を見上げた。
雪が降りそうなくらい寒いこんな日は、せっかくのやる気をちょっぴり挫かせる。
長い髪をサイドに一つに束ねてOLモードに切り替えた。
奈良ちゃんの仕事場に潜入したのが12月。そろそろ結果を出さなきゃいけないよね……。
深いため息を1つだけ落として、私は東門へと回る。
そして道場の入口付近で、石段に座っていたしーちゃんを見つけた。
「おはよう、」
しーちゃんは私に気づくと持っていたスマホの画面から視線を上げ、立ち上がってパンツについた砂を叩いた。
黒っぽいコーデュロイに、上はシャツとアーガイルの白いセーター。ずいぶん薄着だったから車で来たんだって分かる。
「……おはよ」
半径1m以内まで近づいてきてからやっと、私は億劫そうに挨拶を返した。
しーちゃんが黒縁の眼鏡をかけると眼光が強まる気がして、何も言われてないのに責められてるような気になるの。
私のことを待ってた……んだよね。
そう分かったけどわざと目を合わさないようにしてた。
さっさと立ち去りたくて施錠された門扉に指をかけると、しーちゃんは私の手首をグイッと掴んで外に出るのを制する。
「中央線人身事故で上り完全ストップだって」
「え?」
「裏に車回してあるから乗りなよ。9時出勤でしょ? ちょうど仕事で新宿通るからさ、送ってく」
「ちょっと、まっ……」
戸惑う私にお構いなしで、そのまま道場横の駐車場へと引っぱっていく。
久しぶりに強引。そりゃあ今までなら「ラッキー」くらいに思って、喜んで助手席に乗りこむよ。
だけど……今は特にしーちゃんには甘えたくなくて、足を突っ張って反抗する。
立ち止まった私をしーちゃんは面倒くさそうに振り返って、ため息交じりに言葉を投げた。
「何、それ。蒼と付き合ったら、僕の車に乗るのもダメなわけ?」
「違う、そんなんじゃないもん。ただ……」
こういうのもまた、頼ることになっちゃうでしょ?
しーちゃんがいなくても1人でこなせる事を証明したい。「やるじゃん」って「一人前だね」って認めてもらいたいの。
「私は電車で1人でいけるから。しーちゃんはもう仕事に向かってよ」
そうぴしゃりと撥ね付けて手を振りほどいてみたけれど――。
「!」
朝稽古で天力を使い過ぎたせいか、踵を返した途端にフラッと立ち眩んでしまった。
「!」
崩れた上半身を咄嗟にしーちゃんが抱きかかえてくれる。
あ……またやっちゃった……。
動かない体を疎ましく思いながらなす術もなく身を預けていると、「ちょっと痩せた?」って低い声が降る。
「ゴハンちゃんと食べてるの? 急激に稽古量増やしたりしてムリしすぎなんだよ。満員電車で倒れて他人に迷惑かけて、わざわざ僕の仕事を増やしたいーって言うなら、
この手を離してもいいけど?」
相変わらずの毒舌。
でも――そんな心配そうなカオで言わないでよ。
「…………」
切ない気持ちで唇を結んでいると、しーちゃんは私が持っていたトートバッグを無言で自分に肩掛けし、私の背中を抱えるみたいに駐車場へと押した。
有無を言わさない強引な腕だけど、ちゃんと歩幅を気にして歩いてくれてるのが分かる。
温もりは変わらない。何だかんだ言っても、やっぱり私のことをよく分かってるの。
ありがとうって笑顔を返すこともできないくらい、いつの間にか開いた距離をもどかしく思った。
小っちゃい頃から導いてくれてた大きなこの手が、ほら、今はこんなに遠い。
「やっと、天子としての自覚が芽生えたか」
日課になった朝稽古が終わって、出勤の準備も整った7時30分。
静かな朝食の席で、お父さんは厳しく目を細めて私を見つめた。
「八純、お前の狙いは当たりだったな。を最前に立たせる事で自己の力と立場を見直させるという」
「ふふ。オレそんな偉そうなこと言いましたっけ?」
八純はいったんお箸を動かす手を休め、黙々と俯きながら隣りでご飯を食べていた私の顔をふわりと覗き込む。
「でも姉さん近頃すごく頑張ってると思う。オーラの量も急に増したかな? 柏原も褒めてたんだ、今までになく心技体が揃ってるって」
「ホント……?」
「うん、姉さんは磨けば光る原石みたいな人なんだから。稽古を続けて経験を積めば、オレと同等の天力を扱える存在になるよ。本当はずっと頼りにしてるんだ」
柔らかい笑みと共に、ポンッと肩を叩かれた。
常にストイックな八純が認めてくれたのが嬉しい。私は視線を少しだけ上げる。
このまま頑張れば、誰かに守られなくても闘えるだけの力がつくのかな?
そしたら朱理を浄化して、妖力者を排除して。もしかしたら自由に…………。
「ふん。いつまで続くか」
私の淡い期待を嘲るみたいに、お父さんは冷たい声で一蹴した。
「中途半端に首を突っ込んで、その身が危険に晒されれば元も子もなかろう。の役目は子孫を残すことだけだ。多くの天力者を輩出することだけが、
宗家におけるお前の存在価値。それ以上は何も望まぬ。仕事も稽古も程々で構わない。大学など早々に辞め、紫己との間に早く子供を設けよ」
…………いつも同じ。
お父さんは何をやっても私にそれしか言ってくれない。
「私は……っ」
「――姉さん、この出汁巻き玉子、半分食べる? 好物だったよな」
反発心を抑えきれずに身を乗り出しかけた私を、八純はお父さんに気づかれないように左手を伸ばして止めた。
「帆立の貝柱と海苔が入った、少し甘めのヤツ。家政婦の清子さんに頼んで出してもらったんだ。お母さんの唯一の得意料理、そろそろ姉さんも恋しくなっただろうなって」
「あ……」
『お母さん』という言葉を出されて、私はフッと冷静さを取り戻す。
クリスマスイブの外泊をこっそり許してくれて、共犯者になったことでお父さんの怒りをかってしまったお母さん。
もう2ヶ月近く会ってない。鎌倉のお家に電話して元気なことは確認したのだけど……。
罪悪感からまた俯いてしまった私に気づくと、八純は目だけで笑んで庇うように私に背を向けた。
そして前方に向かって強気な声を投げる。
「ああ、そう言えば父さん。お母さんはいつ戻られます? 来月の三者面談の日程も確認したいので、迎えに行くのでしたらオレも一緒に行きますよ」
お父さんはちょっと不機嫌そうに視線を逸らし「お前に任せる」とだけ返した。
あ、うそ。お母さんの帰宅の許可出たの? これで戻ってこれる……?
浮き立つ気持ちを抑えて八純のシャツの背中をぎゅっと掴むと、後ろ手でそっとピースを作ってくれた。
ありがとう。何かあるといつも突破口を開いてくれるよね。
頼りになる弟を素直に尊敬しつつその強さが羨ましくて、一人で立ち向かうことのできない自分に歯がゆさを感じた。
「いってきます」
いつものようにお勝手口から外に出て、まず最初に青白い冬の空を見上げた。
雪が降りそうなくらい寒いこんな日は、せっかくのやる気をちょっぴり挫かせる。
長い髪をサイドに一つに束ねてOLモードに切り替えた。
奈良ちゃんの仕事場に潜入したのが12月。そろそろ結果を出さなきゃいけないよね……。
深いため息を1つだけ落として、私は東門へと回る。
そして道場の入口付近で、石段に座っていたしーちゃんを見つけた。
「おはよう、」
しーちゃんは私に気づくと持っていたスマホの画面から視線を上げ、立ち上がってパンツについた砂を叩いた。
黒っぽいコーデュロイに、上はシャツとアーガイルの白いセーター。ずいぶん薄着だったから車で来たんだって分かる。
「……おはよ」
半径1m以内まで近づいてきてからやっと、私は億劫そうに挨拶を返した。
しーちゃんが黒縁の眼鏡をかけると眼光が強まる気がして、何も言われてないのに責められてるような気になるの。
私のことを待ってた……んだよね。
そう分かったけどわざと目を合わさないようにしてた。
さっさと立ち去りたくて施錠された門扉に指をかけると、しーちゃんは私の手首をグイッと掴んで外に出るのを制する。
「中央線人身事故で上り完全ストップだって」
「え?」
「裏に車回してあるから乗りなよ。9時出勤でしょ? ちょうど仕事で新宿通るからさ、送ってく」
「ちょっと、まっ……」
戸惑う私にお構いなしで、そのまま道場横の駐車場へと引っぱっていく。
久しぶりに強引。そりゃあ今までなら「ラッキー」くらいに思って、喜んで助手席に乗りこむよ。
だけど……今は特にしーちゃんには甘えたくなくて、足を突っ張って反抗する。
立ち止まった私をしーちゃんは面倒くさそうに振り返って、ため息交じりに言葉を投げた。
「何、それ。蒼と付き合ったら、僕の車に乗るのもダメなわけ?」
「違う、そんなんじゃないもん。ただ……」
こういうのもまた、頼ることになっちゃうでしょ?
しーちゃんがいなくても1人でこなせる事を証明したい。「やるじゃん」って「一人前だね」って認めてもらいたいの。
「私は電車で1人でいけるから。しーちゃんはもう仕事に向かってよ」
そうぴしゃりと撥ね付けて手を振りほどいてみたけれど――。
「!」
朝稽古で天力を使い過ぎたせいか、踵を返した途端にフラッと立ち眩んでしまった。
「!」
崩れた上半身を咄嗟にしーちゃんが抱きかかえてくれる。
あ……またやっちゃった……。
動かない体を疎ましく思いながらなす術もなく身を預けていると、「ちょっと痩せた?」って低い声が降る。
「ゴハンちゃんと食べてるの? 急激に稽古量増やしたりしてムリしすぎなんだよ。満員電車で倒れて他人に迷惑かけて、わざわざ僕の仕事を増やしたいーって言うなら、
この手を離してもいいけど?」
相変わらずの毒舌。
でも――そんな心配そうなカオで言わないでよ。
「…………」
切ない気持ちで唇を結んでいると、しーちゃんは私が持っていたトートバッグを無言で自分に肩掛けし、私の背中を抱えるみたいに駐車場へと押した。
有無を言わさない強引な腕だけど、ちゃんと歩幅を気にして歩いてくれてるのが分かる。
温もりは変わらない。何だかんだ言っても、やっぱり私のことをよく分かってるの。
ありがとうって笑顔を返すこともできないくらい、いつの間にか開いた距離をもどかしく思った。
小っちゃい頃から導いてくれてた大きなこの手が、ほら、今はこんなに遠い。
 車の中は微かにサンダルウッドの香りがして、しーちゃんの好きなUVERworldの曲がかかってる。
目新しい小物が増えてるわけじゃないし、座席の位置とか大きく変わってるわけでもない。
なのにしーちゃんと噛み合ってないだけで慣れ親しんでるはずの車内が居心地悪くて、シートベルトにさえ息苦しさを感じた。
「コート脱げば?」
落ちつかないで何度も足を組み直す私に気づいて、しーちゃんは人差し指で後部座席に置くように促した。
「ううん。別に大丈夫」
「顔、赤いけど?」
「いいの。気にしないで。どうせすぐ着くし」
「あ、そう」
そう突き放したように言いながらも、エアコンの温度を下げてくれる。
私は会話を避けるように窓の外ばかり見てた。
でもね、しーちゃんがどんな風に運転してるのか不思議なくらい分かるの。
左手でサウンドパネルを弄って、たまに前髪をかきあげて。信号が赤になって止まるとハンドルに重心をかけて前方を覗きこんだりする癖。
「あぁ、そう言えばこれどうぞ。まだ空けてないから」
少しして思い出したみたいに、ペットボトルに入ったミルクティーを差し出してくれた。
「……。いただきます」
ちょうど喉がカラカラだったから、素直に受けとってコクンと飲む。
甘い…………。
しーちゃんはこんなの好きじゃないから、これも私の為なんだ。
気づくともう、新宿の街中を走っていた。
ガラス越しに見える朝一番の繁華街は色も光もなくて、まるですっぴんみたいに新鮮。
何気なく視線をのばすと、ピンク色ののぼりに2月14日の文字を見つけた。
あっ、そういえば今度の土曜日じゃない?
蒼くんとの初めてのバレンタインだっていうのに、何かそれどころじゃない自分が悲しい。
手の届かないものに憧れる子供みたいに、私は指先を噛みながら窓の外をぼんやりと眺めていた。
「で、どうなの? 今月に入ってからの奈良ちゃんの動きはさ」
オフィス街に続く交差点を左折したところで、しーちゃんはふと仕事の話を持ってくる。
「うん……変わりないよ。毎日ちょっとずつ、妖力がチラついてるのが見えるんだけど。憑依されてるって感じはしなくて、記憶も意思もしっかり奈良ちゃんなの」
「んー……あれ?」
「え?」
「僕、憑依の可能性があるって、に説明したっけ?」
「!?」
しーちゃんが鋭い視線をぶつけてきて、私はビクッと体を揺らす。
いけない! これは朱理に教えてもらったことだった。
祟峻かもしれない妖力者と接近したなんて知られたら、奈良ちゃんのガードから外されちゃうかもしれない。
それだけは避けたくて、私は平静を装って口角をあげる。
「蒼くんと、話してたの! そういうのも考えられるって」
「ふ〜ん。一応、口止めしといたんだけどね。が無茶しないように」
「えぇ、そうなの!?」
蒼くんゴメンナサイ……。
心の中で手を合わせていると、しーちゃんは次に予想もしてなかった事を聞いてきた。
「そう言えばさ、奈良ちゃんの好きな男ってどんなヤツなわけ? は面識あるんでしょ?」
「!!」
しーちゃんの口から朱理の話題が出るとは思わなくて、今度は動揺を隠しきれなかった。
何であいつのコトなんか気にするの? まさかどこかで会ったりした?
ううん、それはナイ! しーちゃんが朱理と鉢合わせたんなら、みすみす逃すようなことはしないはずだもの。
「なんか……軽い人だよ。見かけカワイイから、笑顔に騙されがちなんだけど」
朱理の存在を知られたくなくて、重要な部分は省いて答える。
「軽いって? どんなふう?」
「どんなって……すぐにベタベタしてきたり、口も上手な感じかなぁ。そんでもって本気でもない女の子や、その友達とかにまでキスとか出来ちゃう人で……」
当たり障りのない部分を説明したつもりなのに、しーちゃんはちょっと怒ったように眉を顰めると、ハザードをたいて道路脇に車を止めた。
かけていた眼鏡を外してダッシュボードに無造作におく。
そして窓の淵に肘をかけて頬杖をつくと、首だけで振り返って冷ややかな目をした。
「あのさ、どういうシチュでそこまで分かっちゃうわけ?」
「へ?」
「キスされたんだ、そいつに」
「な! 別にそんなんじゃ……」
「前にも忠告したよね、奈良ちゃんの男に気に入られるような事だけは避けなって」
「分かってるよ、違うもん。気に入られたとかそんなんじゃないもんっ」
「だったら何でそんな状況になるわけ? ガードする為に近づいといて、自身が彼女の精神的不安要素になったら、妖力に支配されやすくなるって事ぐらい分かるでしょ?」
分かってるよ、朱理にも言われた。嫉妬や劣等っていう感情が奈良ちゃんの心を曇らせてるんだって。
もおっ!! だから何? どうすればいいのよ。しーちゃんなんて何も知らないくせに!
頭ごなしのお説教はあの日からの頑張りを全否定されてるみたいで、悲しさと苛立ちで爆発しそうだった。
「じゃあね! 私もう行くから!」
シートベルトを乱暴に外し、吐き捨てるように叫んだ。
でも車のドアに指をかけたところで、カチャンって運転席からロックをかけられる。
「ちょっと、何?」
反射的にさらなる苛立ちを露わにした瞬間、頭がガクッと大きく揺れて宙に浮いた気がした。
次にすぐ身体の半分に重みがかかって、私の視界はしーちゃんでいっぱいになる。
シートを倒されて上から抑えつけられてることに、少ししてから気付いた。
顔が近い……。
サラッと落ちてきたしーちゃんの髪が私の頬をくすぐって、息がかかるほど近づいたキレイな口元に不覚にもドクンと胸が鳴った。
車の中は微かにサンダルウッドの香りがして、しーちゃんの好きなUVERworldの曲がかかってる。
目新しい小物が増えてるわけじゃないし、座席の位置とか大きく変わってるわけでもない。
なのにしーちゃんと噛み合ってないだけで慣れ親しんでるはずの車内が居心地悪くて、シートベルトにさえ息苦しさを感じた。
「コート脱げば?」
落ちつかないで何度も足を組み直す私に気づいて、しーちゃんは人差し指で後部座席に置くように促した。
「ううん。別に大丈夫」
「顔、赤いけど?」
「いいの。気にしないで。どうせすぐ着くし」
「あ、そう」
そう突き放したように言いながらも、エアコンの温度を下げてくれる。
私は会話を避けるように窓の外ばかり見てた。
でもね、しーちゃんがどんな風に運転してるのか不思議なくらい分かるの。
左手でサウンドパネルを弄って、たまに前髪をかきあげて。信号が赤になって止まるとハンドルに重心をかけて前方を覗きこんだりする癖。
「あぁ、そう言えばこれどうぞ。まだ空けてないから」
少しして思い出したみたいに、ペットボトルに入ったミルクティーを差し出してくれた。
「……。いただきます」
ちょうど喉がカラカラだったから、素直に受けとってコクンと飲む。
甘い…………。
しーちゃんはこんなの好きじゃないから、これも私の為なんだ。
気づくともう、新宿の街中を走っていた。
ガラス越しに見える朝一番の繁華街は色も光もなくて、まるですっぴんみたいに新鮮。
何気なく視線をのばすと、ピンク色ののぼりに2月14日の文字を見つけた。
あっ、そういえば今度の土曜日じゃない?
蒼くんとの初めてのバレンタインだっていうのに、何かそれどころじゃない自分が悲しい。
手の届かないものに憧れる子供みたいに、私は指先を噛みながら窓の外をぼんやりと眺めていた。
「で、どうなの? 今月に入ってからの奈良ちゃんの動きはさ」
オフィス街に続く交差点を左折したところで、しーちゃんはふと仕事の話を持ってくる。
「うん……変わりないよ。毎日ちょっとずつ、妖力がチラついてるのが見えるんだけど。憑依されてるって感じはしなくて、記憶も意思もしっかり奈良ちゃんなの」
「んー……あれ?」
「え?」
「僕、憑依の可能性があるって、に説明したっけ?」
「!?」
しーちゃんが鋭い視線をぶつけてきて、私はビクッと体を揺らす。
いけない! これは朱理に教えてもらったことだった。
祟峻かもしれない妖力者と接近したなんて知られたら、奈良ちゃんのガードから外されちゃうかもしれない。
それだけは避けたくて、私は平静を装って口角をあげる。
「蒼くんと、話してたの! そういうのも考えられるって」
「ふ〜ん。一応、口止めしといたんだけどね。が無茶しないように」
「えぇ、そうなの!?」
蒼くんゴメンナサイ……。
心の中で手を合わせていると、しーちゃんは次に予想もしてなかった事を聞いてきた。
「そう言えばさ、奈良ちゃんの好きな男ってどんなヤツなわけ? は面識あるんでしょ?」
「!!」
しーちゃんの口から朱理の話題が出るとは思わなくて、今度は動揺を隠しきれなかった。
何であいつのコトなんか気にするの? まさかどこかで会ったりした?
ううん、それはナイ! しーちゃんが朱理と鉢合わせたんなら、みすみす逃すようなことはしないはずだもの。
「なんか……軽い人だよ。見かけカワイイから、笑顔に騙されがちなんだけど」
朱理の存在を知られたくなくて、重要な部分は省いて答える。
「軽いって? どんなふう?」
「どんなって……すぐにベタベタしてきたり、口も上手な感じかなぁ。そんでもって本気でもない女の子や、その友達とかにまでキスとか出来ちゃう人で……」
当たり障りのない部分を説明したつもりなのに、しーちゃんはちょっと怒ったように眉を顰めると、ハザードをたいて道路脇に車を止めた。
かけていた眼鏡を外してダッシュボードに無造作におく。
そして窓の淵に肘をかけて頬杖をつくと、首だけで振り返って冷ややかな目をした。
「あのさ、どういうシチュでそこまで分かっちゃうわけ?」
「へ?」
「キスされたんだ、そいつに」
「な! 別にそんなんじゃ……」
「前にも忠告したよね、奈良ちゃんの男に気に入られるような事だけは避けなって」
「分かってるよ、違うもん。気に入られたとかそんなんじゃないもんっ」
「だったら何でそんな状況になるわけ? ガードする為に近づいといて、自身が彼女の精神的不安要素になったら、妖力に支配されやすくなるって事ぐらい分かるでしょ?」
分かってるよ、朱理にも言われた。嫉妬や劣等っていう感情が奈良ちゃんの心を曇らせてるんだって。
もおっ!! だから何? どうすればいいのよ。しーちゃんなんて何も知らないくせに!
頭ごなしのお説教はあの日からの頑張りを全否定されてるみたいで、悲しさと苛立ちで爆発しそうだった。
「じゃあね! 私もう行くから!」
シートベルトを乱暴に外し、吐き捨てるように叫んだ。
でも車のドアに指をかけたところで、カチャンって運転席からロックをかけられる。
「ちょっと、何?」
反射的にさらなる苛立ちを露わにした瞬間、頭がガクッと大きく揺れて宙に浮いた気がした。
次にすぐ身体の半分に重みがかかって、私の視界はしーちゃんでいっぱいになる。
シートを倒されて上から抑えつけられてることに、少ししてから気付いた。
顔が近い……。
サラッと落ちてきたしーちゃんの髪が私の頬をくすぐって、息がかかるほど近づいたキレイな口元に不覚にもドクンと胸が鳴った。
 「はさ、自分の事を分かってなさすぎだよ。いつも無防備で、隙だらけで。だから会ったばかりの男にも簡単につけ込まれたりするんだ」
表情の読みとれない彫刻みたいな顔で、しーちゃんは薄く笑う。
「ほら今だって、こんなに簡単に組み敷かれて」
「な……によ。これはしーちゃんだから……」
「僕だから何? だったら尚更、警戒しとかなきゃダメなんじゃないの? これでも一応、の政略結婚の相手なんだけど」
「!」
ちょっと熱っぽい瞳。いつもと違う低く甘い声。
しーちゃんの色っぽさを怖いと感じたのは初めてで、意識した途端になぜか躰が火照っていくのを止められなかった。
横から私に覆いかぶさった体勢で黙って見下ろしながら、しーちゃんは右手をスッと伸ばして私の下唇を親指で撫でた。
何なの? 知らない男の人みたいに。
これじゃあまるで、しーちゃんに迫られてるみたいじゃない。
戸惑って。動けなくて。壊れそうなくらい心臓が鼓動していた。
しーちゃんが肌に触れることも、体温を直に感じることも慣れっこのはずなのに。
この突き刺さすような視線が今日はすごくイヤ。
威圧的なくせに小さなものを愛でるみたいに穏やかで、簡単に跳ね除けることができないの。
息が苦しい……。
精一杯の抵抗として顔を外に背けると、しーちゃんは肩を大きく跳ねさせてから伸ばしていた手で空を切った。
そしてその後、驚くくらいあっさり私の躰を解放して、「行ってらっしゃい」なんて何事もなかったように姿勢を正したの。
ロックが解除される。同時に、後部座席に置いてあったトートバッグが私の膝へと戻された。
「……?……」
急に自由を取り戻した私はよけい頭が混乱する。
今の……何だったのかな? まだ気持ちがが落ちつかない。
びっくりしたんだよ! キスされるのかもって勘違いした。しーちゃんに限ってそんなわけないのに――。
「っ……」
ドキドキさせられたのが悔しくて、私は無言で車のドアを開けた。
「あ、」
けど、もう一度だけ手首を掴まれて引き戻される。
「今日も、蒼と待ち合わせしてる?」
「な……だったら何?」
「今夜おじ様は八純と出雲に公務で、帰宅の予定ないからさ。遅くなるなら僕が柏原に伝えとく。思う存分、楽しんできても大丈夫だよ」
「!?」
バンッ!!!
私は何も返さずに車を飛びだし、音をたてて扉を閉めた。
こんな状況でも蒼くんとの事を見逃してくれる、その思考が理解不能。
応援してもらうのをずっと望んでた。
でもさっきまで婚約者だとか豪語しておいて、今度は「楽しんできなよ」って、味方なの? 敵なの?
素直に喜べないのは、しーちゃんの気持ちが読めないからだ。
カッカした頭のまま早歩きでオフィスの玄関口に向かう。
中央線の遅れでみんなの出勤に影響が出ているせいか、ホールにいつもの人の流れはなかった。
少し先まで視線をのばすと、西武線で通う奈良ちゃんの姿を発見。
「おはよう!」
波立っていた感情は自然と落ちつき、私は口元を緩めながら彼女を呼び止める。
高い声をあげて、いつもみたいに手を振りかえしてくれるものだと思ってた。
なのに奈良ちゃんはこちらを一瞥しただけで、足を止めずにそのままエレベーターの方へと進んでいってしまったの。
あれ? 気づいたよね?
らしくない反応に焦って、彼女の元へ慌てて駆け寄る。
「おはよう。今日も寒いね!」
「……」
「奈良……ちゃん?」
「は早いんやね。電車大丈夫やったん? 動かないからって、課長からメール入っててんけど」
「あ、うん。私はどうにか――」
「朝帰りしとったから?」
「!」
振向いた奈良ちゃんの目が今まで見たことないくらい冷たくて、驚いて体が硬直した。
肩に届かない髪をサラリと揺らし、彼女は私から再び視線をそらして次の言葉を放つ。
「白のレクサス、紫己くんやろ?」
「え?」
「あの程度のスモークじゃ丸見えやで。もっと気をつけた方がええんとちゃう」
「あ……」
さっきの……車の中でしーちゃんに倒された所を、見られてた?
軽蔑するような目に、有り得ないことを誤解されてるってすぐに分かった。
「あの、違う、あれはねっ」
とにかく否定したくて言葉を繋げようとするけど、奈良ちゃんはそのチャンスを与えてくれない。
「他人のプライベートにとやかく言うつもりはないんやけど、そーいうのどーなん? 『そうくん』っていうカレシおるんやろ?
2人の関係とかあんたの常識とか、そんなん全部ひっくるめて大目に見ても、紫己くんを都合のイイように使うとか一般的に許されへんで」
突き放したようにそう言うと、プイッと顔を背ける奈良ちゃん。
そんなんじゃないの! ってちゃんと言い訳したいけど、私自身も理解できないさっきのシーンを、この場でうまく説明できるわけもなくて……。
ただ茫然とした気持ちで、彼女の隙のない後ろ姿を見つめる。
そしてその背中に毒々しい妖力が溢れ出てるのに気づいたんだ。
「!?」
色でいうなら群所色。
怒りと悲しみをいっぱい含んだ混沌とした妖気が、器の内に納まりきれずにじわじわと外部に漏れ出てるように見える。
これが……憑依?
喰われているのとはあきらかに違う。妖力者の魂と奈良ちゃんの躰がシンクロしてるって表現が近いかもしれない。
『アンタ達で言う――レベル4? 完全憑依できた時、奈良ちゃんはもう人間の姿をしただけの妖力者ってわけ』
朱理の言葉が脳裏をよぎり背筋が凍った。まさに、あと一歩のところまで来てる気がするの。
どうしてこんなに急速に? 私のせいで? それともアイツが……。
不安と嫌疑に急き立てられた私は彼女の正面に駆け回ると、咄嗟にエレベーターに乗るのを両手を広げて阻止した。
「ねえ、先週朱理に会ったんだよね? その時何を話したの? 何か特別なことはなかった? 例えば私についてとか……」
思わず口をついた責めるような問いかけに、自分でヤバイって思った時にはもう手遅れだった。
「何で朱理と2人っきりの時に、の話題で盛り上がんなきゃあかんの!? ちょっと自分、勘違いしすぎなんちゃう?」
「……あっ……」
「悪いんやけど、もうあんたとはしばらく話したくない!」
「奈良ちゃん……」
絶対的な拒否を叩きつけてエレベーターの中に消える彼女を、私はただ見送るしかなかった。
完璧にこじらせてしまった。
女友達に潔癖主義の奈良ちゃんには、私の中途半端な言動は不愉快だったのかもしれない。
言葉の選択をミスってしまった。そもそも嘘で固めた出逢いだもの、どこかで綻びるのは当然かもしれないね。
でも奈良ちゃんとはそういうの抜きで楽しくて、仕事が終わっても友達でいられることを願ってたの。
近頃、人間関係がさっぱりうまくいかないなあ……。
そうヘコみながら次の便をぼんやり待っていると、マナーモードにし忘れたスマホが馴染みのない音を鳴らした。
プルッ プルプルッ
ショートメール?
通知をタップして画面を開き、目に飛び込んできたメッセージに思わず息をのんだ。
【鏡、そろそろ受け取りにきてイイよ。今夜なんてどうでしょう? 朱理】
タイミング悪すぎ!
どうしたって終わらせなきゃダメなんじゃない。
「はさ、自分の事を分かってなさすぎだよ。いつも無防備で、隙だらけで。だから会ったばかりの男にも簡単につけ込まれたりするんだ」
表情の読みとれない彫刻みたいな顔で、しーちゃんは薄く笑う。
「ほら今だって、こんなに簡単に組み敷かれて」
「な……によ。これはしーちゃんだから……」
「僕だから何? だったら尚更、警戒しとかなきゃダメなんじゃないの? これでも一応、の政略結婚の相手なんだけど」
「!」
ちょっと熱っぽい瞳。いつもと違う低く甘い声。
しーちゃんの色っぽさを怖いと感じたのは初めてで、意識した途端になぜか躰が火照っていくのを止められなかった。
横から私に覆いかぶさった体勢で黙って見下ろしながら、しーちゃんは右手をスッと伸ばして私の下唇を親指で撫でた。
何なの? 知らない男の人みたいに。
これじゃあまるで、しーちゃんに迫られてるみたいじゃない。
戸惑って。動けなくて。壊れそうなくらい心臓が鼓動していた。
しーちゃんが肌に触れることも、体温を直に感じることも慣れっこのはずなのに。
この突き刺さすような視線が今日はすごくイヤ。
威圧的なくせに小さなものを愛でるみたいに穏やかで、簡単に跳ね除けることができないの。
息が苦しい……。
精一杯の抵抗として顔を外に背けると、しーちゃんは肩を大きく跳ねさせてから伸ばしていた手で空を切った。
そしてその後、驚くくらいあっさり私の躰を解放して、「行ってらっしゃい」なんて何事もなかったように姿勢を正したの。
ロックが解除される。同時に、後部座席に置いてあったトートバッグが私の膝へと戻された。
「……?……」
急に自由を取り戻した私はよけい頭が混乱する。
今の……何だったのかな? まだ気持ちがが落ちつかない。
びっくりしたんだよ! キスされるのかもって勘違いした。しーちゃんに限ってそんなわけないのに――。
「っ……」
ドキドキさせられたのが悔しくて、私は無言で車のドアを開けた。
「あ、」
けど、もう一度だけ手首を掴まれて引き戻される。
「今日も、蒼と待ち合わせしてる?」
「な……だったら何?」
「今夜おじ様は八純と出雲に公務で、帰宅の予定ないからさ。遅くなるなら僕が柏原に伝えとく。思う存分、楽しんできても大丈夫だよ」
「!?」
バンッ!!!
私は何も返さずに車を飛びだし、音をたてて扉を閉めた。
こんな状況でも蒼くんとの事を見逃してくれる、その思考が理解不能。
応援してもらうのをずっと望んでた。
でもさっきまで婚約者だとか豪語しておいて、今度は「楽しんできなよ」って、味方なの? 敵なの?
素直に喜べないのは、しーちゃんの気持ちが読めないからだ。
カッカした頭のまま早歩きでオフィスの玄関口に向かう。
中央線の遅れでみんなの出勤に影響が出ているせいか、ホールにいつもの人の流れはなかった。
少し先まで視線をのばすと、西武線で通う奈良ちゃんの姿を発見。
「おはよう!」
波立っていた感情は自然と落ちつき、私は口元を緩めながら彼女を呼び止める。
高い声をあげて、いつもみたいに手を振りかえしてくれるものだと思ってた。
なのに奈良ちゃんはこちらを一瞥しただけで、足を止めずにそのままエレベーターの方へと進んでいってしまったの。
あれ? 気づいたよね?
らしくない反応に焦って、彼女の元へ慌てて駆け寄る。
「おはよう。今日も寒いね!」
「……」
「奈良……ちゃん?」
「は早いんやね。電車大丈夫やったん? 動かないからって、課長からメール入っててんけど」
「あ、うん。私はどうにか――」
「朝帰りしとったから?」
「!」
振向いた奈良ちゃんの目が今まで見たことないくらい冷たくて、驚いて体が硬直した。
肩に届かない髪をサラリと揺らし、彼女は私から再び視線をそらして次の言葉を放つ。
「白のレクサス、紫己くんやろ?」
「え?」
「あの程度のスモークじゃ丸見えやで。もっと気をつけた方がええんとちゃう」
「あ……」
さっきの……車の中でしーちゃんに倒された所を、見られてた?
軽蔑するような目に、有り得ないことを誤解されてるってすぐに分かった。
「あの、違う、あれはねっ」
とにかく否定したくて言葉を繋げようとするけど、奈良ちゃんはそのチャンスを与えてくれない。
「他人のプライベートにとやかく言うつもりはないんやけど、そーいうのどーなん? 『そうくん』っていうカレシおるんやろ?
2人の関係とかあんたの常識とか、そんなん全部ひっくるめて大目に見ても、紫己くんを都合のイイように使うとか一般的に許されへんで」
突き放したようにそう言うと、プイッと顔を背ける奈良ちゃん。
そんなんじゃないの! ってちゃんと言い訳したいけど、私自身も理解できないさっきのシーンを、この場でうまく説明できるわけもなくて……。
ただ茫然とした気持ちで、彼女の隙のない後ろ姿を見つめる。
そしてその背中に毒々しい妖力が溢れ出てるのに気づいたんだ。
「!?」
色でいうなら群所色。
怒りと悲しみをいっぱい含んだ混沌とした妖気が、器の内に納まりきれずにじわじわと外部に漏れ出てるように見える。
これが……憑依?
喰われているのとはあきらかに違う。妖力者の魂と奈良ちゃんの躰がシンクロしてるって表現が近いかもしれない。
『アンタ達で言う――レベル4? 完全憑依できた時、奈良ちゃんはもう人間の姿をしただけの妖力者ってわけ』
朱理の言葉が脳裏をよぎり背筋が凍った。まさに、あと一歩のところまで来てる気がするの。
どうしてこんなに急速に? 私のせいで? それともアイツが……。
不安と嫌疑に急き立てられた私は彼女の正面に駆け回ると、咄嗟にエレベーターに乗るのを両手を広げて阻止した。
「ねえ、先週朱理に会ったんだよね? その時何を話したの? 何か特別なことはなかった? 例えば私についてとか……」
思わず口をついた責めるような問いかけに、自分でヤバイって思った時にはもう手遅れだった。
「何で朱理と2人っきりの時に、の話題で盛り上がんなきゃあかんの!? ちょっと自分、勘違いしすぎなんちゃう?」
「……あっ……」
「悪いんやけど、もうあんたとはしばらく話したくない!」
「奈良ちゃん……」
絶対的な拒否を叩きつけてエレベーターの中に消える彼女を、私はただ見送るしかなかった。
完璧にこじらせてしまった。
女友達に潔癖主義の奈良ちゃんには、私の中途半端な言動は不愉快だったのかもしれない。
言葉の選択をミスってしまった。そもそも嘘で固めた出逢いだもの、どこかで綻びるのは当然かもしれないね。
でも奈良ちゃんとはそういうの抜きで楽しくて、仕事が終わっても友達でいられることを願ってたの。
近頃、人間関係がさっぱりうまくいかないなあ……。
そうヘコみながら次の便をぼんやり待っていると、マナーモードにし忘れたスマホが馴染みのない音を鳴らした。
プルッ プルプルッ
ショートメール?
通知をタップして画面を開き、目に飛び込んできたメッセージに思わず息をのんだ。
【鏡、そろそろ受け取りにきてイイよ。今夜なんてどうでしょう? 朱理】
タイミング悪すぎ!
どうしたって終わらせなきゃダメなんじゃない。
<<前へ 8話へ>>
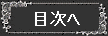
 「やっと、天子としての自覚が芽生えたか」
日課になった朝稽古が終わって、出勤の準備も整った7時30分。
静かな朝食の席で、お父さんは厳しく目を細めて私を見つめた。
「八純、お前の狙いは当たりだったな。を最前に立たせる事で自己の力と立場を見直させるという」
「ふふ。オレそんな偉そうなこと言いましたっけ?」
八純はいったんお箸を動かす手を休め、黙々と俯きながら隣りでご飯を食べていた私の顔をふわりと覗き込む。
「でも姉さん近頃すごく頑張ってると思う。オーラの量も急に増したかな? 柏原も褒めてたんだ、今までになく心技体が揃ってるって」
「ホント……?」
「うん、姉さんは磨けば光る原石みたいな人なんだから。稽古を続けて経験を積めば、オレと同等の天力を扱える存在になるよ。本当はずっと頼りにしてるんだ」
柔らかい笑みと共に、ポンッと肩を叩かれた。
常にストイックな八純が認めてくれたのが嬉しい。私は視線を少しだけ上げる。
このまま頑張れば、誰かに守られなくても闘えるだけの力がつくのかな?
そしたら朱理を浄化して、妖力者を排除して。もしかしたら自由に…………。
「ふん。いつまで続くか」
私の淡い期待を嘲るみたいに、お父さんは冷たい声で一蹴した。
「中途半端に首を突っ込んで、その身が危険に晒されれば元も子もなかろう。の役目は子孫を残すことだけだ。多くの天力者を輩出することだけが、
宗家におけるお前の存在価値。それ以上は何も望まぬ。仕事も稽古も程々で構わない。大学など早々に辞め、紫己との間に早く子供を設けよ」
…………いつも同じ。
お父さんは何をやっても私にそれしか言ってくれない。
「私は……っ」
「――姉さん、この出汁巻き玉子、半分食べる? 好物だったよな」
反発心を抑えきれずに身を乗り出しかけた私を、八純はお父さんに気づかれないように左手を伸ばして止めた。
「帆立の貝柱と海苔が入った、少し甘めのヤツ。家政婦の清子さんに頼んで出してもらったんだ。お母さんの唯一の得意料理、そろそろ姉さんも恋しくなっただろうなって」
「あ……」
『お母さん』という言葉を出されて、私はフッと冷静さを取り戻す。
クリスマスイブの外泊をこっそり許してくれて、共犯者になったことでお父さんの怒りをかってしまったお母さん。
もう2ヶ月近く会ってない。鎌倉のお家に電話して元気なことは確認したのだけど……。
罪悪感からまた俯いてしまった私に気づくと、八純は目だけで笑んで庇うように私に背を向けた。
そして前方に向かって強気な声を投げる。
「ああ、そう言えば父さん。お母さんはいつ戻られます? 来月の三者面談の日程も確認したいので、迎えに行くのでしたらオレも一緒に行きますよ」
お父さんはちょっと不機嫌そうに視線を逸らし「お前に任せる」とだけ返した。
あ、うそ。お母さんの帰宅の許可出たの? これで戻ってこれる……?
浮き立つ気持ちを抑えて八純のシャツの背中をぎゅっと掴むと、後ろ手でそっとピースを作ってくれた。
ありがとう。何かあるといつも突破口を開いてくれるよね。
頼りになる弟を素直に尊敬しつつその強さが羨ましくて、一人で立ち向かうことのできない自分に歯がゆさを感じた。
「いってきます」
いつものようにお勝手口から外に出て、まず最初に青白い冬の空を見上げた。
雪が降りそうなくらい寒いこんな日は、せっかくのやる気をちょっぴり挫かせる。
長い髪をサイドに一つに束ねてOLモードに切り替えた。
奈良ちゃんの仕事場に潜入したのが12月。そろそろ結果を出さなきゃいけないよね……。
深いため息を1つだけ落として、私は東門へと回る。
そして道場の入口付近で、石段に座っていたしーちゃんを見つけた。
「おはよう、」
しーちゃんは私に気づくと持っていたスマホの画面から視線を上げ、立ち上がってパンツについた砂を叩いた。
黒っぽいコーデュロイに、上はシャツとアーガイルの白いセーター。ずいぶん薄着だったから車で来たんだって分かる。
「……おはよ」
半径1m以内まで近づいてきてからやっと、私は億劫そうに挨拶を返した。
しーちゃんが黒縁の眼鏡をかけると眼光が強まる気がして、何も言われてないのに責められてるような気になるの。
私のことを待ってた……んだよね。
そう分かったけどわざと目を合わさないようにしてた。
さっさと立ち去りたくて施錠された門扉に指をかけると、しーちゃんは私の手首をグイッと掴んで外に出るのを制する。
「中央線人身事故で上り完全ストップだって」
「え?」
「裏に車回してあるから乗りなよ。9時出勤でしょ? ちょうど仕事で新宿通るからさ、送ってく」
「ちょっと、まっ……」
戸惑う私にお構いなしで、そのまま道場横の駐車場へと引っぱっていく。
久しぶりに強引。そりゃあ今までなら「ラッキー」くらいに思って、喜んで助手席に乗りこむよ。
だけど……今は特にしーちゃんには甘えたくなくて、足を突っ張って反抗する。
立ち止まった私をしーちゃんは面倒くさそうに振り返って、ため息交じりに言葉を投げた。
「何、それ。蒼と付き合ったら、僕の車に乗るのもダメなわけ?」
「違う、そんなんじゃないもん。ただ……」
こういうのもまた、頼ることになっちゃうでしょ?
しーちゃんがいなくても1人でこなせる事を証明したい。「やるじゃん」って「一人前だね」って認めてもらいたいの。
「私は電車で1人でいけるから。しーちゃんはもう仕事に向かってよ」
そうぴしゃりと撥ね付けて手を振りほどいてみたけれど――。
「!」
朝稽古で天力を使い過ぎたせいか、踵を返した途端にフラッと立ち眩んでしまった。
「!」
崩れた上半身を咄嗟にしーちゃんが抱きかかえてくれる。
あ……またやっちゃった……。
動かない体を疎ましく思いながらなす術もなく身を預けていると、「ちょっと痩せた?」って低い声が降る。
「ゴハンちゃんと食べてるの? 急激に稽古量増やしたりしてムリしすぎなんだよ。満員電車で倒れて他人に迷惑かけて、わざわざ僕の仕事を増やしたいーって言うなら、
この手を離してもいいけど?」
相変わらずの毒舌。
でも――そんな心配そうなカオで言わないでよ。
「…………」
切ない気持ちで唇を結んでいると、しーちゃんは私が持っていたトートバッグを無言で自分に肩掛けし、私の背中を抱えるみたいに駐車場へと押した。
有無を言わさない強引な腕だけど、ちゃんと歩幅を気にして歩いてくれてるのが分かる。
温もりは変わらない。何だかんだ言っても、やっぱり私のことをよく分かってるの。
ありがとうって笑顔を返すこともできないくらい、いつの間にか開いた距離をもどかしく思った。
小っちゃい頃から導いてくれてた大きなこの手が、ほら、今はこんなに遠い。
「やっと、天子としての自覚が芽生えたか」
日課になった朝稽古が終わって、出勤の準備も整った7時30分。
静かな朝食の席で、お父さんは厳しく目を細めて私を見つめた。
「八純、お前の狙いは当たりだったな。を最前に立たせる事で自己の力と立場を見直させるという」
「ふふ。オレそんな偉そうなこと言いましたっけ?」
八純はいったんお箸を動かす手を休め、黙々と俯きながら隣りでご飯を食べていた私の顔をふわりと覗き込む。
「でも姉さん近頃すごく頑張ってると思う。オーラの量も急に増したかな? 柏原も褒めてたんだ、今までになく心技体が揃ってるって」
「ホント……?」
「うん、姉さんは磨けば光る原石みたいな人なんだから。稽古を続けて経験を積めば、オレと同等の天力を扱える存在になるよ。本当はずっと頼りにしてるんだ」
柔らかい笑みと共に、ポンッと肩を叩かれた。
常にストイックな八純が認めてくれたのが嬉しい。私は視線を少しだけ上げる。
このまま頑張れば、誰かに守られなくても闘えるだけの力がつくのかな?
そしたら朱理を浄化して、妖力者を排除して。もしかしたら自由に…………。
「ふん。いつまで続くか」
私の淡い期待を嘲るみたいに、お父さんは冷たい声で一蹴した。
「中途半端に首を突っ込んで、その身が危険に晒されれば元も子もなかろう。の役目は子孫を残すことだけだ。多くの天力者を輩出することだけが、
宗家におけるお前の存在価値。それ以上は何も望まぬ。仕事も稽古も程々で構わない。大学など早々に辞め、紫己との間に早く子供を設けよ」
…………いつも同じ。
お父さんは何をやっても私にそれしか言ってくれない。
「私は……っ」
「――姉さん、この出汁巻き玉子、半分食べる? 好物だったよな」
反発心を抑えきれずに身を乗り出しかけた私を、八純はお父さんに気づかれないように左手を伸ばして止めた。
「帆立の貝柱と海苔が入った、少し甘めのヤツ。家政婦の清子さんに頼んで出してもらったんだ。お母さんの唯一の得意料理、そろそろ姉さんも恋しくなっただろうなって」
「あ……」
『お母さん』という言葉を出されて、私はフッと冷静さを取り戻す。
クリスマスイブの外泊をこっそり許してくれて、共犯者になったことでお父さんの怒りをかってしまったお母さん。
もう2ヶ月近く会ってない。鎌倉のお家に電話して元気なことは確認したのだけど……。
罪悪感からまた俯いてしまった私に気づくと、八純は目だけで笑んで庇うように私に背を向けた。
そして前方に向かって強気な声を投げる。
「ああ、そう言えば父さん。お母さんはいつ戻られます? 来月の三者面談の日程も確認したいので、迎えに行くのでしたらオレも一緒に行きますよ」
お父さんはちょっと不機嫌そうに視線を逸らし「お前に任せる」とだけ返した。
あ、うそ。お母さんの帰宅の許可出たの? これで戻ってこれる……?
浮き立つ気持ちを抑えて八純のシャツの背中をぎゅっと掴むと、後ろ手でそっとピースを作ってくれた。
ありがとう。何かあるといつも突破口を開いてくれるよね。
頼りになる弟を素直に尊敬しつつその強さが羨ましくて、一人で立ち向かうことのできない自分に歯がゆさを感じた。
「いってきます」
いつものようにお勝手口から外に出て、まず最初に青白い冬の空を見上げた。
雪が降りそうなくらい寒いこんな日は、せっかくのやる気をちょっぴり挫かせる。
長い髪をサイドに一つに束ねてOLモードに切り替えた。
奈良ちゃんの仕事場に潜入したのが12月。そろそろ結果を出さなきゃいけないよね……。
深いため息を1つだけ落として、私は東門へと回る。
そして道場の入口付近で、石段に座っていたしーちゃんを見つけた。
「おはよう、」
しーちゃんは私に気づくと持っていたスマホの画面から視線を上げ、立ち上がってパンツについた砂を叩いた。
黒っぽいコーデュロイに、上はシャツとアーガイルの白いセーター。ずいぶん薄着だったから車で来たんだって分かる。
「……おはよ」
半径1m以内まで近づいてきてからやっと、私は億劫そうに挨拶を返した。
しーちゃんが黒縁の眼鏡をかけると眼光が強まる気がして、何も言われてないのに責められてるような気になるの。
私のことを待ってた……んだよね。
そう分かったけどわざと目を合わさないようにしてた。
さっさと立ち去りたくて施錠された門扉に指をかけると、しーちゃんは私の手首をグイッと掴んで外に出るのを制する。
「中央線人身事故で上り完全ストップだって」
「え?」
「裏に車回してあるから乗りなよ。9時出勤でしょ? ちょうど仕事で新宿通るからさ、送ってく」
「ちょっと、まっ……」
戸惑う私にお構いなしで、そのまま道場横の駐車場へと引っぱっていく。
久しぶりに強引。そりゃあ今までなら「ラッキー」くらいに思って、喜んで助手席に乗りこむよ。
だけど……今は特にしーちゃんには甘えたくなくて、足を突っ張って反抗する。
立ち止まった私をしーちゃんは面倒くさそうに振り返って、ため息交じりに言葉を投げた。
「何、それ。蒼と付き合ったら、僕の車に乗るのもダメなわけ?」
「違う、そんなんじゃないもん。ただ……」
こういうのもまた、頼ることになっちゃうでしょ?
しーちゃんがいなくても1人でこなせる事を証明したい。「やるじゃん」って「一人前だね」って認めてもらいたいの。
「私は電車で1人でいけるから。しーちゃんはもう仕事に向かってよ」
そうぴしゃりと撥ね付けて手を振りほどいてみたけれど――。
「!」
朝稽古で天力を使い過ぎたせいか、踵を返した途端にフラッと立ち眩んでしまった。
「!」
崩れた上半身を咄嗟にしーちゃんが抱きかかえてくれる。
あ……またやっちゃった……。
動かない体を疎ましく思いながらなす術もなく身を預けていると、「ちょっと痩せた?」って低い声が降る。
「ゴハンちゃんと食べてるの? 急激に稽古量増やしたりしてムリしすぎなんだよ。満員電車で倒れて他人に迷惑かけて、わざわざ僕の仕事を増やしたいーって言うなら、
この手を離してもいいけど?」
相変わらずの毒舌。
でも――そんな心配そうなカオで言わないでよ。
「…………」
切ない気持ちで唇を結んでいると、しーちゃんは私が持っていたトートバッグを無言で自分に肩掛けし、私の背中を抱えるみたいに駐車場へと押した。
有無を言わさない強引な腕だけど、ちゃんと歩幅を気にして歩いてくれてるのが分かる。
温もりは変わらない。何だかんだ言っても、やっぱり私のことをよく分かってるの。
ありがとうって笑顔を返すこともできないくらい、いつの間にか開いた距離をもどかしく思った。
小っちゃい頃から導いてくれてた大きなこの手が、ほら、今はこんなに遠い。
 車の中は微かにサンダルウッドの香りがして、しーちゃんの好きなUVERworldの曲がかかってる。
目新しい小物が増えてるわけじゃないし、座席の位置とか大きく変わってるわけでもない。
なのにしーちゃんと噛み合ってないだけで慣れ親しんでるはずの車内が居心地悪くて、シートベルトにさえ息苦しさを感じた。
「コート脱げば?」
落ちつかないで何度も足を組み直す私に気づいて、しーちゃんは人差し指で後部座席に置くように促した。
「ううん。別に大丈夫」
「顔、赤いけど?」
「いいの。気にしないで。どうせすぐ着くし」
「あ、そう」
そう突き放したように言いながらも、エアコンの温度を下げてくれる。
私は会話を避けるように窓の外ばかり見てた。
でもね、しーちゃんがどんな風に運転してるのか不思議なくらい分かるの。
左手でサウンドパネルを弄って、たまに前髪をかきあげて。信号が赤になって止まるとハンドルに重心をかけて前方を覗きこんだりする癖。
「あぁ、そう言えばこれどうぞ。まだ空けてないから」
少しして思い出したみたいに、ペットボトルに入ったミルクティーを差し出してくれた。
「……。いただきます」
ちょうど喉がカラカラだったから、素直に受けとってコクンと飲む。
甘い…………。
しーちゃんはこんなの好きじゃないから、これも私の為なんだ。
気づくともう、新宿の街中を走っていた。
ガラス越しに見える朝一番の繁華街は色も光もなくて、まるですっぴんみたいに新鮮。
何気なく視線をのばすと、ピンク色ののぼりに2月14日の文字を見つけた。
あっ、そういえば今度の土曜日じゃない?
蒼くんとの初めてのバレンタインだっていうのに、何かそれどころじゃない自分が悲しい。
手の届かないものに憧れる子供みたいに、私は指先を噛みながら窓の外をぼんやりと眺めていた。
「で、どうなの? 今月に入ってからの奈良ちゃんの動きはさ」
オフィス街に続く交差点を左折したところで、しーちゃんはふと仕事の話を持ってくる。
「うん……変わりないよ。毎日ちょっとずつ、妖力がチラついてるのが見えるんだけど。憑依されてるって感じはしなくて、記憶も意思もしっかり奈良ちゃんなの」
「んー……あれ?」
「え?」
「僕、憑依の可能性があるって、に説明したっけ?」
「!?」
しーちゃんが鋭い視線をぶつけてきて、私はビクッと体を揺らす。
いけない! これは朱理に教えてもらったことだった。
祟峻かもしれない妖力者と接近したなんて知られたら、奈良ちゃんのガードから外されちゃうかもしれない。
それだけは避けたくて、私は平静を装って口角をあげる。
「蒼くんと、話してたの! そういうのも考えられるって」
「ふ〜ん。一応、口止めしといたんだけどね。が無茶しないように」
「えぇ、そうなの!?」
蒼くんゴメンナサイ……。
心の中で手を合わせていると、しーちゃんは次に予想もしてなかった事を聞いてきた。
「そう言えばさ、奈良ちゃんの好きな男ってどんなヤツなわけ? は面識あるんでしょ?」
「!!」
しーちゃんの口から朱理の話題が出るとは思わなくて、今度は動揺を隠しきれなかった。
何であいつのコトなんか気にするの? まさかどこかで会ったりした?
ううん、それはナイ! しーちゃんが朱理と鉢合わせたんなら、みすみす逃すようなことはしないはずだもの。
「なんか……軽い人だよ。見かけカワイイから、笑顔に騙されがちなんだけど」
朱理の存在を知られたくなくて、重要な部分は省いて答える。
「軽いって? どんなふう?」
「どんなって……すぐにベタベタしてきたり、口も上手な感じかなぁ。そんでもって本気でもない女の子や、その友達とかにまでキスとか出来ちゃう人で……」
当たり障りのない部分を説明したつもりなのに、しーちゃんはちょっと怒ったように眉を顰めると、ハザードをたいて道路脇に車を止めた。
かけていた眼鏡を外してダッシュボードに無造作におく。
そして窓の淵に肘をかけて頬杖をつくと、首だけで振り返って冷ややかな目をした。
「あのさ、どういうシチュでそこまで分かっちゃうわけ?」
「へ?」
「キスされたんだ、そいつに」
「な! 別にそんなんじゃ……」
「前にも忠告したよね、奈良ちゃんの男に気に入られるような事だけは避けなって」
「分かってるよ、違うもん。気に入られたとかそんなんじゃないもんっ」
「だったら何でそんな状況になるわけ? ガードする為に近づいといて、自身が彼女の精神的不安要素になったら、妖力に支配されやすくなるって事ぐらい分かるでしょ?」
分かってるよ、朱理にも言われた。嫉妬や劣等っていう感情が奈良ちゃんの心を曇らせてるんだって。
もおっ!! だから何? どうすればいいのよ。しーちゃんなんて何も知らないくせに!
頭ごなしのお説教はあの日からの頑張りを全否定されてるみたいで、悲しさと苛立ちで爆発しそうだった。
「じゃあね! 私もう行くから!」
シートベルトを乱暴に外し、吐き捨てるように叫んだ。
でも車のドアに指をかけたところで、カチャンって運転席からロックをかけられる。
「ちょっと、何?」
反射的にさらなる苛立ちを露わにした瞬間、頭がガクッと大きく揺れて宙に浮いた気がした。
次にすぐ身体の半分に重みがかかって、私の視界はしーちゃんでいっぱいになる。
シートを倒されて上から抑えつけられてることに、少ししてから気付いた。
顔が近い……。
サラッと落ちてきたしーちゃんの髪が私の頬をくすぐって、息がかかるほど近づいたキレイな口元に不覚にもドクンと胸が鳴った。
車の中は微かにサンダルウッドの香りがして、しーちゃんの好きなUVERworldの曲がかかってる。
目新しい小物が増えてるわけじゃないし、座席の位置とか大きく変わってるわけでもない。
なのにしーちゃんと噛み合ってないだけで慣れ親しんでるはずの車内が居心地悪くて、シートベルトにさえ息苦しさを感じた。
「コート脱げば?」
落ちつかないで何度も足を組み直す私に気づいて、しーちゃんは人差し指で後部座席に置くように促した。
「ううん。別に大丈夫」
「顔、赤いけど?」
「いいの。気にしないで。どうせすぐ着くし」
「あ、そう」
そう突き放したように言いながらも、エアコンの温度を下げてくれる。
私は会話を避けるように窓の外ばかり見てた。
でもね、しーちゃんがどんな風に運転してるのか不思議なくらい分かるの。
左手でサウンドパネルを弄って、たまに前髪をかきあげて。信号が赤になって止まるとハンドルに重心をかけて前方を覗きこんだりする癖。
「あぁ、そう言えばこれどうぞ。まだ空けてないから」
少しして思い出したみたいに、ペットボトルに入ったミルクティーを差し出してくれた。
「……。いただきます」
ちょうど喉がカラカラだったから、素直に受けとってコクンと飲む。
甘い…………。
しーちゃんはこんなの好きじゃないから、これも私の為なんだ。
気づくともう、新宿の街中を走っていた。
ガラス越しに見える朝一番の繁華街は色も光もなくて、まるですっぴんみたいに新鮮。
何気なく視線をのばすと、ピンク色ののぼりに2月14日の文字を見つけた。
あっ、そういえば今度の土曜日じゃない?
蒼くんとの初めてのバレンタインだっていうのに、何かそれどころじゃない自分が悲しい。
手の届かないものに憧れる子供みたいに、私は指先を噛みながら窓の外をぼんやりと眺めていた。
「で、どうなの? 今月に入ってからの奈良ちゃんの動きはさ」
オフィス街に続く交差点を左折したところで、しーちゃんはふと仕事の話を持ってくる。
「うん……変わりないよ。毎日ちょっとずつ、妖力がチラついてるのが見えるんだけど。憑依されてるって感じはしなくて、記憶も意思もしっかり奈良ちゃんなの」
「んー……あれ?」
「え?」
「僕、憑依の可能性があるって、に説明したっけ?」
「!?」
しーちゃんが鋭い視線をぶつけてきて、私はビクッと体を揺らす。
いけない! これは朱理に教えてもらったことだった。
祟峻かもしれない妖力者と接近したなんて知られたら、奈良ちゃんのガードから外されちゃうかもしれない。
それだけは避けたくて、私は平静を装って口角をあげる。
「蒼くんと、話してたの! そういうのも考えられるって」
「ふ〜ん。一応、口止めしといたんだけどね。が無茶しないように」
「えぇ、そうなの!?」
蒼くんゴメンナサイ……。
心の中で手を合わせていると、しーちゃんは次に予想もしてなかった事を聞いてきた。
「そう言えばさ、奈良ちゃんの好きな男ってどんなヤツなわけ? は面識あるんでしょ?」
「!!」
しーちゃんの口から朱理の話題が出るとは思わなくて、今度は動揺を隠しきれなかった。
何であいつのコトなんか気にするの? まさかどこかで会ったりした?
ううん、それはナイ! しーちゃんが朱理と鉢合わせたんなら、みすみす逃すようなことはしないはずだもの。
「なんか……軽い人だよ。見かけカワイイから、笑顔に騙されがちなんだけど」
朱理の存在を知られたくなくて、重要な部分は省いて答える。
「軽いって? どんなふう?」
「どんなって……すぐにベタベタしてきたり、口も上手な感じかなぁ。そんでもって本気でもない女の子や、その友達とかにまでキスとか出来ちゃう人で……」
当たり障りのない部分を説明したつもりなのに、しーちゃんはちょっと怒ったように眉を顰めると、ハザードをたいて道路脇に車を止めた。
かけていた眼鏡を外してダッシュボードに無造作におく。
そして窓の淵に肘をかけて頬杖をつくと、首だけで振り返って冷ややかな目をした。
「あのさ、どういうシチュでそこまで分かっちゃうわけ?」
「へ?」
「キスされたんだ、そいつに」
「な! 別にそんなんじゃ……」
「前にも忠告したよね、奈良ちゃんの男に気に入られるような事だけは避けなって」
「分かってるよ、違うもん。気に入られたとかそんなんじゃないもんっ」
「だったら何でそんな状況になるわけ? ガードする為に近づいといて、自身が彼女の精神的不安要素になったら、妖力に支配されやすくなるって事ぐらい分かるでしょ?」
分かってるよ、朱理にも言われた。嫉妬や劣等っていう感情が奈良ちゃんの心を曇らせてるんだって。
もおっ!! だから何? どうすればいいのよ。しーちゃんなんて何も知らないくせに!
頭ごなしのお説教はあの日からの頑張りを全否定されてるみたいで、悲しさと苛立ちで爆発しそうだった。
「じゃあね! 私もう行くから!」
シートベルトを乱暴に外し、吐き捨てるように叫んだ。
でも車のドアに指をかけたところで、カチャンって運転席からロックをかけられる。
「ちょっと、何?」
反射的にさらなる苛立ちを露わにした瞬間、頭がガクッと大きく揺れて宙に浮いた気がした。
次にすぐ身体の半分に重みがかかって、私の視界はしーちゃんでいっぱいになる。
シートを倒されて上から抑えつけられてることに、少ししてから気付いた。
顔が近い……。
サラッと落ちてきたしーちゃんの髪が私の頬をくすぐって、息がかかるほど近づいたキレイな口元に不覚にもドクンと胸が鳴った。
 「はさ、自分の事を分かってなさすぎだよ。いつも無防備で、隙だらけで。だから会ったばかりの男にも簡単につけ込まれたりするんだ」
表情の読みとれない彫刻みたいな顔で、しーちゃんは薄く笑う。
「ほら今だって、こんなに簡単に組み敷かれて」
「な……によ。これはしーちゃんだから……」
「僕だから何? だったら尚更、警戒しとかなきゃダメなんじゃないの? これでも一応、の政略結婚の相手なんだけど」
「!」
ちょっと熱っぽい瞳。いつもと違う低く甘い声。
しーちゃんの色っぽさを怖いと感じたのは初めてで、意識した途端になぜか躰が火照っていくのを止められなかった。
横から私に覆いかぶさった体勢で黙って見下ろしながら、しーちゃんは右手をスッと伸ばして私の下唇を親指で撫でた。
何なの? 知らない男の人みたいに。
これじゃあまるで、しーちゃんに迫られてるみたいじゃない。
戸惑って。動けなくて。壊れそうなくらい心臓が鼓動していた。
しーちゃんが肌に触れることも、体温を直に感じることも慣れっこのはずなのに。
この突き刺さすような視線が今日はすごくイヤ。
威圧的なくせに小さなものを愛でるみたいに穏やかで、簡単に跳ね除けることができないの。
息が苦しい……。
精一杯の抵抗として顔を外に背けると、しーちゃんは肩を大きく跳ねさせてから伸ばしていた手で空を切った。
そしてその後、驚くくらいあっさり私の躰を解放して、「行ってらっしゃい」なんて何事もなかったように姿勢を正したの。
ロックが解除される。同時に、後部座席に置いてあったトートバッグが私の膝へと戻された。
「……?……」
急に自由を取り戻した私はよけい頭が混乱する。
今の……何だったのかな? まだ気持ちがが落ちつかない。
びっくりしたんだよ! キスされるのかもって勘違いした。しーちゃんに限ってそんなわけないのに――。
「っ……」
ドキドキさせられたのが悔しくて、私は無言で車のドアを開けた。
「あ、」
けど、もう一度だけ手首を掴まれて引き戻される。
「今日も、蒼と待ち合わせしてる?」
「な……だったら何?」
「今夜おじ様は八純と出雲に公務で、帰宅の予定ないからさ。遅くなるなら僕が柏原に伝えとく。思う存分、楽しんできても大丈夫だよ」
「!?」
バンッ!!!
私は何も返さずに車を飛びだし、音をたてて扉を閉めた。
こんな状況でも蒼くんとの事を見逃してくれる、その思考が理解不能。
応援してもらうのをずっと望んでた。
でもさっきまで婚約者だとか豪語しておいて、今度は「楽しんできなよ」って、味方なの? 敵なの?
素直に喜べないのは、しーちゃんの気持ちが読めないからだ。
カッカした頭のまま早歩きでオフィスの玄関口に向かう。
中央線の遅れでみんなの出勤に影響が出ているせいか、ホールにいつもの人の流れはなかった。
少し先まで視線をのばすと、西武線で通う奈良ちゃんの姿を発見。
「おはよう!」
波立っていた感情は自然と落ちつき、私は口元を緩めながら彼女を呼び止める。
高い声をあげて、いつもみたいに手を振りかえしてくれるものだと思ってた。
なのに奈良ちゃんはこちらを一瞥しただけで、足を止めずにそのままエレベーターの方へと進んでいってしまったの。
あれ? 気づいたよね?
らしくない反応に焦って、彼女の元へ慌てて駆け寄る。
「おはよう。今日も寒いね!」
「……」
「奈良……ちゃん?」
「は早いんやね。電車大丈夫やったん? 動かないからって、課長からメール入っててんけど」
「あ、うん。私はどうにか――」
「朝帰りしとったから?」
「!」
振向いた奈良ちゃんの目が今まで見たことないくらい冷たくて、驚いて体が硬直した。
肩に届かない髪をサラリと揺らし、彼女は私から再び視線をそらして次の言葉を放つ。
「白のレクサス、紫己くんやろ?」
「え?」
「あの程度のスモークじゃ丸見えやで。もっと気をつけた方がええんとちゃう」
「あ……」
さっきの……車の中でしーちゃんに倒された所を、見られてた?
軽蔑するような目に、有り得ないことを誤解されてるってすぐに分かった。
「あの、違う、あれはねっ」
とにかく否定したくて言葉を繋げようとするけど、奈良ちゃんはそのチャンスを与えてくれない。
「他人のプライベートにとやかく言うつもりはないんやけど、そーいうのどーなん? 『そうくん』っていうカレシおるんやろ?
2人の関係とかあんたの常識とか、そんなん全部ひっくるめて大目に見ても、紫己くんを都合のイイように使うとか一般的に許されへんで」
突き放したようにそう言うと、プイッと顔を背ける奈良ちゃん。
そんなんじゃないの! ってちゃんと言い訳したいけど、私自身も理解できないさっきのシーンを、この場でうまく説明できるわけもなくて……。
ただ茫然とした気持ちで、彼女の隙のない後ろ姿を見つめる。
そしてその背中に毒々しい妖力が溢れ出てるのに気づいたんだ。
「!?」
色でいうなら群所色。
怒りと悲しみをいっぱい含んだ混沌とした妖気が、器の内に納まりきれずにじわじわと外部に漏れ出てるように見える。
これが……憑依?
喰われているのとはあきらかに違う。妖力者の魂と奈良ちゃんの躰がシンクロしてるって表現が近いかもしれない。
『アンタ達で言う――レベル4? 完全憑依できた時、奈良ちゃんはもう人間の姿をしただけの妖力者ってわけ』
朱理の言葉が脳裏をよぎり背筋が凍った。まさに、あと一歩のところまで来てる気がするの。
どうしてこんなに急速に? 私のせいで? それともアイツが……。
不安と嫌疑に急き立てられた私は彼女の正面に駆け回ると、咄嗟にエレベーターに乗るのを両手を広げて阻止した。
「ねえ、先週朱理に会ったんだよね? その時何を話したの? 何か特別なことはなかった? 例えば私についてとか……」
思わず口をついた責めるような問いかけに、自分でヤバイって思った時にはもう手遅れだった。
「何で朱理と2人っきりの時に、の話題で盛り上がんなきゃあかんの!? ちょっと自分、勘違いしすぎなんちゃう?」
「……あっ……」
「悪いんやけど、もうあんたとはしばらく話したくない!」
「奈良ちゃん……」
絶対的な拒否を叩きつけてエレベーターの中に消える彼女を、私はただ見送るしかなかった。
完璧にこじらせてしまった。
女友達に潔癖主義の奈良ちゃんには、私の中途半端な言動は不愉快だったのかもしれない。
言葉の選択をミスってしまった。そもそも嘘で固めた出逢いだもの、どこかで綻びるのは当然かもしれないね。
でも奈良ちゃんとはそういうの抜きで楽しくて、仕事が終わっても友達でいられることを願ってたの。
近頃、人間関係がさっぱりうまくいかないなあ……。
そうヘコみながら次の便をぼんやり待っていると、マナーモードにし忘れたスマホが馴染みのない音を鳴らした。
プルッ プルプルッ
ショートメール?
通知をタップして画面を開き、目に飛び込んできたメッセージに思わず息をのんだ。
【鏡、そろそろ受け取りにきてイイよ。今夜なんてどうでしょう? 朱理】
タイミング悪すぎ!
どうしたって終わらせなきゃダメなんじゃない。
「はさ、自分の事を分かってなさすぎだよ。いつも無防備で、隙だらけで。だから会ったばかりの男にも簡単につけ込まれたりするんだ」
表情の読みとれない彫刻みたいな顔で、しーちゃんは薄く笑う。
「ほら今だって、こんなに簡単に組み敷かれて」
「な……によ。これはしーちゃんだから……」
「僕だから何? だったら尚更、警戒しとかなきゃダメなんじゃないの? これでも一応、の政略結婚の相手なんだけど」
「!」
ちょっと熱っぽい瞳。いつもと違う低く甘い声。
しーちゃんの色っぽさを怖いと感じたのは初めてで、意識した途端になぜか躰が火照っていくのを止められなかった。
横から私に覆いかぶさった体勢で黙って見下ろしながら、しーちゃんは右手をスッと伸ばして私の下唇を親指で撫でた。
何なの? 知らない男の人みたいに。
これじゃあまるで、しーちゃんに迫られてるみたいじゃない。
戸惑って。動けなくて。壊れそうなくらい心臓が鼓動していた。
しーちゃんが肌に触れることも、体温を直に感じることも慣れっこのはずなのに。
この突き刺さすような視線が今日はすごくイヤ。
威圧的なくせに小さなものを愛でるみたいに穏やかで、簡単に跳ね除けることができないの。
息が苦しい……。
精一杯の抵抗として顔を外に背けると、しーちゃんは肩を大きく跳ねさせてから伸ばしていた手で空を切った。
そしてその後、驚くくらいあっさり私の躰を解放して、「行ってらっしゃい」なんて何事もなかったように姿勢を正したの。
ロックが解除される。同時に、後部座席に置いてあったトートバッグが私の膝へと戻された。
「……?……」
急に自由を取り戻した私はよけい頭が混乱する。
今の……何だったのかな? まだ気持ちがが落ちつかない。
びっくりしたんだよ! キスされるのかもって勘違いした。しーちゃんに限ってそんなわけないのに――。
「っ……」
ドキドキさせられたのが悔しくて、私は無言で車のドアを開けた。
「あ、」
けど、もう一度だけ手首を掴まれて引き戻される。
「今日も、蒼と待ち合わせしてる?」
「な……だったら何?」
「今夜おじ様は八純と出雲に公務で、帰宅の予定ないからさ。遅くなるなら僕が柏原に伝えとく。思う存分、楽しんできても大丈夫だよ」
「!?」
バンッ!!!
私は何も返さずに車を飛びだし、音をたてて扉を閉めた。
こんな状況でも蒼くんとの事を見逃してくれる、その思考が理解不能。
応援してもらうのをずっと望んでた。
でもさっきまで婚約者だとか豪語しておいて、今度は「楽しんできなよ」って、味方なの? 敵なの?
素直に喜べないのは、しーちゃんの気持ちが読めないからだ。
カッカした頭のまま早歩きでオフィスの玄関口に向かう。
中央線の遅れでみんなの出勤に影響が出ているせいか、ホールにいつもの人の流れはなかった。
少し先まで視線をのばすと、西武線で通う奈良ちゃんの姿を発見。
「おはよう!」
波立っていた感情は自然と落ちつき、私は口元を緩めながら彼女を呼び止める。
高い声をあげて、いつもみたいに手を振りかえしてくれるものだと思ってた。
なのに奈良ちゃんはこちらを一瞥しただけで、足を止めずにそのままエレベーターの方へと進んでいってしまったの。
あれ? 気づいたよね?
らしくない反応に焦って、彼女の元へ慌てて駆け寄る。
「おはよう。今日も寒いね!」
「……」
「奈良……ちゃん?」
「は早いんやね。電車大丈夫やったん? 動かないからって、課長からメール入っててんけど」
「あ、うん。私はどうにか――」
「朝帰りしとったから?」
「!」
振向いた奈良ちゃんの目が今まで見たことないくらい冷たくて、驚いて体が硬直した。
肩に届かない髪をサラリと揺らし、彼女は私から再び視線をそらして次の言葉を放つ。
「白のレクサス、紫己くんやろ?」
「え?」
「あの程度のスモークじゃ丸見えやで。もっと気をつけた方がええんとちゃう」
「あ……」
さっきの……車の中でしーちゃんに倒された所を、見られてた?
軽蔑するような目に、有り得ないことを誤解されてるってすぐに分かった。
「あの、違う、あれはねっ」
とにかく否定したくて言葉を繋げようとするけど、奈良ちゃんはそのチャンスを与えてくれない。
「他人のプライベートにとやかく言うつもりはないんやけど、そーいうのどーなん? 『そうくん』っていうカレシおるんやろ?
2人の関係とかあんたの常識とか、そんなん全部ひっくるめて大目に見ても、紫己くんを都合のイイように使うとか一般的に許されへんで」
突き放したようにそう言うと、プイッと顔を背ける奈良ちゃん。
そんなんじゃないの! ってちゃんと言い訳したいけど、私自身も理解できないさっきのシーンを、この場でうまく説明できるわけもなくて……。
ただ茫然とした気持ちで、彼女の隙のない後ろ姿を見つめる。
そしてその背中に毒々しい妖力が溢れ出てるのに気づいたんだ。
「!?」
色でいうなら群所色。
怒りと悲しみをいっぱい含んだ混沌とした妖気が、器の内に納まりきれずにじわじわと外部に漏れ出てるように見える。
これが……憑依?
喰われているのとはあきらかに違う。妖力者の魂と奈良ちゃんの躰がシンクロしてるって表現が近いかもしれない。
『アンタ達で言う――レベル4? 完全憑依できた時、奈良ちゃんはもう人間の姿をしただけの妖力者ってわけ』
朱理の言葉が脳裏をよぎり背筋が凍った。まさに、あと一歩のところまで来てる気がするの。
どうしてこんなに急速に? 私のせいで? それともアイツが……。
不安と嫌疑に急き立てられた私は彼女の正面に駆け回ると、咄嗟にエレベーターに乗るのを両手を広げて阻止した。
「ねえ、先週朱理に会ったんだよね? その時何を話したの? 何か特別なことはなかった? 例えば私についてとか……」
思わず口をついた責めるような問いかけに、自分でヤバイって思った時にはもう手遅れだった。
「何で朱理と2人っきりの時に、の話題で盛り上がんなきゃあかんの!? ちょっと自分、勘違いしすぎなんちゃう?」
「……あっ……」
「悪いんやけど、もうあんたとはしばらく話したくない!」
「奈良ちゃん……」
絶対的な拒否を叩きつけてエレベーターの中に消える彼女を、私はただ見送るしかなかった。
完璧にこじらせてしまった。
女友達に潔癖主義の奈良ちゃんには、私の中途半端な言動は不愉快だったのかもしれない。
言葉の選択をミスってしまった。そもそも嘘で固めた出逢いだもの、どこかで綻びるのは当然かもしれないね。
でも奈良ちゃんとはそういうの抜きで楽しくて、仕事が終わっても友達でいられることを願ってたの。
近頃、人間関係がさっぱりうまくいかないなあ……。
そうヘコみながら次の便をぼんやり待っていると、マナーモードにし忘れたスマホが馴染みのない音を鳴らした。
プルッ プルプルッ
ショートメール?
通知をタップして画面を開き、目に飛び込んできたメッセージに思わず息をのんだ。
【鏡、そろそろ受け取りにきてイイよ。今夜なんてどうでしょう? 朱理】
タイミング悪すぎ!
どうしたって終わらせなきゃダメなんじゃない。