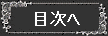◇ 8―①.それぞれの想い 〜 紫己 〜
僕のことをあからさまに避けてるくせに他のヤツとキス云々なんて話するから、ちょっと脅かしてやろうって思った。
なのにってば、目を潤ませながら睨み付けてきたりしてさ。
頭を撫でてればそれで済んだ幼いお姫様がどんどん『女』になってく気がして、先に反応したのは僕の方だった。
ヤバイね。
距離を置かれるのが寂しいなんて言えない。
言えない分だけイラつく。
『REAL』の撮影現場でフラッシュを浴びながら、僕は車内でのとのやりとりばかり思い出していた。
 「シキ、それじゃあ商品が霞む! もっと前面に出して」
「あ、はい」
編集部に隣接してる地下スタジオ。
馴染みのカメラマンに珍しく叱咤されて、集中できてないことに気づく。
カメアシが申し訳なさそうに頭を下げて、僕のしていたタグホイヤーの位置を微調整した。
再びシャッターが切られる。
パシャパシャと心地良い音が響くたびにいくつもポーズを変えてみせるけど、納得のいく絵が撮れていないのかレンズ越しにもう一度声をかけられた。
「何か動き固いよ! 次号の特集は『腕時計は男の印象を決める』だろ? もっと手にこう色気っての出して!」
「色気、う〜ん……こんな感じ?」
要求に答えようと手の動きを確認して、不意にまた今朝のことを思い出してしまった。
この腕でを押し倒して、この指であの唇に触れたんだっけ。
温もりと柔らかい感触がまだ残ってる。こんなに近くに感じたのはどれくらいぶりだろう。
「シキ、それじゃあ商品が霞む! もっと前面に出して」
「あ、はい」
編集部に隣接してる地下スタジオ。
馴染みのカメラマンに珍しく叱咤されて、集中できてないことに気づく。
カメアシが申し訳なさそうに頭を下げて、僕のしていたタグホイヤーの位置を微調整した。
再びシャッターが切られる。
パシャパシャと心地良い音が響くたびにいくつもポーズを変えてみせるけど、納得のいく絵が撮れていないのかレンズ越しにもう一度声をかけられた。
「何か動き固いよ! 次号の特集は『腕時計は男の印象を決める』だろ? もっと手にこう色気っての出して!」
「色気、う〜ん……こんな感じ?」
要求に答えようと手の動きを確認して、不意にまた今朝のことを思い出してしまった。
この腕でを押し倒して、この指であの唇に触れたんだっけ。
温もりと柔らかい感触がまだ残ってる。こんなに近くに感じたのはどれくらいぶりだろう。
 あんなにそばにいたのに、家族でも恋人でもない僕たちの関係は案外脆い。
の結婚相手に立候補したことを喜んでもらえるとは思ってなかったけど、結局は何となく流されて受け入れるんじゃないかって思ってた。
2回もリングを突き返されるなんて、さすがに笑えない。
もし蒼と付き合ってなかったら――あの時に一線を越えてさえいなかったら――間に合ったんだろうか。
よく考えなよ。僕の隣だけがセーフティーエリアなんじゃないの?
大学を卒業するまでちゃんと待つし、子孫繁栄のためだけにを囲ったりしない。
ファッションも食事もこれからの生き方そのものも、出来るだけ選ばせてあげたいって思ってる。
他の誰と一緒になっても、血統という赤い鎖がずっとを縛り付けるんだ。
重くて窮屈でにとっては煩わしいだけのそれを、僕だけが華やかなアクセサリーに変えてあげられるのに。
でもは僕の手をとらなかった。
今更悔やんでも仕方ないけど、その程度の存在なんだって思い知らされる。
僕がいなきゃダメだって何で分かんないわけ?
だから自分に向けられる笑顔を失ってでも、これから先のの自由を守るって決めた。
守る……? カッコつけすぎかぁ。
疎まれてでも離してやるもんか! って、意固地になってるだけかもしれない。
あんなにそばにいたのに、家族でも恋人でもない僕たちの関係は案外脆い。
の結婚相手に立候補したことを喜んでもらえるとは思ってなかったけど、結局は何となく流されて受け入れるんじゃないかって思ってた。
2回もリングを突き返されるなんて、さすがに笑えない。
もし蒼と付き合ってなかったら――あの時に一線を越えてさえいなかったら――間に合ったんだろうか。
よく考えなよ。僕の隣だけがセーフティーエリアなんじゃないの?
大学を卒業するまでちゃんと待つし、子孫繁栄のためだけにを囲ったりしない。
ファッションも食事もこれからの生き方そのものも、出来るだけ選ばせてあげたいって思ってる。
他の誰と一緒になっても、血統という赤い鎖がずっとを縛り付けるんだ。
重くて窮屈でにとっては煩わしいだけのそれを、僕だけが華やかなアクセサリーに変えてあげられるのに。
でもは僕の手をとらなかった。
今更悔やんでも仕方ないけど、その程度の存在なんだって思い知らされる。
僕がいなきゃダメだって何で分かんないわけ?
だから自分に向けられる笑顔を失ってでも、これから先のの自由を守るって決めた。
守る……? カッコつけすぎかぁ。
疎まれてでも離してやるもんか! って、意固地になってるだけかもしれない。
 ボンネットに体を横に投げ出して、見えない何かを掴むみたいに左手を伸ばす。
でも遠い…………。
片手を差し出すだけじゃもう絶対、に届くことはないんだろうね。
でも本気で両手を広げてもそこに飛び込んでもらえなかったら、僕は一体どうなるんだろう。
それを考えるのは少し怖いよ。
引き寄せた手首に口づける真似をした時、カメラのフラッシュが激しく音を響かせた。
やっとOKの声がかかって、僕は安堵の息を漏らす。
「シキくんお疲れ様です! 最後のカオすっごくセクシーで、なのにピュアで、とっても良かったですよ〜。これであたし達アラフォー女子の心は確実に掴みましたって!!」
休憩に入ってすぐ、現場入りしていた担当エディターの樹(たつき)さんが賑やかに駆け寄ったきた。
黒いパンツスーツにセミロングの黒髪を後ろで1本にまとめ、トレードマークの赤ふちの眼鏡をかけた彼女はファッション雑誌の編集部にいるのが不思議なくらい地味。
だけど発想が半端なく派手で、僕を読モからカバーモデルまで引き上げてくれたのも彼女だった。
もう6年の付き合いになる。
ボンネットに体を横に投げ出して、見えない何かを掴むみたいに左手を伸ばす。
でも遠い…………。
片手を差し出すだけじゃもう絶対、に届くことはないんだろうね。
でも本気で両手を広げてもそこに飛び込んでもらえなかったら、僕は一体どうなるんだろう。
それを考えるのは少し怖いよ。
引き寄せた手首に口づける真似をした時、カメラのフラッシュが激しく音を響かせた。
やっとOKの声がかかって、僕は安堵の息を漏らす。
「シキくんお疲れ様です! 最後のカオすっごくセクシーで、なのにピュアで、とっても良かったですよ〜。これであたし達アラフォー女子の心は確実に掴みましたって!!」
休憩に入ってすぐ、現場入りしていた担当エディターの樹(たつき)さんが賑やかに駆け寄ったきた。
黒いパンツスーツにセミロングの黒髪を後ろで1本にまとめ、トレードマークの赤ふちの眼鏡をかけた彼女はファッション雑誌の編集部にいるのが不思議なくらい地味。
だけど発想が半端なく派手で、僕を読モからカバーモデルまで引き上げてくれたのも彼女だった。
もう6年の付き合いになる。
 「『アラフォー女子の心』ってさぁ、メンズ雑誌じゃん。ウチ。どーなのよ、それ」
苦笑いを返すと、樹さんは目をキラキラさせながら僕を見上げて「いいんです、いいんです!」と表情をさらに明るくした。
「あたし達は妄想をカテに生きてるんで!」
「……はい?」
「流れ始めたんですよ〜、年末に撮ったカルペスウォーターのCMが。もう反響も上がってきてるみたいで、これで来月号でシキくんがバーンっとアピールしてくれれば、
メンズ雑誌だろうが何だろうがとりあえず女子は表紙買いするはずです!」
「とりあえずって……」
チーフリーダーの樹さんらしからぬ台詞に思わず乾いた笑いを零すけど、彼女がわりと真剣な眼差しを向けるから、これも戦略なんだろうなって理解した。
「今年の『REAL』の平均売り上げ目標7万部だっけ? 正直、厳しいよね」
「はい、そうです。だからシキくんには今年1年で顔と名前を売ってもらって、ウチの雑誌をもっと世間に広めて欲しいんです!」
「ゴメン。CMを引き受けるのでギリだよ。これ以上スケジュールは埋められない」
「分かってます。でも出来ることはやってもらわなきゃ生き残れません。『REAL』の看板はあなたなんですから」
「…………」
雑誌が売れない時代だって言われてる。
特にうちみたいな正統派ファッション誌は、どこかで変革が必要なんだ。
そのタイミングに僕が居合わせたなら、やはりココでも覚悟を決めなきゃならない。
「うん、頑張るよ。樹さんには親孝行しなきゃだしね」
「シキくん♥ せめて『姉孝行』でお願いします」
樹さんの飾りっ気のないヘラッとした笑顔は、僕の心のモヤさえも静かに消し去ってくれた。
「あ、そう言えばコレ良かったらどうですか? シキくん前に余ったら欲しいって言ってましたよね」
少しして彼女は手持ちのバッグから、アナスイのパーティー券を取り出した。
新作を宣伝するためにマスコミや出版社、VIPの為にひらかれるファッションショー。が好きそうだなって思って頼んでおいたヤツだ。
「ありがとう。でも確かこれって――」
「はい……そうなんです。今夜なんですよ、突然ですみません」
7時スタートか。仕事はお互い間に合うけど、今の感じだとたぶんは誘っても来ない。
かと言って他の女の子に声をかけるのも、色んな意味で気がひける。
もういらないかな……。
そう思って受け取るのをいったん躊躇うけど、ふと、僕とじゃなければ喜んで行くんじゃない? って気づいた。
蒼に渡せばイイ。
「樹さん、コレ友達に譲っても平気?」
「え? あ、はい。シキくんのご友人なら大丈夫です」
「助かる。じゃあ有難く頂くね」
お礼どうしよっか――って問いかけると、彼女は口角をあげて首を振り「土曜日の撮影も全力でお願いします!!」とだけ言った。
その日はたしか朝8時から横浜ロケで、5月号の初夏マリン特集。
天気予報には雪マークがついてたっけ。
「『アラフォー女子の心』ってさぁ、メンズ雑誌じゃん。ウチ。どーなのよ、それ」
苦笑いを返すと、樹さんは目をキラキラさせながら僕を見上げて「いいんです、いいんです!」と表情をさらに明るくした。
「あたし達は妄想をカテに生きてるんで!」
「……はい?」
「流れ始めたんですよ〜、年末に撮ったカルペスウォーターのCMが。もう反響も上がってきてるみたいで、これで来月号でシキくんがバーンっとアピールしてくれれば、
メンズ雑誌だろうが何だろうがとりあえず女子は表紙買いするはずです!」
「とりあえずって……」
チーフリーダーの樹さんらしからぬ台詞に思わず乾いた笑いを零すけど、彼女がわりと真剣な眼差しを向けるから、これも戦略なんだろうなって理解した。
「今年の『REAL』の平均売り上げ目標7万部だっけ? 正直、厳しいよね」
「はい、そうです。だからシキくんには今年1年で顔と名前を売ってもらって、ウチの雑誌をもっと世間に広めて欲しいんです!」
「ゴメン。CMを引き受けるのでギリだよ。これ以上スケジュールは埋められない」
「分かってます。でも出来ることはやってもらわなきゃ生き残れません。『REAL』の看板はあなたなんですから」
「…………」
雑誌が売れない時代だって言われてる。
特にうちみたいな正統派ファッション誌は、どこかで変革が必要なんだ。
そのタイミングに僕が居合わせたなら、やはりココでも覚悟を決めなきゃならない。
「うん、頑張るよ。樹さんには親孝行しなきゃだしね」
「シキくん♥ せめて『姉孝行』でお願いします」
樹さんの飾りっ気のないヘラッとした笑顔は、僕の心のモヤさえも静かに消し去ってくれた。
「あ、そう言えばコレ良かったらどうですか? シキくん前に余ったら欲しいって言ってましたよね」
少しして彼女は手持ちのバッグから、アナスイのパーティー券を取り出した。
新作を宣伝するためにマスコミや出版社、VIPの為にひらかれるファッションショー。が好きそうだなって思って頼んでおいたヤツだ。
「ありがとう。でも確かこれって――」
「はい……そうなんです。今夜なんですよ、突然ですみません」
7時スタートか。仕事はお互い間に合うけど、今の感じだとたぶんは誘っても来ない。
かと言って他の女の子に声をかけるのも、色んな意味で気がひける。
もういらないかな……。
そう思って受け取るのをいったん躊躇うけど、ふと、僕とじゃなければ喜んで行くんじゃない? って気づいた。
蒼に渡せばイイ。
「樹さん、コレ友達に譲っても平気?」
「え? あ、はい。シキくんのご友人なら大丈夫です」
「助かる。じゃあ有難く頂くね」
お礼どうしよっか――って問いかけると、彼女は口角をあげて首を振り「土曜日の撮影も全力でお願いします!!」とだけ言った。
その日はたしか朝8時から横浜ロケで、5月号の初夏マリン特集。
天気予報には雪マークがついてたっけ。
<<前へ 次へ>>
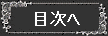
 「シキ、それじゃあ商品が霞む! もっと前面に出して」
「あ、はい」
編集部に隣接してる地下スタジオ。
馴染みのカメラマンに珍しく叱咤されて、集中できてないことに気づく。
カメアシが申し訳なさそうに頭を下げて、僕のしていたタグホイヤーの位置を微調整した。
再びシャッターが切られる。
パシャパシャと心地良い音が響くたびにいくつもポーズを変えてみせるけど、納得のいく絵が撮れていないのかレンズ越しにもう一度声をかけられた。
「何か動き固いよ! 次号の特集は『腕時計は男の印象を決める』だろ? もっと手にこう色気っての出して!」
「色気、う〜ん……こんな感じ?」
要求に答えようと手の動きを確認して、不意にまた今朝のことを思い出してしまった。
この腕でを押し倒して、この指であの唇に触れたんだっけ。
温もりと柔らかい感触がまだ残ってる。こんなに近くに感じたのはどれくらいぶりだろう。
「シキ、それじゃあ商品が霞む! もっと前面に出して」
「あ、はい」
編集部に隣接してる地下スタジオ。
馴染みのカメラマンに珍しく叱咤されて、集中できてないことに気づく。
カメアシが申し訳なさそうに頭を下げて、僕のしていたタグホイヤーの位置を微調整した。
再びシャッターが切られる。
パシャパシャと心地良い音が響くたびにいくつもポーズを変えてみせるけど、納得のいく絵が撮れていないのかレンズ越しにもう一度声をかけられた。
「何か動き固いよ! 次号の特集は『腕時計は男の印象を決める』だろ? もっと手にこう色気っての出して!」
「色気、う〜ん……こんな感じ?」
要求に答えようと手の動きを確認して、不意にまた今朝のことを思い出してしまった。
この腕でを押し倒して、この指であの唇に触れたんだっけ。
温もりと柔らかい感触がまだ残ってる。こんなに近くに感じたのはどれくらいぶりだろう。
 あんなにそばにいたのに、家族でも恋人でもない僕たちの関係は案外脆い。
の結婚相手に立候補したことを喜んでもらえるとは思ってなかったけど、結局は何となく流されて受け入れるんじゃないかって思ってた。
2回もリングを突き返されるなんて、さすがに笑えない。
もし蒼と付き合ってなかったら――あの時に一線を越えてさえいなかったら――間に合ったんだろうか。
よく考えなよ。僕の隣だけがセーフティーエリアなんじゃないの?
大学を卒業するまでちゃんと待つし、子孫繁栄のためだけにを囲ったりしない。
ファッションも食事もこれからの生き方そのものも、出来るだけ選ばせてあげたいって思ってる。
他の誰と一緒になっても、血統という赤い鎖がずっとを縛り付けるんだ。
重くて窮屈でにとっては煩わしいだけのそれを、僕だけが華やかなアクセサリーに変えてあげられるのに。
でもは僕の手をとらなかった。
今更悔やんでも仕方ないけど、その程度の存在なんだって思い知らされる。
僕がいなきゃダメだって何で分かんないわけ?
だから自分に向けられる笑顔を失ってでも、これから先のの自由を守るって決めた。
守る……? カッコつけすぎかぁ。
疎まれてでも離してやるもんか! って、意固地になってるだけかもしれない。
あんなにそばにいたのに、家族でも恋人でもない僕たちの関係は案外脆い。
の結婚相手に立候補したことを喜んでもらえるとは思ってなかったけど、結局は何となく流されて受け入れるんじゃないかって思ってた。
2回もリングを突き返されるなんて、さすがに笑えない。
もし蒼と付き合ってなかったら――あの時に一線を越えてさえいなかったら――間に合ったんだろうか。
よく考えなよ。僕の隣だけがセーフティーエリアなんじゃないの?
大学を卒業するまでちゃんと待つし、子孫繁栄のためだけにを囲ったりしない。
ファッションも食事もこれからの生き方そのものも、出来るだけ選ばせてあげたいって思ってる。
他の誰と一緒になっても、血統という赤い鎖がずっとを縛り付けるんだ。
重くて窮屈でにとっては煩わしいだけのそれを、僕だけが華やかなアクセサリーに変えてあげられるのに。
でもは僕の手をとらなかった。
今更悔やんでも仕方ないけど、その程度の存在なんだって思い知らされる。
僕がいなきゃダメだって何で分かんないわけ?
だから自分に向けられる笑顔を失ってでも、これから先のの自由を守るって決めた。
守る……? カッコつけすぎかぁ。
疎まれてでも離してやるもんか! って、意固地になってるだけかもしれない。
 ボンネットに体を横に投げ出して、見えない何かを掴むみたいに左手を伸ばす。
でも遠い…………。
片手を差し出すだけじゃもう絶対、に届くことはないんだろうね。
でも本気で両手を広げてもそこに飛び込んでもらえなかったら、僕は一体どうなるんだろう。
それを考えるのは少し怖いよ。
引き寄せた手首に口づける真似をした時、カメラのフラッシュが激しく音を響かせた。
やっとOKの声がかかって、僕は安堵の息を漏らす。
「シキくんお疲れ様です! 最後のカオすっごくセクシーで、なのにピュアで、とっても良かったですよ〜。これであたし達アラフォー女子の心は確実に掴みましたって!!」
休憩に入ってすぐ、現場入りしていた担当エディターの樹(たつき)さんが賑やかに駆け寄ったきた。
黒いパンツスーツにセミロングの黒髪を後ろで1本にまとめ、トレードマークの赤ふちの眼鏡をかけた彼女はファッション雑誌の編集部にいるのが不思議なくらい地味。
だけど発想が半端なく派手で、僕を読モからカバーモデルまで引き上げてくれたのも彼女だった。
もう6年の付き合いになる。
ボンネットに体を横に投げ出して、見えない何かを掴むみたいに左手を伸ばす。
でも遠い…………。
片手を差し出すだけじゃもう絶対、に届くことはないんだろうね。
でも本気で両手を広げてもそこに飛び込んでもらえなかったら、僕は一体どうなるんだろう。
それを考えるのは少し怖いよ。
引き寄せた手首に口づける真似をした時、カメラのフラッシュが激しく音を響かせた。
やっとOKの声がかかって、僕は安堵の息を漏らす。
「シキくんお疲れ様です! 最後のカオすっごくセクシーで、なのにピュアで、とっても良かったですよ〜。これであたし達アラフォー女子の心は確実に掴みましたって!!」
休憩に入ってすぐ、現場入りしていた担当エディターの樹(たつき)さんが賑やかに駆け寄ったきた。
黒いパンツスーツにセミロングの黒髪を後ろで1本にまとめ、トレードマークの赤ふちの眼鏡をかけた彼女はファッション雑誌の編集部にいるのが不思議なくらい地味。
だけど発想が半端なく派手で、僕を読モからカバーモデルまで引き上げてくれたのも彼女だった。
もう6年の付き合いになる。
 「『アラフォー女子の心』ってさぁ、メンズ雑誌じゃん。ウチ。どーなのよ、それ」
苦笑いを返すと、樹さんは目をキラキラさせながら僕を見上げて「いいんです、いいんです!」と表情をさらに明るくした。
「あたし達は妄想をカテに生きてるんで!」
「……はい?」
「流れ始めたんですよ〜、年末に撮ったカルペスウォーターのCMが。もう反響も上がってきてるみたいで、これで来月号でシキくんがバーンっとアピールしてくれれば、
メンズ雑誌だろうが何だろうがとりあえず女子は表紙買いするはずです!」
「とりあえずって……」
チーフリーダーの樹さんらしからぬ台詞に思わず乾いた笑いを零すけど、彼女がわりと真剣な眼差しを向けるから、これも戦略なんだろうなって理解した。
「今年の『REAL』の平均売り上げ目標7万部だっけ? 正直、厳しいよね」
「はい、そうです。だからシキくんには今年1年で顔と名前を売ってもらって、ウチの雑誌をもっと世間に広めて欲しいんです!」
「ゴメン。CMを引き受けるのでギリだよ。これ以上スケジュールは埋められない」
「分かってます。でも出来ることはやってもらわなきゃ生き残れません。『REAL』の看板はあなたなんですから」
「…………」
雑誌が売れない時代だって言われてる。
特にうちみたいな正統派ファッション誌は、どこかで変革が必要なんだ。
そのタイミングに僕が居合わせたなら、やはりココでも覚悟を決めなきゃならない。
「うん、頑張るよ。樹さんには親孝行しなきゃだしね」
「シキくん♥ せめて『姉孝行』でお願いします」
樹さんの飾りっ気のないヘラッとした笑顔は、僕の心のモヤさえも静かに消し去ってくれた。
「あ、そう言えばコレ良かったらどうですか? シキくん前に余ったら欲しいって言ってましたよね」
少しして彼女は手持ちのバッグから、アナスイのパーティー券を取り出した。
新作を宣伝するためにマスコミや出版社、VIPの為にひらかれるファッションショー。が好きそうだなって思って頼んでおいたヤツだ。
「ありがとう。でも確かこれって――」
「はい……そうなんです。今夜なんですよ、突然ですみません」
7時スタートか。仕事はお互い間に合うけど、今の感じだとたぶんは誘っても来ない。
かと言って他の女の子に声をかけるのも、色んな意味で気がひける。
もういらないかな……。
そう思って受け取るのをいったん躊躇うけど、ふと、僕とじゃなければ喜んで行くんじゃない? って気づいた。
蒼に渡せばイイ。
「樹さん、コレ友達に譲っても平気?」
「え? あ、はい。シキくんのご友人なら大丈夫です」
「助かる。じゃあ有難く頂くね」
お礼どうしよっか――って問いかけると、彼女は口角をあげて首を振り「土曜日の撮影も全力でお願いします!!」とだけ言った。
その日はたしか朝8時から横浜ロケで、5月号の初夏マリン特集。
天気予報には雪マークがついてたっけ。
「『アラフォー女子の心』ってさぁ、メンズ雑誌じゃん。ウチ。どーなのよ、それ」
苦笑いを返すと、樹さんは目をキラキラさせながら僕を見上げて「いいんです、いいんです!」と表情をさらに明るくした。
「あたし達は妄想をカテに生きてるんで!」
「……はい?」
「流れ始めたんですよ〜、年末に撮ったカルペスウォーターのCMが。もう反響も上がってきてるみたいで、これで来月号でシキくんがバーンっとアピールしてくれれば、
メンズ雑誌だろうが何だろうがとりあえず女子は表紙買いするはずです!」
「とりあえずって……」
チーフリーダーの樹さんらしからぬ台詞に思わず乾いた笑いを零すけど、彼女がわりと真剣な眼差しを向けるから、これも戦略なんだろうなって理解した。
「今年の『REAL』の平均売り上げ目標7万部だっけ? 正直、厳しいよね」
「はい、そうです。だからシキくんには今年1年で顔と名前を売ってもらって、ウチの雑誌をもっと世間に広めて欲しいんです!」
「ゴメン。CMを引き受けるのでギリだよ。これ以上スケジュールは埋められない」
「分かってます。でも出来ることはやってもらわなきゃ生き残れません。『REAL』の看板はあなたなんですから」
「…………」
雑誌が売れない時代だって言われてる。
特にうちみたいな正統派ファッション誌は、どこかで変革が必要なんだ。
そのタイミングに僕が居合わせたなら、やはりココでも覚悟を決めなきゃならない。
「うん、頑張るよ。樹さんには親孝行しなきゃだしね」
「シキくん♥ せめて『姉孝行』でお願いします」
樹さんの飾りっ気のないヘラッとした笑顔は、僕の心のモヤさえも静かに消し去ってくれた。
「あ、そう言えばコレ良かったらどうですか? シキくん前に余ったら欲しいって言ってましたよね」
少しして彼女は手持ちのバッグから、アナスイのパーティー券を取り出した。
新作を宣伝するためにマスコミや出版社、VIPの為にひらかれるファッションショー。が好きそうだなって思って頼んでおいたヤツだ。
「ありがとう。でも確かこれって――」
「はい……そうなんです。今夜なんですよ、突然ですみません」
7時スタートか。仕事はお互い間に合うけど、今の感じだとたぶんは誘っても来ない。
かと言って他の女の子に声をかけるのも、色んな意味で気がひける。
もういらないかな……。
そう思って受け取るのをいったん躊躇うけど、ふと、僕とじゃなければ喜んで行くんじゃない? って気づいた。
蒼に渡せばイイ。
「樹さん、コレ友達に譲っても平気?」
「え? あ、はい。シキくんのご友人なら大丈夫です」
「助かる。じゃあ有難く頂くね」
お礼どうしよっか――って問いかけると、彼女は口角をあげて首を振り「土曜日の撮影も全力でお願いします!!」とだけ言った。
その日はたしか朝8時から横浜ロケで、5月号の初夏マリン特集。
天気予報には雪マークがついてたっけ。